燭台切光忠はぱたんと冷蔵庫を閉じ、外した前掛けでやにわに手を拭って台所をあとにした。外廊下に出てみると、ぬるい風に煽られて風鈴がチリンと揺れていた。空は抜けるほど青くて、中天を越した太陽は地面をことさら皓く照らしている。たった今まで日の当たらない場所にいた燭台切はその明暗の差に思わずくらりと目眩がするくらいである。
庭の奥の林では、セミがじいじい鳴いていた。ときおり、鳥の鳴き声がする。名前をど忘れしたが、テッペンカケタカ、と鳴く鳥だった。しばらくして蝉と鳥の声に耳が慣れると、今度は山から引いている湧水が筧を通って手水鉢に落ちる、ささやかな音に気がついた。急に鹿威しが大きな音を立てて、燭台切は我に返る。今日は、そういう自然のちいさな音の一つ一つがよく耳に届く日であった。つまるところ、——静かなのである。
濡れ縁の近くの、庭が一望できるあたりまで来て、燭台切は立ち止まる。いつもなら、こんな長閑な午後にはどこからともなく短刀の子らが集まっては輪になって、やれ缶けりだ、隠れ鬼だとかしましく騒いでいるものだが、今日に限ってはその声がない。昨晩の、京都市中の見廻りのせいだ。
京都は三条大橋といえば、ふだんは特段に早い敵の槍がちくちく突っついてくるせいでなかなか進まないのが悩みの種なのだが、昨夜に限って様子が違った。どういうわけかその槍が見当たらないのだ。たまたま運がよかっただけかもしれないが、一周りして無傷で返ってきた小さ刀たちが、これならもう一回行ける、だから行かせろと口々主張するのである。負傷者の出る合戦へ一晩のうちに隊を何度も向かわすのをよしとはしない審神者殿が、昨晩はうんと悩んだ末、それじゃあ隊の顔ぶれをまるごと取り替えてもう一回だけなら、と決断した。一向に攻略の目処が立たない京の軍場に辟易しているのは、刀達だけでなく審神者も同じであった。その上で、十分慎重に慎重を期した判断だった。
京都の夜戦において、現在本丸に顕現している十振りの短刀を半々にわけ、一晩ごとに交互に出陣するのがここでの通例だったが、そういうわけで急遽残りの半分を第二陣に仕立て上げ、一晩に二度という異例の出撃が敢行された。二巡目はさすがに無傷とは行かなかったが、大橋を渡り切った先に濃い瘴気を見つけたという今までにない報告が齎されることになった。いつも橋の途中で引き返すことが多かった我らが本丸で、これは快挙といっていい成果である。
——以上が昨晩の顛末であり、本日午後、本丸に短刀たちの声がない理由である。
と、濡れ縁にほど近い立木の枝が、風のせいでもなしにざわりと揺れた。続いて、よっ、とわざとらしい声を出して飛び降りる影がある。やろうと思えば葉の一枚も揺らさずに降りてこられるだろうに、この大脇差は自分の気配がことさら薄いことを知っていて、軍場を離れるとこうして態々音を立てているところがあった。今のもそうとしか思えない空々しさで、だが確かにそうでもしなければ彼の存在には気付けなかったろう。
無人の庭を眺めるでもなしに立ち止まっていた燭台切は、突然降って湧いた大脇差に、はちみつ色の片目を素直に丸くした。
「おや、驚いた。青江くんじゃないか」
「ふふ。きみが腑抜けた顔をしているから、物珍しくて見物に来てしまったよ」
ふらふらと濡れ縁までやってきて腰を下ろす彼の隣に、燭台切も腰を下ろす。いつもの濃紺の内番着を着込んだ彼は、金の蛇眼をきゅっとすぼめて眩い空を仰ぐと、くん、と猫のように伸びをする。
「静かなものだねえ」
そう言う彼の普段は高い位置でくくられている鉄色の艶髪が、項のあたりでゆるく結わえられているだけなのに、燭台切は気がついた。視線でそれを察した青江は、毛先を人差し指に絡めて髪を下ろしているわけを言い訳する。
「お陰で昼寝が捗るよ」
「おやまあ、そんなところで何をしていたのかと思えば」
燭台切は咎めるような声を出した。それは、大の大人が昼寝なんてだらしない、という諫言ではなく、どうせならきちんと部屋で休めばいいのに、という忠告の意味である。
なにせ、昨晩の付き添い刀は他でもない、この大脇差であった。突発的な出来事ゆえに付き添いに適した他の脇差たちがみんな出払っていたせいもあって、すっかり面子のすげ替えられた短刀たちとは違い、彼は夕刻から明け方まできっちり二巡お役目をこなしたのだ。
「きみ、昨夜は出ずっぱりだったんだろう」
「まあねえ。でも、ほら。僕は所詮脇差、それも大脇差だからね。小さくて可愛い子たちほどじゃないさ。疲労のことだけどね」
「きみね、またそんなこと言って」
「おやおや、これはいけない」
本丸の台所番を一手に引き受ける燭台切の、どこか所帯染みた説教の気配に、本丸随一の偵察能力の高さを誇る彼はさっさと逃げを打つことに決めたらしい。燭台切の視線を吹っ切ってするりと立ち上がってしまう。
「部屋に戻ってちゃんと布団を敷いて休んだらどうだい」
青江は振り返ることなく、後ろ手にひらひらと手を振るばかりだった。向かう方向も、脇差部屋とはまったくの別方向である。
置いてけぼりにされた燭台切が彼の行く先を追いかけてみようかどうしようか、悩んでいると、きいきいとうぐいす張りの廊下が鳴って、次には頭の真上に、ふう、とわざとらしいため息が落ちてくる。
「あれがおとなしくいうことを聞くたまかい。ま、あれはあれなりに適当に寝床は確保するだろうから、きみは気にしなくてよろしい」
雅やかな紫紺の髪をちょいと上げて袂を紅白のたすきに括った歌仙兼定が、大きな竹かごを両腕で抱え柱に寄りかかり、かの脇差が去った方向を眺めていた。
「歌仙くん、おつかれ。畑当番はもう終わり?」
「こうも暑くちゃ仕事にならないよ。さっさと使う分だけ収穫して、あとは明日の当番にでも任せることにするさ」
床に降ろされたかごの中にはごろごろとトマトとキュウリが放り込まれている。毎朝採らねば次の日には大きくなりすぎる夏野菜の収穫は、夏の間畑当番の重要な仕事だ。
燭台切はしばし考える素振りをした。
「明日の当番って、ええと」
「あれだ、あれ。今日と明日の当番を交換してやったのさ。今朝方、青白い顔して畑に行こうとするもんだから」
なるほど腑に落ちる。さっきからあれ呼ばわりで、今もさも迷惑そうな顔を見せてはいるが、なんだかんだ彼は情に厚い刀だ。押し付けるように当番を変わったのだろう光景が、燭台切の目に浮かんだ。
「まったく、調子が出ない。あれもそうだけど、うちの庭がこんなにも静かとだとね」
「うん? 歌仙くんなら、こういう静寂が風流でよいとか言うと思っていたけど」
「僕に内番が回っていないときなら歓迎だがね。誰の声も聞こえない畑で雑草をむしる僕の気にもなってごらん。虚しいったらありゃしない」
はたはたと、袖に腕を突っ込んで揺らす行儀の悪さは、雅を愛する文系名刀らしかぬ所作だったが、理由は昼下がりの暑さばかりではなさそうだ。なにせ、二人して黙ってしまうと、間を埋める音がない。
「ないならないで、寂しいものだよね。子供の声というのは」
「そうまでは、言ってないさ」
「そうかな」
「そうさ」
チリン、チリンと、慰めるように風鈴が間をつなぐ。蝉しぐれが、寄せては返す波のように強弱する。風はあいも変わらず、ぬるい。
歌仙はしばらく黙ってその風に目を細めていたが、まるで静けさに嫌気がさしたように頭を一振りしてもたれ掛かっていた柱から体を起こした。
「短刀たちが起き出す前に、水浴びを済ませることにするよ。きっと寝汗をかいて風呂場に押し寄せるだろうから」
「そうするといいね。もう後半刻もしたら起きるだろうから」
野菜を台所に置いてから風呂場へ向かうという白い長着の背中を見送り、燭台切も長居した濡れ縁を後にする。向かう先は粟田口の大部屋で、今は短刀たちが十振ならんで昼寝しているはずだ。そもそも初めからそこへ行くつもりで、燭台切は廊下を歩いていたのだった。
「おじゃまするよ」
「どうぞ」
開けっ放しの障子戸の一応外から声をかければ、すっと背筋を伸ばして几帳面に正座した粟田口の長男が、団扇をしずかにそよがせている。部屋の中に入ることはせず、廊下から覗きこめば、小さな刀たちが刀派問わず、一期一振に頭を向けるようにしてころころ寝転がって休んでいる。それぞれの腹には薄掛けが乗せられていて、さて誰がそんな気の利いたことをしたのかな、と声に出さずに思い巡らせていると、一期一振がすかさずに言った。
「主ですよ。腹を冷やすと良くないと、わざわざ押入れから引っ張りだして」
「彼、本当に心配症だね」
そもそも短刀たちに昼寝を、と言い出したのもその審神者であった。この本丸では、どんなに夜が遅くなっても朝寝はさせない。決まった時間に起きて、みんなで朝食をいただく。その代わり、夜戦に出たり、長期の遠征帰りの刀には、夕べに早く床入するようにだとか、時にはこうやって昼寝が奨励される。ここのところ夜の京に出陣している短刀たちには以前からかわるがわるに昼寝の時間が取られていたのだが、こうして短刀全員揃って昼寝をするのは今日が初めてだった。それでは、本丸中が奇妙な静けさに包まれるわけである。
「こんなに、静かになるものなんだね」
何もない日までお祭り騒ぎの愛染国俊が、飛んだりかけたり一箇所にじっとしてられない今剣が。当番でもないのに厩や畑に顔を出して嬉しそうに手伝う秋田が。人一倍職務に忠実で、本丸中でちょこちょこと雑用をもらう平野と前田が。仔虎を追いかけて転んでべそをかく五虎退と、その傷口に容赦なく消毒液をぶっかけて更に泣かせる薬研が。どこで覚えてくるのか色仕掛けの研究に熱心な乱と、反応がいいからやたら餌食にされる厚が。短刀たち、とひとくくりにされて叱られるのがまんざらでもない小夜が。
まるでいつもの喧騒を感じさせず、すよすよとさやかな寝息を立てて眠っている。まるで人の赤子のように、なにも案じずに眠っている。
すべての子に均等に風がゆくようにと団扇を繰っていた一期一振が、はた、とその手を止めた。
「主が」
途方に暮れたような声だった。
「主が、私に、謝るのですよ。『あなたの弟達を、いたずらに傷つけることしかできなくてごめん』と。『あなたたちに、見送ることしかさせずにごめん』と」
それは、近頃の幕末期の京のことを言っているのだろう。確かに、短刀たちは出陣するたびに腕や腹に決して小さくはない傷をつけて帰ってくる。夜戦の上に市街地戦であるということが災いして、太刀やそれ以上の刃渡りを持つ刀たちはおいそれと付いて行くこともできない。
審神者は、それを悲しいと見る。小さいものが宵闇に放り出されて体中に傷を作るのが、哀れで痛々しいと感ずる。
だがそれは、と燭台切は思料する。それは所詮、人間の考えだ。
一期一振は茫として言葉を継いだ。
「私は、思っても見ませんでした。人間とは、そのように考えるものなのですね。なあ、光忠殿。私は、薄情なのでしょうか」
彼は燭台切のことを振り返りはしなかった。いっそ独白とも言える声音で、困ったように言うのである。
「見送りに『効く殺してきなさい』と言い諭し、出迎えては『よくやりました』と励ますのは、兄として失格なのでしょうか」
一期一振の、一番近くに陣取っていた前田が、風のなくなった室内に寝苦しそうに寝返りをうつ。彼は団扇を揺らすのを再開した。
燭台切の答えは、否でも諾でもなかった。
「きみ、思ってもいないことを人に聞いて、どうするんだい」
「おや。ばれましたか」
はは、と掠れるような音で彼は笑う。
「いや、しかし、私は確かに戸惑っているのです。この肉の体はなにもかも人間みたいだというのに、肝心のところで人間じみていない。主君の言うように、幼子を慈しむように弟達を愛でることは、できやしないのです」
まあ、ことさらに僕らの主は、臆病で心配症で、慈悲深いお方だから、と燭台切は前置きをした上で、それにしても、と継ぐ。
「それにしても僕らは、刀だからね。人間のふりはできても、所詮『ふり』でしかない、ということかもしれない」
それは燭台切が記憶している精一杯の人間に関する知識である。一期一振にしろ自分にしろ、焼けて記憶が無いところは多かったが、それでも覚えていることはある。
「確かに人間というのは、子供を夜に軍場に出したりはしない。肋骨を避けて刃を押し込むコツを教えてやったりはしないし、首の掻っ切るのの思い切りの良さを褒めたりはしない」
僕らは、刀だから。と燭台切は繰り返す。
しかし、でも、困ったな。
「でも歌仙くんは、子供の声が聞こえなくて張り合いがないと言うよ。青江くんは、小さい子を可愛い可愛いと甘やかす。僕は、僕だって――冷蔵庫に今日のおやつを冷やしてある。昨日はみんな頑張ったから、特別に生クリームとさくらんぼを載せたよ」
昨日遅くに短刀達が帰ってきてから、今日のおやつはプリンにしようと決めていた。とっときの缶詰を開けて、特別に生クリームも泡立てて、ちょっと豪華なのにしようとさえ思っていた。
戸惑っている、とそう口にしながらも、一期一振は団扇を仰ぐ手を止めない。
「ねえ一期くん。きみだって多分、明日の昼寝からは弟くんたちの腹に薄掛けをかけてやることを忘れないよ。まるで人間みたいにさ」

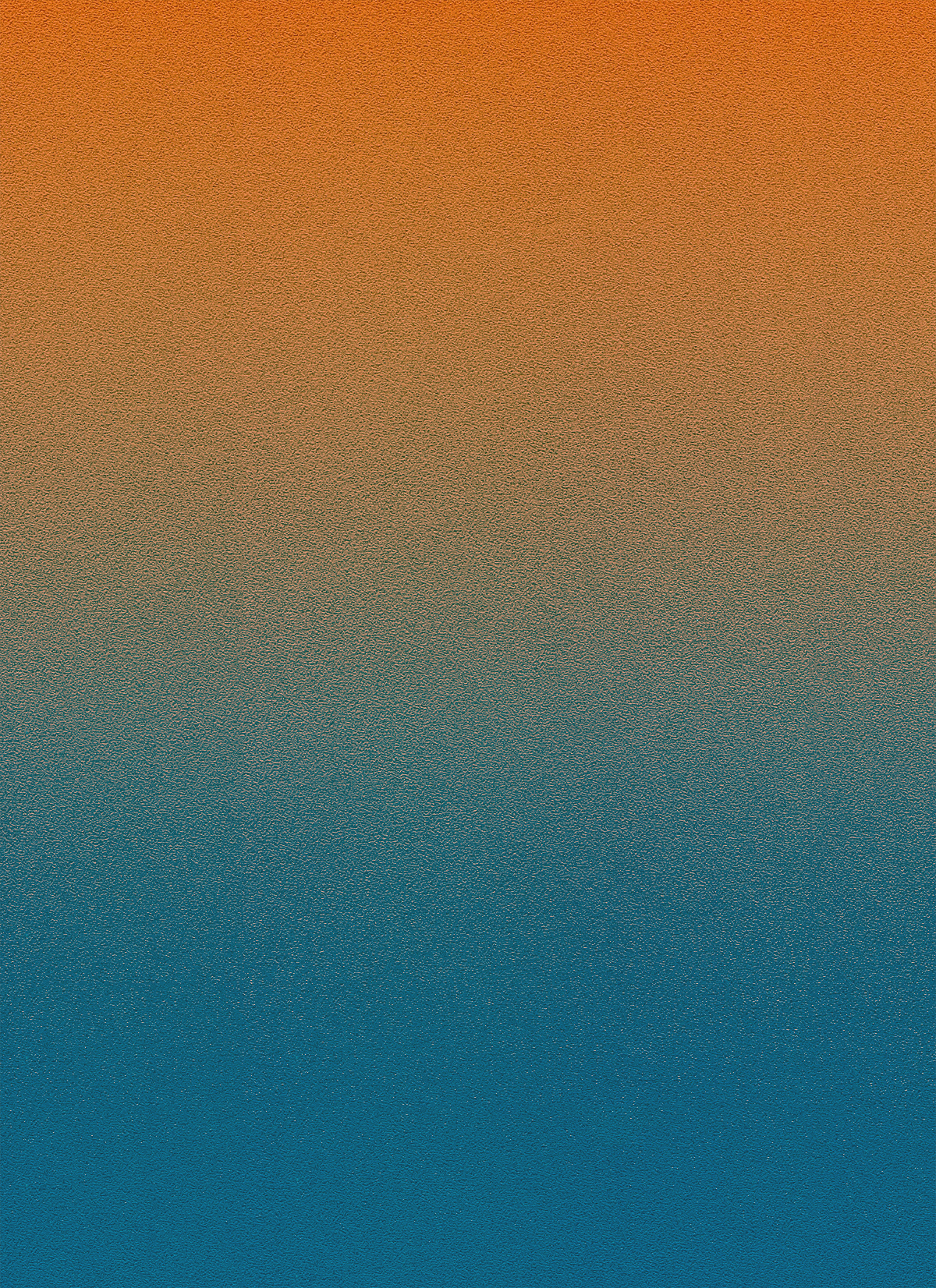
コメントを残す