今朝方から、藤四郎の短刀たちが何かを探して走り回っている。大柄の刀と違い足音もパタパタと控えめなので、注意してやろうという気にもならない。盆正月に親戚の子が集まってはしゃいでいるのを思い出して懐かしい。
暦はまだ十月に入ったばかりである。朝晩は冷えるようになったが、昼の日差しは心地よかった。障子越しの日差しに眠気を誘われる、午後。
書類仕事に精を出していると遠くから一人分の短刀の足音がして、部屋の前を通り過ぎたと思ったら慌てて引き返してきた。
おや、と顔を上げると、襖の向こうから「主様、」と控えめに呼ぶ声があった。前田藤四郎だった。
「おいで」
「失礼致します」
いつもながらの折り目正しさで膝をついて部屋に入ってきた彼は、書類を書く手を止める審神者ににじり寄ると、少し躊躇った様子で、
「主様、お手を貸していただけますか」
などというものだから、何か手伝いが必要なのかと首を傾げる。
彼は遠慮がちに審神者の手に触れた。それからそれをそっと持ち上げ、しげしげと眺め回す。何の変哲もない男の手だ、一体何が面白いのだろうと好きにさせていると、小作りの人形のような顔が近づいてすんと鼻を鳴らして匂いを嗅ぐものだから、流石にそれには驚いた。
何もやましいところはないが無性に居た堪れなくなった頃に、ようやく手が離される。
「違いますね……」
そうか、違ったのか。なにが違ったのかは分からないが、前田が酷く残念そうな顔をするのでこちらまで悪いことをした気分になった。
「力になれなかったようで、すまない」
「いいえ! 何も説明せず、申し訳ありません。……実は、探しものをしておりまして」
「そういえば、朝から賑やかだったが、それか?」
「はい。今朝方のことなのですが――」
前田の話によると、こうだ。
藤四郎たちは屋敷の中でもとくに食堂に次いで大きな部屋を宛てがわれ兄弟揃ってそこで寝起きしているのだが、その部屋に朝方侵入者があった、らしい。
らしい、というのは、それが敵意を持ったものではなかったからか、そこで休んでいた藤四郎の刀の誰ひとりとして目を覚まさなかったからである。
「そんなことがあるか?」
侵入者、のあたりで口を挟みそうになったが、ぐっと耐えて最後まで聞いてみると、どちらかと言えば皆で夢でも見ていたような話だ。そう伝えると、前田は少し気分を害したようだった。少し膨れた頬が愛らしい。
「骨喰兄様も鯰尾兄様もそうおっしゃいます。兄たちはなにも覚えていないようなのです。ですが、私達短刀は皆それを見たのです。白いきれいな指が前髪を梳いて、頬を撫ぜてゆきました。冷たい手でしたが、佳い薫りがして、とても気持ちが良かった」
「ははあ、だからお前たちは、今朝からその手の持ち主を探しているのだな」
「はい」
「して、それはいったい何者なのだろう」
顎を撫ぜながら問う。返事を期待したものではなかったが、前田はたぶんですが、と前置きをして、それから恥ずかしそうに言うのである。
「母様、なのではないのでしょうか」
ぞっと背筋が冷えた。
それから数日と立たず、審神者の庭は突如秋の気配に包まれた。金木犀が咲いたのである。前触れもなく薫る花である。昨日まで気が付かなかったが、思えば空もよく晴れ、高い。いつの間にか秋が来ていたのだろう。
秋の気配のことを金気、と呼ぶと知ったのは何の拍子だったか。金の名の付く花を、鉄の体を持つ子が母と思い込んだとしても、それほど無理のある話ではあるまいと、審神者は己を納得させることにした。
庭に面した縁側から、杜若の垣根が見える、その並び。
はらはらと黄金の花を降らせる木の根元で、あの日母を探し回っていた藤四郎の短刀たちは、体を寄せ合うようにして眠っている。

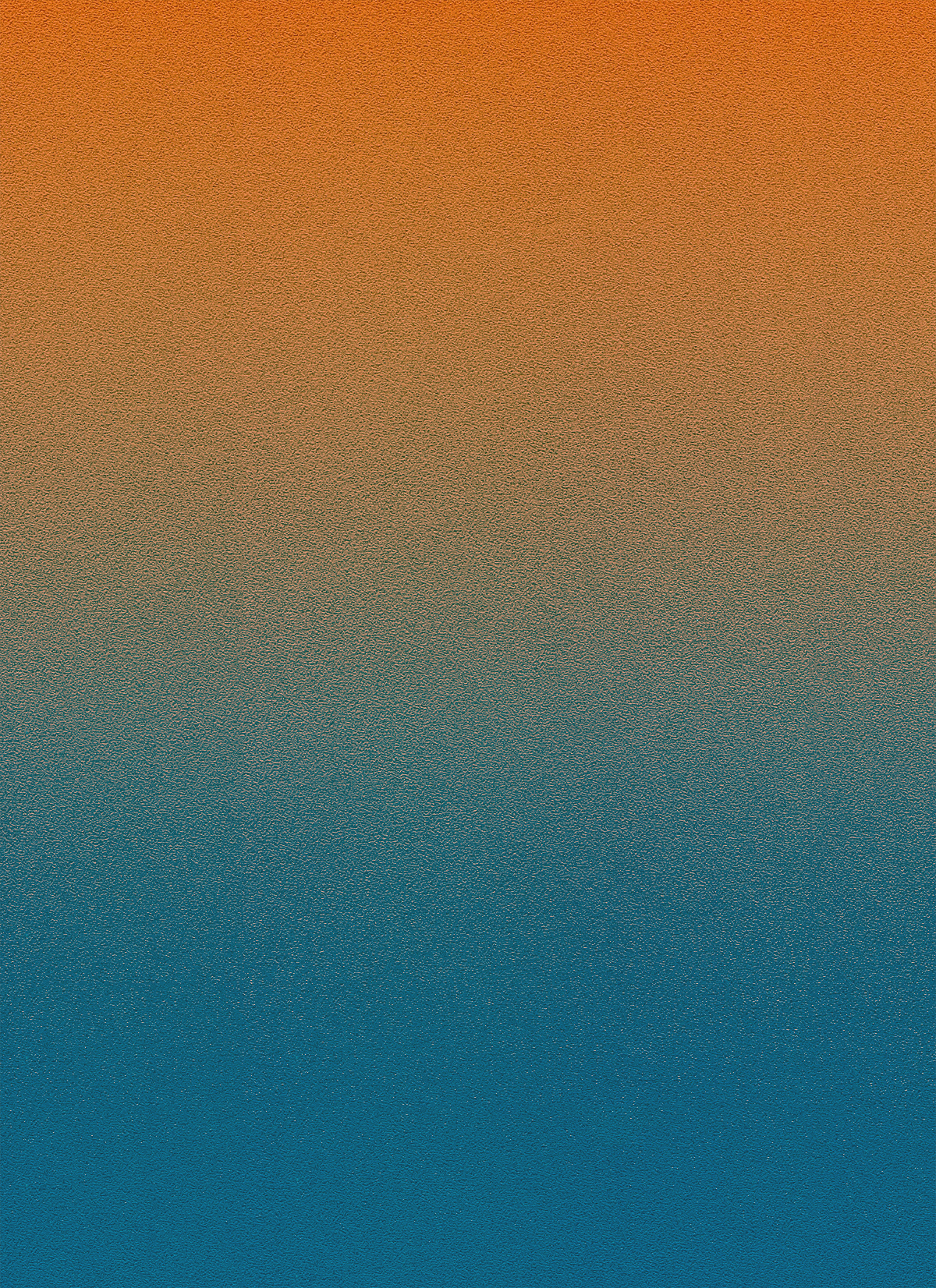
コメントを残す