その日はたまたま書類仕事が多く、夕餉の後まで持ち込む有様だった。ようやく目処が立とうという頃にはぽっかりと満月が昇っていて、それを雪見障子越しに見つけた近侍筆頭のへし切り長谷部が、月が綺麗だとか、なんだとか、とにかく珍しく風流刀のようなことを云う。普段はまるきり堅苦しい物言いしかしないやつなので、なにか思うところでもあるのかと執務を切り上げ月見酒に誘った。案の定、嬉しげな顔をして肴を見繕ってくると云うので任せる。
障子を開けると、火鉢で温まった空気が一斉に逃げ出したが、思っていたほど寒くはなかった。書類仕事で煮詰まった頭が冷えて心地よい。しばらく突っ立っていたら流石に寒気が来たので、慌てて丹前を引っ張りだして羽織る。
庭の隅にしぶとく踞っていた残雪は、先日の春めいた陽気のおかげですべて乾ききった。あとはもう、春一番を待つばかりのこの頃である。桜ばかりのこの庭で池のほとりに一本だけ立つ白梅は、気の早いものでいつの間にかもう蕾を付けている。その向こうに、南中に向かう満月が輪郭を柔く溶かして浮かんでいた。
執務室から座布団を二枚、縁側に引っ張ってきて座敷を用意していると、右手に燗、左手には湯気の立つ皿を持って長谷部が戻ってきた。どうやら厨番の光忠から宴会のおこぼれを頂戴したらしい。
「おお、桜エビ」
「初物だそうですよ」
酒は越州、越乃寒梅。ぬるく点けた燗がとろりと喉をすべるのが良い。月明かりの下でもわかるくらい赤く色づいたエビは、網で炙って塩を振っただけの質素な味付けだが、これが嘘みたいに美味かった。行儀悪く指でつまんで殻ごとばりばりやっていると、酒も肴もみるみる減ってゆく。そのせいか、いつになく酔ってしまって、こんなのは三日月宗近が来た晩の大宴会以来である。
「この時期の月は、いいな」
「はい」
「真冬の頃ほど冴えてはいないが、朧月ほど甘すぎない。触れたら指ごと切れてしまいそうな月より、おれはこのくらいのほうが好きだよ」
長谷部はなぜか不満気な顔をする。
「主にそれだけ褒められれば、あの月も誉れでしょう」
「何だ、妬いたか」
「刀が月に妬くものですか」
「お前が云ったのだぞ、月が綺麗だと」
「主はものの風流を解されない」
まさか長谷部に風流を説かれるとは思わなかった。釈然としない思いごと、杯の残りを胃の腑に流した。
庭向こうの大広間では、今宵も酒飲み連中が夕餉の後から大騒ぎしている。その歓声もいまはどこか遠く、おぼろげだった。こんな時間に、どこかで鶯が鳴いている。春来たばかりで、どこかぎこちなく下手くそだ。
その声に耳を澄ませていると、突然、ぶん、と耳鳴りがした。例えば耳元で御手杵が得物を振ったような音である。続いて間をおかず、ぽとり、となにかが落ちる音がする。今度はすぐ手元のことで、素直に視線を落とすと、真白く発光する芍薬の首がひとつ、落ちている。
「は」
疑問が声になる前に、もう一度、ぶん、と耳鳴り。それから手元と、同じことが繰り返す。転げ落ちた勢いのまま指先にあたった花びらは、ほんのりと冷たく、やわかった。
どういうことだと顔を向けると、近侍筆頭は手酌で杯を満たしながら、
「こういうこともあるでしょう」
と訳知り顔で云った。いつもは何くれ構ってくれるというのに、さっきので機嫌を損ねたのか、随分そっけない。そも、彼が一番こういう現象を好まないと思ったのに、意外だった。なんとなく尻の座りが悪くなって、濡縁に転がった芍薬を一つ指でつまんで、月光に透かしてみる。自ら光っているように見えたが、なんの仕掛けもないただの花であった。
そうしているうちにも、長谷部の足元に、あるいは己の膝の上に、肩越しに、ぶんと音がするたび花は落ちた。
花を元に戻して、代わりに銚子を目で探すと、察した長谷部が酌をしたが、杯を半分も満たさぬうちに酒が切れた。仕方なく、それをぐっと飲み干す。くらりと目が廻って、勢い背が床についた。ひんやりとした床板が心地よい。目を開くと、満月が目の前に迫っていた。いよいよ南中しようとしている。
「主があんまり褒めるからですよ」
ちょっと拗ねたような声がして、やっぱり妬いてるんじゃないかと笑いたくなった。そうか、褒められると花を降らせたくなるのは、月も同じか。得心した心地で、瞳を閉じる。
「悪いが誉れは、譲ってやれよ、今晩くらい」
宴もたけなわ。大広間の方で、どっと笑い声があがる。こちらは月の落ちる音しかしない。

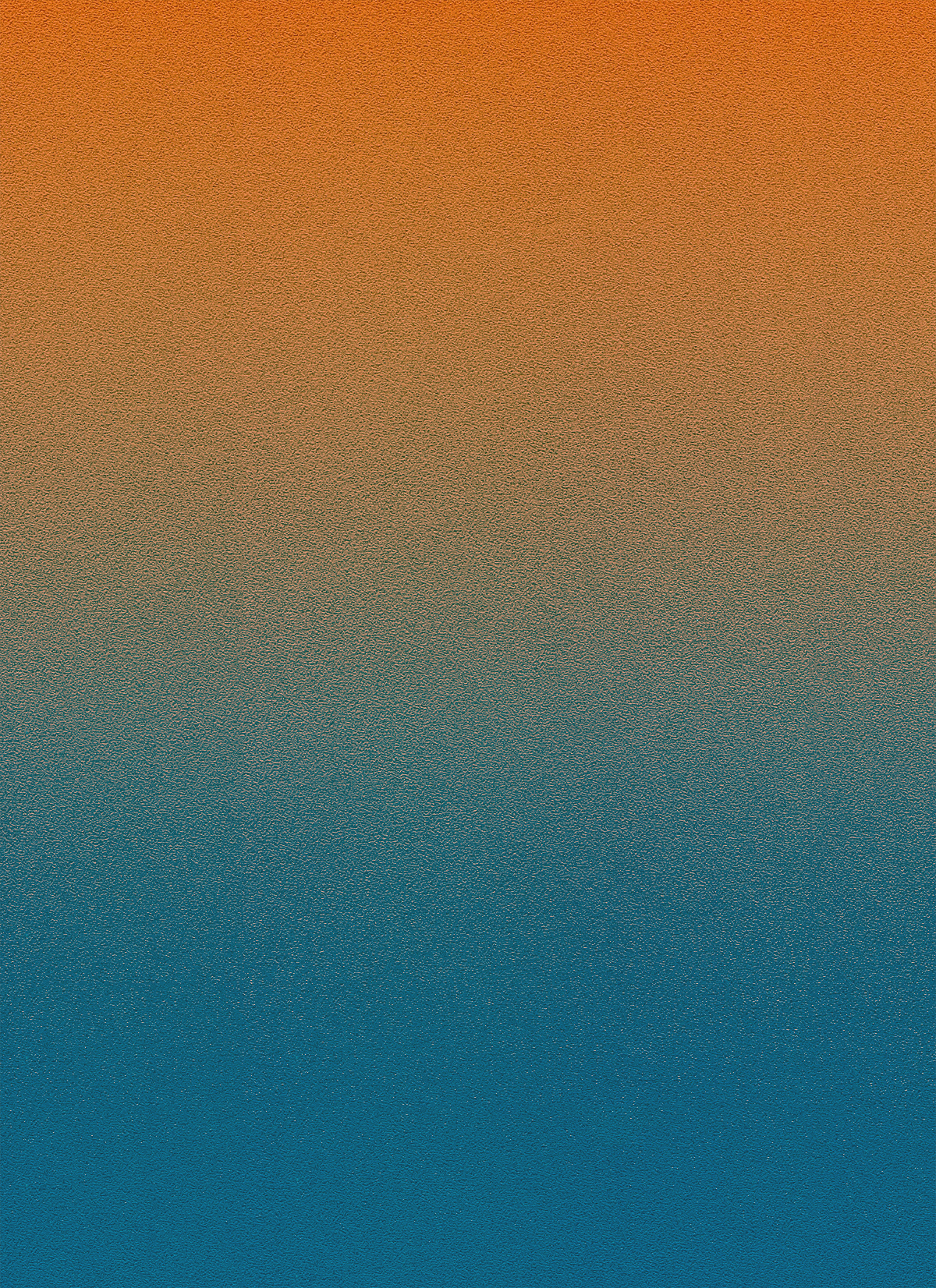
コメントを残す