ある夜、皆が寝静まった本丸の庭に、審神者がぼうと立っている。半纏の前を握りしめて、さみぃさみぃと厠から帰る道すがら、それを見つけた同田貫がすわ敵襲かと驚いたのも無理は無い。雪こそないが、しんしんと冷えた夜半の庭に、白の薄い寝間着一枚で、彼はじっと何かを見上げていた。
ほうっといてもよかったが、明日になって審神者が冷たくなって見つかっても寝覚めが悪い。なにより彼なしでは、同田貫はただの鉄である。もう二度と自らの体で戦うことなどできないだろう。そう思えば、声をかけてやることくらいは容易かった。
「おい、何してる」
「ああ、お前か」
「星をね」
審神者は一度きり同田貫を見やると、すぐにまた上を向いてしまった。
「星を見てる」
「星ぃ?」
つられて見上げれば、まァたしかに、そこには星空がある。月のない夜のことだ、チカチカと瞬くそれらは打刀である己の目にはいっそうるさいほどだ。しかし、それが一体どうしたというのか。同田貫にはわからない。
「なあ、なにがそんなにおもしろいかよ」
「まあ、きみには、わからないかもしれないね」
審神者はかすかに笑ったようだった。同田貫は、いい加減部屋に帰りたかったので、適当に相槌した。
「そりゃあ、俺には情緒はわからないが」
「いいや、たとえここにいるのがあの歌仙兼定だろうが、同じだろうさね」
なんだそりゃ、と声に出して言ったのだか、思うに留めたのか。そのあたりの記憶は曖昧だ。
そんな夜のことを、同田貫は唐突に思い出している。普段、同田貫はいくさのさなかに他所事を考えることなどないが、なぜか急に、思い出したのだった。阿津賀志山のてっぺんの、森が急に開けた平らな場所。藍地にたっぷりの砂金をこぼしたような星空は、あの夜の数倍もうるさかった。
審神者がこの空を見る日は、永遠に来ないであろう。これは過去の空である。人の子が決して立ち入れぬ太古の空である。そして今やその空の下には、異形の影がうろつき、ざわりざわりとうごめいている。
同田貫は彼の刃を腰から引き抜いた。戦が始まる。その頃には、もう星空のことなど忘れてしまっていた。

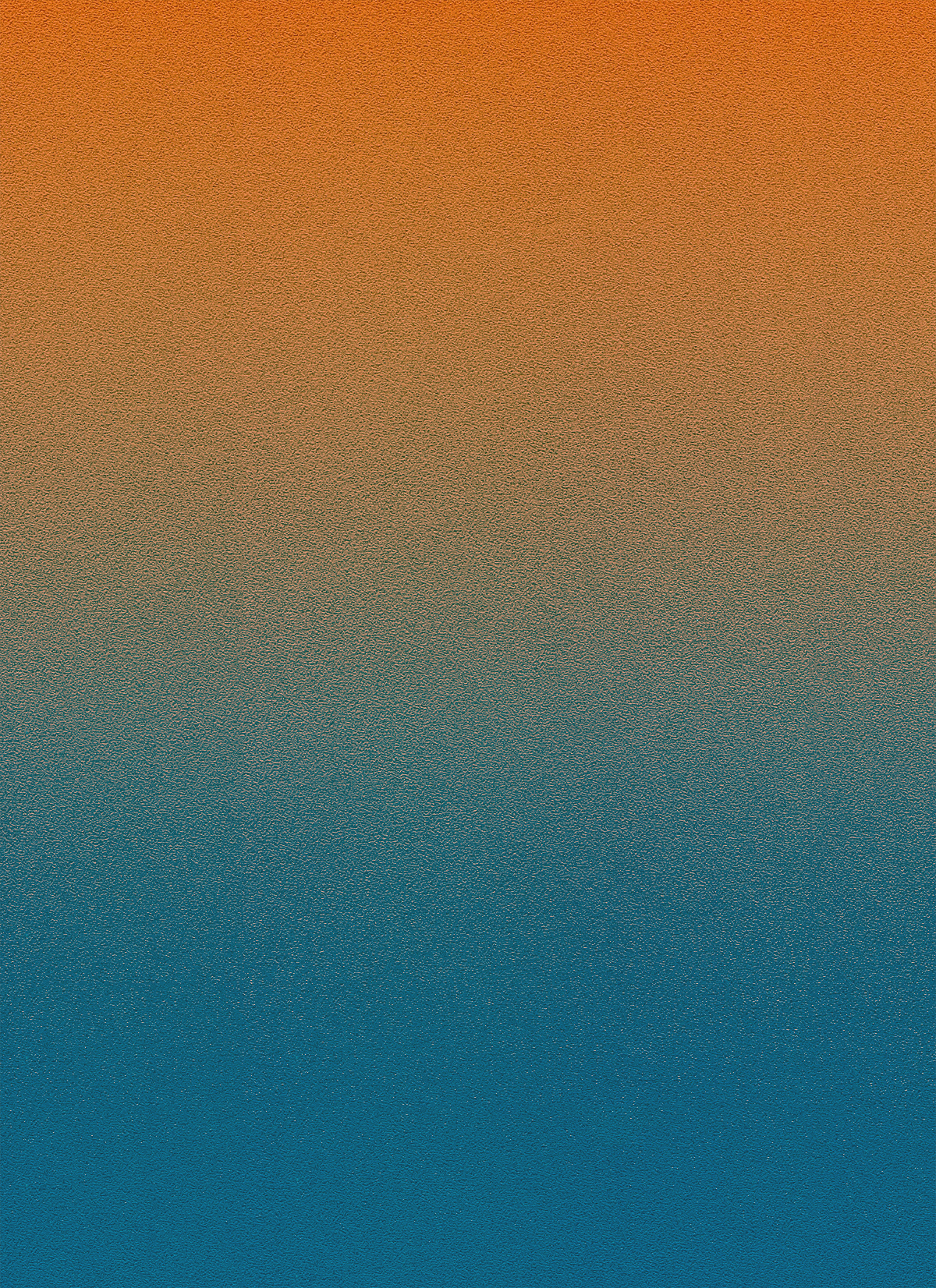
コメントを残す