池のほとりの白梅がようやく一輪ほころんだ。
桜ばかりのこの庭で唯一の梅の木は、他のどの草木より一番に春を告げる、いわば春の偵察のようなものである。あれが咲くと、春が来る。誰もがそれを心得ているから、今朝の吉報に本丸の刀は大いに喜んだ。
そんな日の午後のことである。昼餉の後執務室で書類整理に勤しんでいると、外から一期一振の怒声が聞こえてきて、何事かと立ち上がる。
「おい、どうした」
「主、これは、申し訳ありませぬ」
一期一振の前には粟田口の刀が数振、地べたに正座して悄気返っている。こちらを振り返った粟田口唯一の太刀は、一瞬前までその優しげな顔に浮かべていただろう怒気を引っ込めて、長兄らしく弟たちの非礼を詫びた。なにがなにやらわからず呆然としていると、いつもの無表情をした骨喰藤四郎が、捧げ持つように差し出すものがある。長さといい太さといい、まるで彼の本体と見間違えんばかりではあるが、
「ああ、これは」
今朝咲いたばかりの花を一輪付けた、梅の太枝であった。
聞けば、木の上で降りられなくなった五虎退の虎を骨喰が助けんとして、踏み抜いたと云う。
「そんなことでこれほどの枝ぶりが折れるとも思えないが」
一期と二人して覗き込んだ枝の折れ口は、どうやら元々傷んでいたものらしかった。
「この冬は厳しかったからかな」
「あるいは、寿命かもしれませんな」
いずれにしろ、不注意と不運と不可抗力の重なった事故である。折れてしまったものはどうしようもなかった。その場に解散を言い渡し、執務に戻るべく踵を返す。最後まで残っていた骨喰は、黙って梅の木を見上げていた。
その晩は、真冬に戻ったような氷雨になった。翌朝はよく晴れたが、空気は凍えそうに冷たい。それから数日が経つが、三寒四温の言葉のままに春に向かっていたはずの本丸の季節はまるで冬至の頃まで巻き戻ってそこで足踏みしているようだった。
気の早い刀が用意した山菜採りの篭が厨の隅で蜘蛛の巣を張っている。近侍のへし切長谷部が、炭の在庫表を見て買い足すべきか思案し出した。このまま冬が続くのであればそれも考えねばならぬ。
骨喰が執務室を尋ねて来たのは、そんな折である。
「主、あの枝を返してくれ」
「なに?」
問いただす暇さえなく、傍若無人に脇を通り抜けられるものだから、止める手が遅れた。相変わらずの無表情のまま、畳に散らばる書類を危なげなく避けつつ骨喰が目指したのは部屋の一番奥であった。そうして彼が手にしたのは、あの日折れた梅の枝である。花をつけたまま捨てるのが忍びなく、しかしあれほどの枝ぶりを挿す花瓶も見当たらない。仕方なく刀掛けに掛けておいたのだが、これが思いの外具合よく収まったので、そのままにしておいたものである。
あの日咲いた一輪は、健気なことにまだ咲いていた。開けっ放しの障子から縁側へ出て、そのまま庭へと飛び降りた骨喰は、それを剣先に見立てたものか、まるで己の本体を振るうかのように、気合一閃、
「破ッ」
目に見えぬ何かを切り裂いた、その瞬間、強い風が吹いた。
東風であった。ごうと耳元を通り過ぎた風は、執務室の書類を巻き上げ、渡り廊下を掃き清め、厨の煤を吹き飛ばし、庭の草木を撫ぜた。木陰の蓑虫を払い、固い土を緩ませ、池の水を揺らし、桜の枝を擽った。本丸中を駆け巡って、そうして、空の彼方へと昇っていた。
庭がようやく静けさを取り戻した時、何かが劇的に変わっていたということはない。ただ、真冬のように凍えていた空気が、ほんのり土の匂いをさせて温んでいるだけだ。
一部始終を目撃していたはずなのに、これっぽっちも事情を理解できなかった審神者の前で、骨喰はやはり無表情ではあったが、やや満足気に己の得物を叩いた。一輪付いた梅の花は散っていたが、池のほとりの老木には溢れるように白梅が咲いていた。

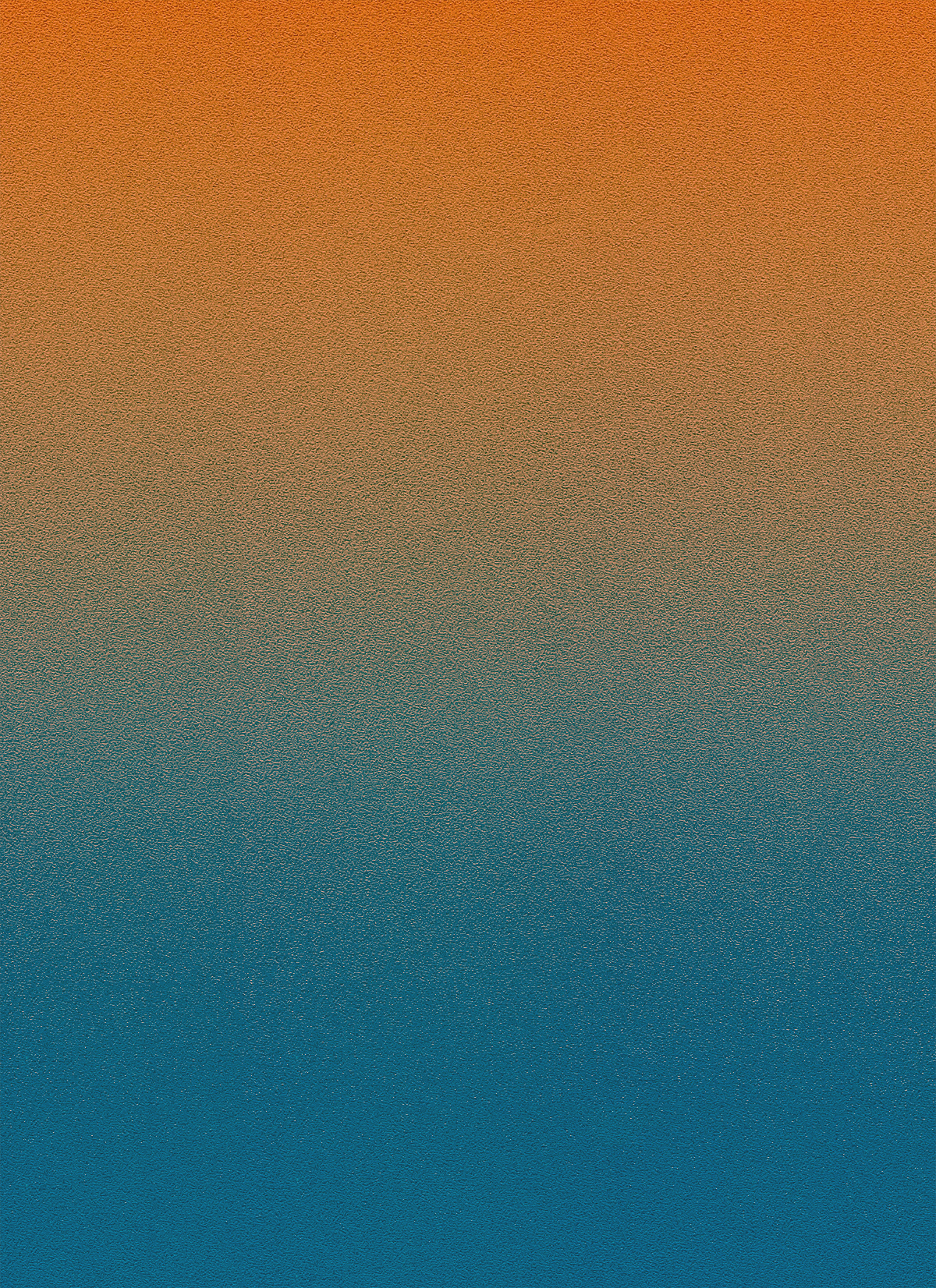
コメントを残す