雲ひとつない好い天気だった。
こんな日は敵機影がすぐ見つかるからいい。遮るもののない空は、遥かかなたまで見透かせるようだった。そのぶん、こちらの機影も相手に見つかりやすいのだが、そこは五分と五分である。互角の状況でいかに敵を圧倒するかこそが戦の醍醐味だ。
しかし、空は静かである。
敵機はおろか、雁のように群れなす艦上機のひとつも見当たらなかった。圧倒的な運動性能でもって飛び回る戦闘機、粘り強く懐に入り込んで魚雷を落とす攻撃機、獲物を狙う鷹のように剛胆で奔放な爆撃機。どの姿もない。
艦上機がないということは、空母もない。やたらと怪我しがちな兄とやたら運のいい弟の双子艦。空母としては少しずれたところのある改装艦。
ともに海を駆けた僚艦の姿もない。年上でありながらどこか子供っぽい彼らも、箱入りの弟分、妹分である彼らも、どこにもいない。
長門は悲しまなかった。
その代わり、数奇な事もあるものだと思った。
兵器として生まれた以上、戦場で死ぬものだと思っていたが、それが自分はどうだ。こんなに穏やかな海に、一人立っている。
節々が痛むが、まだ立っていられぬほどではなかった。なに、そこは日本男児の意地である。見栄と言わないこともない。ただし、手持ち無沙汰であるというのが目下の苦痛といえばそうだった。
長門は一人であった。
一人であること、そしてそれが、自分であること。そこに意味を見出すのは人間の仕事だ。長門はただ、こんなこともあるのだろうなと漫然と覚えただけである。
誰も乗っていない、動かすもののいない艦。火がともらない機関室。操舵をする者もなく、指揮を執るものもいない。機銃も主砲も手入れを怠って錆付いている。艦首に旗が揚がらなくなって、もう幾許か。
体の中が空虚である、これを寂寥というのならば、やはり自分は一人でさびしいと、そういうことなのだろうか。
やめよう。
長門は空を仰いだ。
なにせ今日は晴天である。雲ひとつない空である。歌のひとつも歌いたい出したいような、そんな天気である。
せっかくなので、歌おうか。誰もいないことではあるが、ひとつ景気づけには行進曲がいい。
知っている歌は多くはないが、なにせわれ等の歌であるから、忘れるはずのない歌を、長門は歌った。
戦艦長門
1946年7月29日、米軍の原爆実験で沈没。

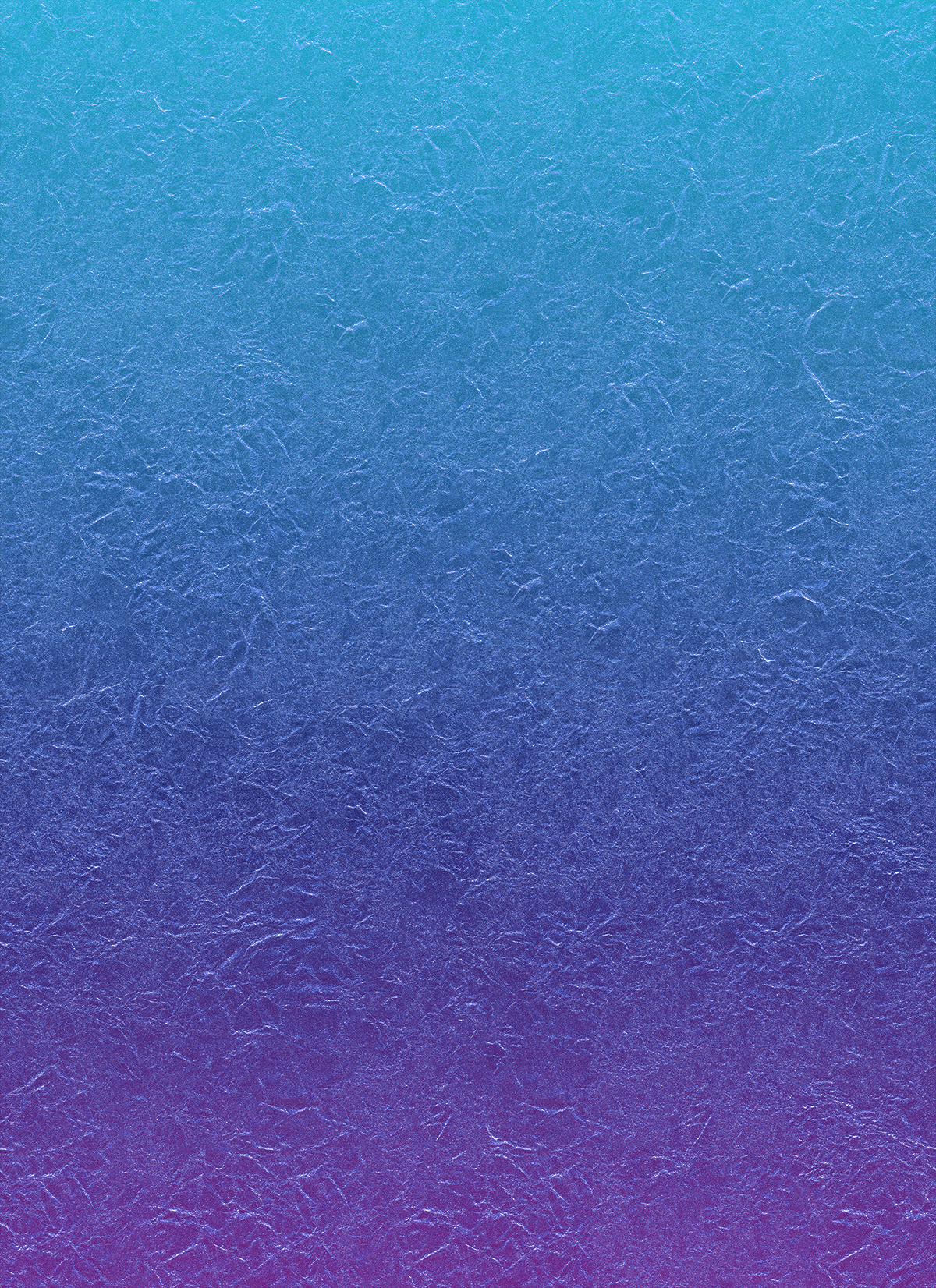
コメントを残す