桜綻ぶ三月の終り。
深夜のコンビニからの帰り道、伊藤八宵は一人の外人を拾った。
◆ ◇ ◆
――それから四ヶ月。
八宵は未だにその外人を家に住まわせている。学生時代よりは多少広いとはいえ、賃貸マンションに男二人。しかもその一方は身長百八十センチ超のドイツ人とくれば不便には違いない。
ウーリッヒ・メーアヴォルフ。八宵が研究生として席を置く大学に、交換留学生とやってきた史学科の学生。
道に迷って途方に暮れていたところを拾っただけで、それ以上の接点はない。専門も違う、年齢も差がある。初対面で意気投合したというわけでもない。本来なら一時的な関係で終わってもおかしくなかった二人。なのに、なぜウーリッヒが未だ八宵の部屋に厄介になっているのか。
それは、偏に八宵が引き止めたからに他ならなかった。
八宵には彼を捨てられない理由があった。
その理由を口にしたことはない。なぜなら、絶対に信じてもらえない話だからである。
――前世で出会った記憶がある、など誰が信じるだろうか。それも、兵器として生きた記憶の中で、なんて。
午後九時を過ぎてさすがに人気のなくなった工学部棟に、煌々と明かりの灯る一室があった。その研究室の扉が、そっと開く。
パソコンに向かい黙々とキーボードを叩いている八宵は気づいていないのだろうか、振り返る気配もない。闖入者はおもむろに部屋の中を見渡して、壁際に並んだ古いソファに目を止めた。所々スプリングの飛び出したソファには薄手の毛布が丸まっているばかりか枕になりそうなクッションまで転がっていて、その些細なスペースが日常的に使われていることがわかる。
闖入者は呆れたようなため息を憑いた。
その段になって、八宵はようやく手を休める。ため息混じりに、ワーキングチェアをきしませて振り返った。
「未成年がこんな時間に一人で外をうろついてていいのかな、九条君よ。……通報すっぞ」
「まあまあ、そう固いこと言わずにさあ」
そこにいたのは近所の高校の制服を着崩した少年だった。九条九。彼と八宵の接点を説明するのは長くなるが、簡単に言うならば、同士――あるいは共犯者。彼もまた、兵器として生きた記憶を持つからである。
「俺と伊八っちゃんの仲じゃないの。……うわあ、ひでえ隈。昔みたいだ」
ひょいと八宵の顔を覗き込んで、九は苦笑した。
「何しにきた」
「伊八っちゃんが根詰めてるって噂を聞いて」
「また霧島さんかよ……何なのあの人。なんでそんな俺情報持ってんの」
「帰りがけにここの電気付いてること多いってさ」
「そんだけであの人に目ぇ付けられる理由が分からん……」
九の遠い親戚だという霧島四郎という男は、一応同じ工学部棟の住人ではあるが、かといって直接仕事で合うこともほとんどない、いわば名簿上で名前を知っている程度の仲のはずなのだが、なにかと八宵のことを気にしてくる変わった男だった。
と、ここまでは表面的な話で、実は八宵の前世での記憶の中に彼の名もあるのだった。しかし、霧島本人にはその記憶はないという。
「なんか、分かんじゃないの。やっぱりさ」
「なにそれ怖い。『覚えてない』んだろ?」
「まあね」
彼らの周りには、なんの因果かかつての知り合いが集まってくる。縁というのはそうそう簡単に切れぬものらしい。記憶がある者もいればない者もいたが、あの頃の知り合いに出会えるのは純粋に嬉しかった。そして、そうやって知った顔を見つけるたびに、「もしかして」とは思っていたのだ。
もしかして、いつかあいつにも逢えるだろうか。再会を誓ったのに、八宵の手の届かぬ場所で勝手に居なくなってしまった、異国の友人にも。
その名をU1224。ドイツ帝国から大日本帝国海軍に譲渡された当時最新鋭の∪ボート。
「――寝てないの?」
九の声に俄に意識を現実に引き戻される。
「寝てる」
「そこで、だろ」
九が視線で壁際のソファを指す。目端が利くのはまさか過去の攻撃機としての性質のせいではなかろうな、と考える。航空機は総じて視野が広い。
「自分ちに帰って寝ることはない、と。……わかりやすいなあ。家にさつきちゃんがいるからなんだろ」
「うっさい。仕事の邪魔するんなら帰れよ」
「学会前、とか適当な嘘でっち上げて泊まり込んでるんだろうけど、そんなのちょっとネット調べればすぐバレるかんね」
「……だからその情報網怖いんですけど」
適当な椅子を引っ張ってきて腰を落ち着けた九を見て、これはそう簡単に帰って貰えそうにないと諦める。
いつの間にかスクリーンセーバーに変わっていたモニターを見るともなしに眺める。四色の旗が翻る黒地のスクリーンには、人生につかれたような冴えない男の顔が反射していた。
「さつきちゃんに、思い出して欲しいんだろ」
あらぬ方向に視線を向けた九が、興味薄そうな声で独り言のように言った。変な気遣いはやめて欲しいと思った。高校生のくせに、こういうところで気が回るやつなのだ。
九の言うとおりなのだった。
はじめは、再び会えただけでいいと思っていた。でも、いざ再会してみると、それだけでは満足できない業深い自分がいた。
なんで俺のことを覚えてないんだと、問い詰めてやりたいと思ったことはこの四ヶ月で数知れない。
「でも、『覚えてる』ってのと『思い出す』のは違うからな……」
別にあの時代が嫌いだったわけではない。兵器として生きて死んだことが悲しいわけでもない。
あの頃の自分たちはあれ以外の時代を知らず、あれ以外の生き方を知らなかった。比較するものがないから、好きも嫌いもなかった。
こうして何の因果か生まれ変わってしまった今でもその考えは根底にあって、大変なことは山ほどあったがそれでも「なかったこと」にしたいとは思わないのだ。
ただの人間にはわからないことだ。あの生き方も、そう悪いものじゃなかった。だから八宵は、記憶を持って生まれてきたことを幸いだと思っている。
でも、今生の途中で前世の記憶を思い出すなんて、それは辛いだけじゃないか。中途半端に思い出すくらいなら、そのまま何も思い出さないで生きていくほうがいいに決まっている。
そう思うと、八宵は前世のことを匂わすような一言ですら、ウーリッヒの前では口にだすのが躊躇われるのだった。
そんなストレスが積み重なれば、ストレスの元凶と同じ部屋に帰ることが苦痛になるのは自然なことだ。
あいつは心配してるだろうな。元はといえば八宵が引き止めたからだとはいえ、やさしい性格の彼のことだ。同居人が帰ってこないとなれば、心を痛めていることだろう。
――もう潮時なのかもしれなかった。未練がましく伸ばしてしまった手を、離すべきなのかもしれない。
もしかして、九はそれを八宵に分からせに来たのだろうか。
「ま、そりゃどうでもいいんだけど」
「……は?」
「夏休みなんだよねー俺たち。海行こうぜ海! 二泊三日で南の島にどーんとさ! つーわけで、伊八っちゃん、保護者役よろしく頼むわ!」
「……あ?」
◆ ◇ ◆
「リア充マジで爆発しろ。高校生とかほんと爆発しろ。俺の有給返せ」
「ヤヨイ、どうしましたか?」
「……あーなんでもない。こっちの話」
日帰りならともかく、泊まりとなると高校生には保護者の付き添いが必要で、しかし生憎彼らの親は仕事だなんだと忙しくて三日も家を空けていられない。それで八宵に白羽の矢が立った、というのがことの流れだそうだ。彼らというのはかつての海軍空戦組+αのことで、まあ小童の数の多い少ないはこの際どうでもいい。
(なんでこいつまで付いてきてんだよ……)
問題は記憶なしの同居人までもが、当然のようにくっついてきていることである。
そりゃあ、子守とはいえ南国のビーチまで出かけるというのに、はるばるドイツからやってきた留学生を誰もいないマンションに取り残すというのはさすがに良心が痛んだ。
霧島兄弟の誰だかが、懇意にしている取引先から特別に借りたプライベートビーチ、とかなんとかいう触れ込みで――その話を聞いたとき、一体誰の仕込みなのか知りたいような知りたくないような微妙な気分になった八宵だ――絶好のリゾート地にもかかわらず人は自分たちだけ。貸切りだ。
ここにいる間くらいは、ただの留学生と親切な研究生の関係ってだけでいいじゃないか。八宵はそう自分に言い聞かせて、ぎこちないながらも会話を成立させていた。
わやわやとはしゃいでいるガキどもを尻目に、八宵とウーリッヒはビーチの少し奥まった場所で、パラソルの作る日陰に並んで座っていた。
「ヤヨイは海、入らないんですか」
無愛想で口下手な八宵に対して、ウーリッヒはあまり気にした様子もなく自然に話を振ってくる。八宵が社交的な性格でないことを知りつつ、部屋に住まわせてくれている相手に対して当たり障りの無い関係を作れる――そういう男なのだろう。誰とでも仲良くなれる、物怖じしない。彼がそういう性格だということを八宵は知っている。もうちょっと親しくなれば、妙な好奇心を発揮して無自覚に他人を振り回してくれることも。
「俺はいいわ。……お前は?」
「わたし、泳げないんですよね」
「……そうなんか」
「ドイチュラントは海が少ないですから、泳げなくても大丈夫なのです」
えっへん、と胸を張って言うことでもないのにそんなことをする。
それにしても、泳げないのか。――昔と違う彼を知って、ショックを受けている自分がいる。この休みの間は、過去のことは気にしないと決めたはずなのに。
「でも、海は好きです。なぜでしょうか、泳げないのに、惹かれるのです」
どきりとした。やめてほしかった。お前は記憶がないのに、なんでそんなことを言う。
「……俺は、海は嫌いだ」
動揺を隠すように、八宵は押し殺した声で遮った。
「泳げるけど、海に入るのは嫌いだ。……塩気でべたべたするし、足がつかないし」
本当は少し違う。
無数の生き物の死骸が溶けているこの水が、八宵は嫌いだった。取り澄ました顔でその底に数多の命を飲み込んでいる水が、嫌いだった。
混沌とした命のスープの中に自ら体を浸そうとするその神経が、八宵には信じられない。
皮肉なものだと思う。前世の記憶を持ち泳ぐこともできるのに海が嫌いな八宵と、記憶もなければ泳ぐこともできず、しかし海に惹かれるウーリッヒ。
何もかもが正反対。前世では同じ兵器だったっていうのに。
思いに耽りそうになる八宵の横で、ウーリッヒは突然立ち上がった。
「ねえヤヨイ、海に入らないのなら、二人だけでデートしましょう!」
◆ ◇ ◆
「っ、おい!」
「え? うわぁっ」
八宵が声を上げたときにはもうその長身は海に向かって傾いていた。間の抜けた叫び声と同時に上がる水音。
デートってなんだ意味わかってんのか。結論から言うと、合っているようなそうでもないような。
海に入れなくても海を見るのは好きなんです、というウーリッヒは、八宵を連れて海岸を歩いた。舗装された道路を歩き、切り立った崖を歩き。護岸用のテトラポットが積み重なっているあたりをぴょんぴょんと跳ねて子どものように楽しそうにしている。
ちゃんと前見て歩けよ。そう声をかけようとした矢先だった。
「なにしてんだこのバカっ!」
彼がいた場所まで慌てて駆け寄る。覗き込んだそこは、深い青。浅くないのは幸いか。……いや、ウーリッヒは泳げないのだ。
どうする。飛び込むのか、助けるために。
この期に及んで八宵は逡巡した。――頭の中では。
冷静な頭脳が何がしかの結論を出す前に、体はまっさきに行動を始めていて。
二度目の水音がすぐ耳元で鳴った。
ゴーグルなしの視界は水泡が目に張り付いているように頼りなかった。
深い海の色に染まるようにして、ウーリッヒのシャツの切れ端が映った気がした。なんで真夏にそんな色なんだ、と思わずツッコミを入れた黒いシャツ。
こんな視界だから気のせいかもしれない。しかし八宵には、まるで見えない手が彼を捕らえて海の深くに引きずり込んでいくように思えて仕方なかった。
海は暗い。そして冷たい。
南の海の中でさえ、八宵は凍りつくような孤独を感じる。何もできないという無力感。動かない体。ただ重力に従って沈んでいくだけ。
――襲い来る既視感を振り払うように、必死で水を掻く。
今の自分は鉄の塊ではない。自由に動く二本の手がある。足がある。沈むのではない、潜るのだ。
視界は利かない。でもそんなのは今更だ。かつては視界なんて存在しなかった。頼れるのは聴覚だけだった。
耳を澄ませる。自分の立てる水音を排除して、彼の姿を耳で追った。スクリュー音ではない、彼の命の音。彼のブロー(呼吸音)。
伸ばした手に、何かが触れた。
◆ ◇ ◆
泳げない自分が、なんの救命道具もなしに身一つで海に放り出されている。
焦って当然の状況で、なぜだか一つの危機感も湧いてこなかった。
よほどの馬鹿か脳天気か、そうでなければ自殺願望者か。自分はそのどちらでもないはずなのに、こんなに脳天気でいいのか、とウーリッヒはそれでもどこか現実感のないままに考えた。
容赦なく下へ下へと沈む体、それと反対に見上げた海面は、きらきらと宝石のように輝いていた。
きれいだ。
初めて見る光景なのに、なぜだか懐かしいと思った。海について、ウーリッヒはいつもそんな感想を持つ。
海の向こうから昇る太陽だとか、吹きつける潮風だとか、波の音一つ、海鳥の声一つとっても、もうずいぶん長い間連絡をとっていなかった友人に再会した時のような切なさを感じる。不思議なものだ。ドイツの内陸部出身でしかもカナヅチの自分には海なんてまるで縁がないものなのに。
そしてそれと同じ感覚を、ウーリッヒは全然別のものにも抱いていた。
伊藤八宵。とっつきにくくて、でも本当は心の優しい、年上の日本人。なぜだろう。たった四ヶ月前に初めて出会ったはずなのに、どうしても他人に思えないのだった。それが気になっているからこそ、ウーリッヒは彼のマンションを出ていくことができないでいたのだ。本来なら異国の地で会った見ず知らずの他人の家に、何ヶ月も居候などできはしない。
水音がはじけて、また水面がきらきらと光った。
ごぽり、と口から空気が漏れる。思い出したように急激に苦しくなって、意識が遠のいた。
(――――)
誰かに名前を呼ばれた。懐かしい名前だ。海のように、懐かしい名前。
「……ぃ、はち?」
激しく噎せた後に、目に入ったのは暴力的な直射日光と、それを遮るように覆い被さる八宵の姿だった。
海の中ではなく、コンクリートの地面に仰向けに寝かされている。
助かったことを実感するより、全身を水浸しにした八宵が呆然とウーリッヒを見下ろしている事のほうが気になった。
衣服でごまかしていた体の線が、太陽に透けている。実は意外と頼りないのだ。それがいやで、薄着は好まなかったっけ。
体を起こしてみると、逆光の中でも彼の表情が困惑に歪んでいるのが見て取れた。
「伊八?」
「なんでその、呼び方……」
髪から次々に滴り落ちる海水に紛れて、それが一筋増えたとしても誰にもわからない。
久しぶり。
そう言うと、彼の顔がくしゃりと歪んだ。
(2011/9/24 深夜隊伊八&U1224アンソロジーに寄稿したものです。)

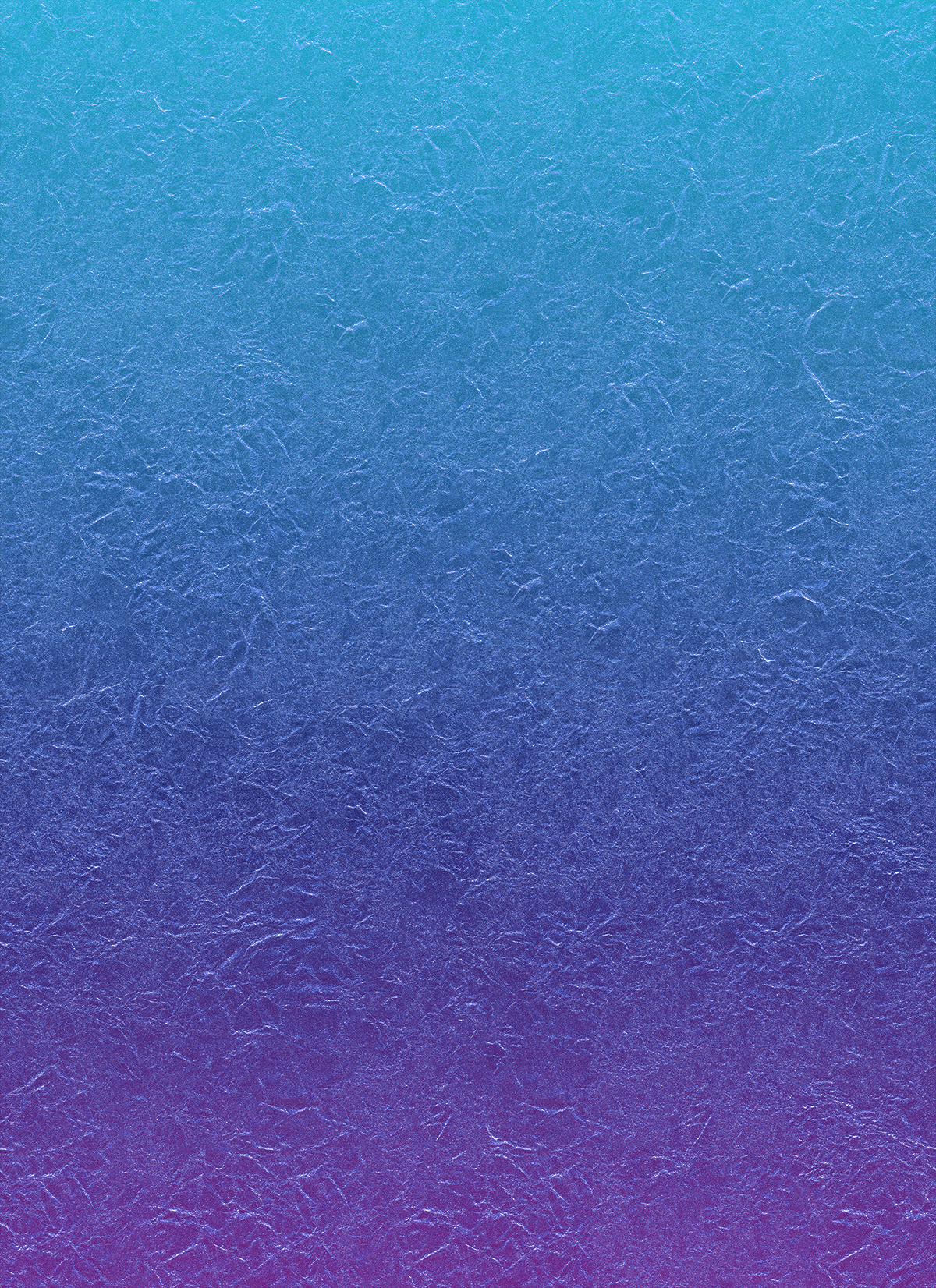
コメントを残す