宇宙には夜も朝もないが、今は当直を除いては皆が眠りについている時間。ふと喉の渇きを覚えて部屋を出たロックオンは、展望室の明かりが煌々と点っていることに気付いて身体を反転させた。
見なれた狭く小さい背中が、無言でロックオンを迎える。
「なんだ、眠れないのか?」
強化ガラスに反射してこちらには気づいているはずなのに、宇宙を透かして見える刹那の視線は微動だにもしなかった。声をかけてもまるっきり無視だ。相変わらず懐かない子どもだが、警戒されることがなくなっただけましというものか。
苦笑しつつ頬を掻こうと腕を上げかけたところで、こちらの姿も見えていることに気付いて途中で止めた。それにしても、己の中途半端な仕草に苦笑だけは漏れたが。
「眠れないのか?」
床を軽く蹴ってゆっくりと刹那の横まで近づいてもう一度声をかけると、一心に宙へと向けられていた視線がようやく揺らいだ。
見下ろした彼の服装は、明らかに寝巻きだとわかるくらいに薄着だったので、やはり寝ようとして寝付けなかったというのが正しいのだろう。空調が整っている船内でも些か寒そうに見えて、しかしロックオンも水を飲みに起きただけだから羽織るもの一つ持っていない。
薄い背に手を伸ばし、二三回軽く擦ってみる。触れる直前で肩がわずかに震えるのがわかったが、あからさまな拒絶はなかったのでそのままにした。
今度は明らかにいぶかしげな眼がこちらを向く。
「いや、寒そうだなーって思って」
「……寒くはない」
ようやく聞けた声は掠れていた。背中を覆う布の感触も、伝わる体温を考慮しなければ乾いて冷たかった。長いことここにいたんじゃないかという疑念に、ロックオンは肩をすくめる。
「寝ろよ」
「眠くない」
ばっさりと切って返されて、ロックオンは今度こそ隠さずに苦笑した。
「眠くなくても横になれ。明日も訓練、あるだろ」
次のミッションはまだ先だが、それでなくても体力を消耗そうなトレーニングメニューがびっしりと組まれている。まだまだ成長途中の身体は頼りない細さで、本人よりも周りのほうが心配してしまう——といっても、それは専らロックオンの役目だったが。
「寝ないと背が伸びないぞ」
ちくりと彼の気にしていることを指摘すると、先ほどよりも間をおいて返事が返った。
「……眠れない」
「うーん、そうか……」
困ったなあ、と他人事に呟くと、じとっとした視線が口よりも雄弁に語りかける。まあ、彼の物静かというのも生易しいほどの口と比べての話なので、実際は常人には汲み取れないほど僅かな視線ではあったのだが。
「体調管理も仕事のうちだ、努力しろよ。……俺が子守唄でも歌ってやろうか?」
こうして二人悩んだところで仕方がない。言い置いて背を向けようとしたのに、それを刹那が止めた。
「子守、唄?」
「あ?」
からかうつもりで付け加えたのに、思わぬ反応を示されてロックオンは戸惑った。
「子守唄とは何だ」
「あー……そうだな。聞くと眠くなるような歌、だ」
知らないのか。そう問いたいのを飲み込んで、ごく簡潔に説明する。本当は「母親が子どもを寝かしつけるときに歌う歌だ」と教えてやりたかったが、そのまま言えば彼の機嫌を損ねるのはわかりきったことなので、なんとか遠まわしに説明した。したつもりだが、かえって本質から離れた回答になってしまったかもしれない。
そのせいかどうなのか、刹那にとって耳慣れぬ単語は、彼の気を随分引いてしまったようだ。
「周りでうるさくされて眠れるものなのか」
「うるさいって……」
「歌え」
「へ?」
「子守唄」
「ええー!」
まいった、まさかこんな展開になるとは思わなかった。ロックオンは頭を掻いて反論を試みる。
「こういうのはベッドの中でブランケットかぶって聞かないと意味ないの! いいからもう寝ろよ!」
「眠くなるかどうか試しに聞くくらいいいだろう」
「だから! ……あー、くそっ」
そんな急に人前で歌えと言われても——それも子守唄だなんて甘ったるいものをだ——、まず歌を歌うこと自体が久しぶりすぎて、曲や歌詞以前にそのための喉の使い方を思い出せるかどうかのほうが問題だ。
断ろうとしても、しかし大きな目が好奇心とそれ以上の期待をはらんでこちらを向いているのを見ると声が出なくなる。
「しかたねえな」
ロックオンは溜息を吐きだした。自分が言い出したことだから、腹をくくろう。そう考えることができるくらいロックオンは大人で、そして刹那に甘かった。
それにしても向き合って子守唄を歌うなんてバカげた真似は御免だったから、ロックオンは刹那の横から頭を抱えて、彼の耳のあたりを自分の肩に押しつけた。珍しくなんの抵抗もなく肩口に収まる刹那が、このときばかりは恨めしい。
ふと視界に入った、ガラスに映った二人の姿が全く最低最悪の絵面だったので、ロックオンは何も見えないようにと瞳を閉じた。
こほんと軽く咳払いをして、すっと息を吸う。
囁くようなか細い低音が漏れ出す。それはほとんど吐息のようなささやかさで、旋律も途切れ途切れ、音程は確かなつもりだったが、歌ったのはずいぶん久しぶりの曲だったから本当に正しいのかどうかすらあやふやだ。
人の罪と神の愛を歌った、どうということのない古い讃美歌だった。キリスト教と縁遠いところで育った刹那には馴染み薄いかもしれないが、ロックオンには懐かしい旋律だ。
賛美歌なんてほとんど覚えていやしない。幼い頃の記憶の中でもとみにかすれている部分だったけれど、神に歌うというよりも恋人に語りかけているような甘い旋律のせいか、この歌はなぜだか心に残っていた。
歌詞の中身になんて意味はない。神の存在がどうであるかについてと同じくらい。
だからロックオンは、その穏やかな旋律だけを噛み締めるように歌った。今は神でも恋人でもなく、愛を知らない小さな子どもに向かって。
歌い終えて、さてどんな文句をぶつけられるのやらと首をすくめたロックオンに届いたのは、小さな寝息だった。
「……効くもんだな」
思わずぽかんと呟いてしまってから、くっと笑いをかみ殺す。ほんと数分の歌でまさかこんなに簡単に眠ってしまうとは、可愛いものだ。
笑った衝撃で起こしてしまうのも勿体ないので、なるべく肩を動かさないように様子をみたが、刹那は幼い子どもさながらにすやすやと寝息を立てている。
「まるで——いや、」
小さな頭を軽く撫でて、ロックオンは微笑んだ。
「まるでもなにも、……子どもだったな」

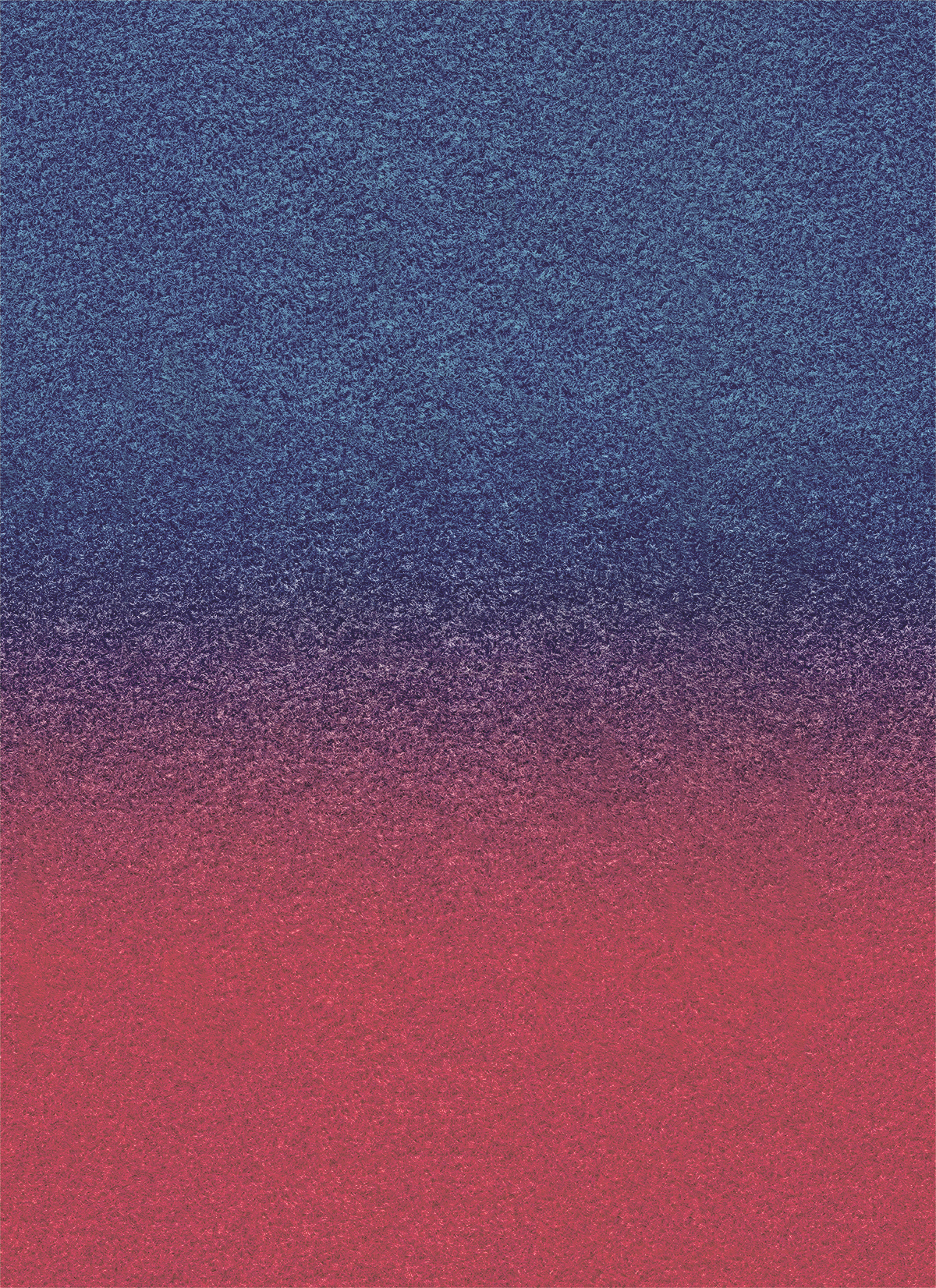
コメントを残す