(1期23話後)
明けない夜はなく、止まない雨はないと古の詩人は歌った。それは真理でありながら、どうしようもなく残酷な事実でもある。何が起ころうとも世界は回る。どんな悲しみがあろうと、どんな憎しみがあろうと、世界は回る。
そう、彼がいなくなっても、世界は全く正常なまま滞りなく回っていく。
日々は過ぎゆく。戦闘員を一人失ったところでいつまでも泣き暮らすわけにはいかないのだ。クルーたちがぎこちないながらも笑顔で会話ができるようになった頃、ガンダムマイスターたちは既に日常を取り戻していた。——それが表面上のことだけであったとしても。
淡々と食事をとるティエリアを見て、スメラギは周りに悟られないくらい小さく嘆息する。
彼がいなくなってから、ティエリアはまた一つ人間らしくなった。悲しみと憎しみを理解し、残された者のやるせなさを知ったようだった。機械のようには割り切ることができない、面倒でそれでいて優しい感情を、彼はあれから手に入れた。
よく眠れていないのか、食事をすすめる手が遅いように見える。作り物のようにきれいな顔に隈が浮かんでいるのがなによりの証拠だ。本当は辛くて仕方がないはずなのに、それでも表面上はいつも通り振舞おうとするのが、見ていて痛々しかった。少しでも彼の気をやわらげてあげたいと思う。しかし、ティエリアに声をかけられるほど近しい存在など片手の指の数にも満たず、そしてその誰の声も彼には届かない。
そんなとき、彼ならどうするだろうか。誰の言うことも聞こうとせず我を貫く彼に、疲れても飛び続けることしかできない不器用な鳥のような彼に、さり気無く宿木を指し示すことができた彼ならば。
(なんでこう、うまくいかないのかしらね、ロックオン——)
あなたがいなくなったことで彼が手に入れた心は、あなたの腕なくしては触れることもままならないなんて。
*
あれから単独、もしくはペアを組んでのミッションは何度か行われていたが、今回は特に入念なミーティングを必要とする、三人揃ってのミッションだ。
カフェテリアにはティエリアの他に何人かのクルーと、アレルヤ・ハプティズムの姿があった。味気ない朝食をとるティエリアを、周囲は若干の怯えを含んだ眼で遠巻きに見守っている。アレルヤはいくらか苦笑してその風景を見つめた。
いつにもまして彼の機嫌は悪そうだ。それが、いまここにいないもうひとりのガンダムマイスターのせいだということはアレルヤにもわかった。確かに、この時間にここにいないとなると、これから行われるミーティングの時間には食事が終わらないかもしれない。
どん、と乱暴な音を立ててドリンクが机に置かれた。クルーたちの肩がびくりと震える。まさにそのタイミングで、カフェテリアのドアがスライドした。
(絶妙だね)
入ってきたのは刹那・F・セイエイ、もちろん真っ先に注目したのはティエリアだった。
射抜くようなまっすぐな視線に気づかないはずもないだろうに、刹那は至って自然体のままカンターに向かう。まったく大した神経の持ち主だ。
ティエリアの脇を通り抜けようとした刹那は、擦れ違いざまに手首を掴まれて立ち止まった。二つの視線が交錯する。
これはあまりよくないな。アレルヤは場の空気を動かさないようにできるだけそっと席を立ち、彼らのほうへと向かった。
「刹那・F・セイエイ、食事の時間くらい守れないのか」
「……」
「そんなにカリカリしなくても……」
アレルヤがやんわりと口をはさむと、予想に違わず矛先がこちらにまで向けられる。
「何を甘いことを言っている。ミーティングの時刻が迫っている、それがずれこめば今後の予定にも差し障りかねない」
「……ミーティングの時間は守る」
平坦な声音にはなんの感情も浮かんでいないようで、ああ、少しでも申し訳なさそうな声を出したらいいのにとアレルヤは内心で嘆いた。
『あー、後で俺がちゃんと注意しとくから、とりあえず刹那は早く食え。ティエリア、そんな言い合いしてたら余計遅れるだろ』
こんなとき、彼の言葉が必要だ。
*
「…………」
いつもいつもうるさくて仕方がなかったオレンジ色の球体は、以来すっかり物静かになってしまった。
スピーカの故障か、最悪演算装置に問題が発生している可能性もある。しかし、どういうわけだかどのメカニックもそれに手を出そうとはしなかった。彼の死とともに訪れた変化を、無理やり修正するのを拒んでいるのだ。
全ては、人間の愚かな感傷に過ぎない。しかし、敢えてそれを口に出す必要がないことがわかる程度に、ティエリアは人間であった。
ミーティングルームから自室に戻る途中に出会ったそれは、先ほどから無言のままティエリアの後を付いてくる。ふよりふよりと漂いながらも、どうやら明確な意志を持ってついてきているようだとわかったので、ティエリアは仕方なくそれに向き合った。
「何の用だ」
「…………」
「仕事は——」
言いかけて口をつぐむ。それがおもに整備を担当していた機体はミッションに出撃しなくなって久しいのだということを思い出した。定期的な整備は今も続行されているのだろうが、エクシアやキュリオス、ヴァーチェに比べればその頻度はごく低い。
小さく舌打ちして顔をゆがめる。眉間に皺が寄るのを人ごとのように感じた。
こんなところでも彼の不在を実感してしまう。それが無性に、無性に、なんだろうか。正体のわからない感情をもてあまし、ティエリアは無言で踵を返した。これ以上AIと会話を試みるのは不利益極まりない。
「ティエリア」
背を向けた途端、久し振りに聞く合成音声に呼び止められる。壁に手をついて振り返ると、目を模して据え付けられた二つのダイオードがチカチカと明滅した。
「……なんだ」
「ロックオン、モドッテクルッテ」
「何を……」
「モドッテクルッテイッテタ。ダカラモドッテクル」
「……」
「モドッテクル、モドッテクル」
「……ッ、黙れ!」
これほどまでに合成音声を耳障りだと思ったことはない。それが一言発するたびに、心臓を素手で撫上げられるような不快感を感じる。
AIに慰められるなんて。いや、そう考えること自体が愚かしい。AIは知識に忠実であるだけで、決してそこに感情なんて宿らない。それは入力と内部状態の変化から導き出される推論の結果に過ぎない。
「ティエリア、ゲンキダシテ」
「うるさいッ!」
なおも耳障りな言葉を放つそれを鷲掴もうとして触れた指先で金属の表面がつるりと滑った。手の平を見返す。指の腹が黒く汚れていた。掴み損ねたそれをよく見ると、指の跡が五つ、筋として残っている。
「……」
なんだかんだ、誰かしらがかまっているはずのそのロボットは、おそらくそれでも足りないくらいに彼にかまわれていたのだ。油や埃で汚れていたことなど見たことがなかった。
二つ並んだダイオードの右の一つの下、すっと引かれた指の一筋がまるで涙のようで、咄嗟にそれをぬぐい取ろうと手を伸ばしてしまった自分を嫌悪した。
途中で止まった手をすり抜けるようにして、球体は先ほどまでの合成音が嘘だったように黙りこくったまま、ふわりとどこかへ行ってしまった。
ああ、彼はもういないのだな。
理解していたはずの事実を再認識するという不思議を味わい、ティエリアはぼうっと天井を見上げた。白々しい明りが目に痛い。
それでも、涙は出なかった。

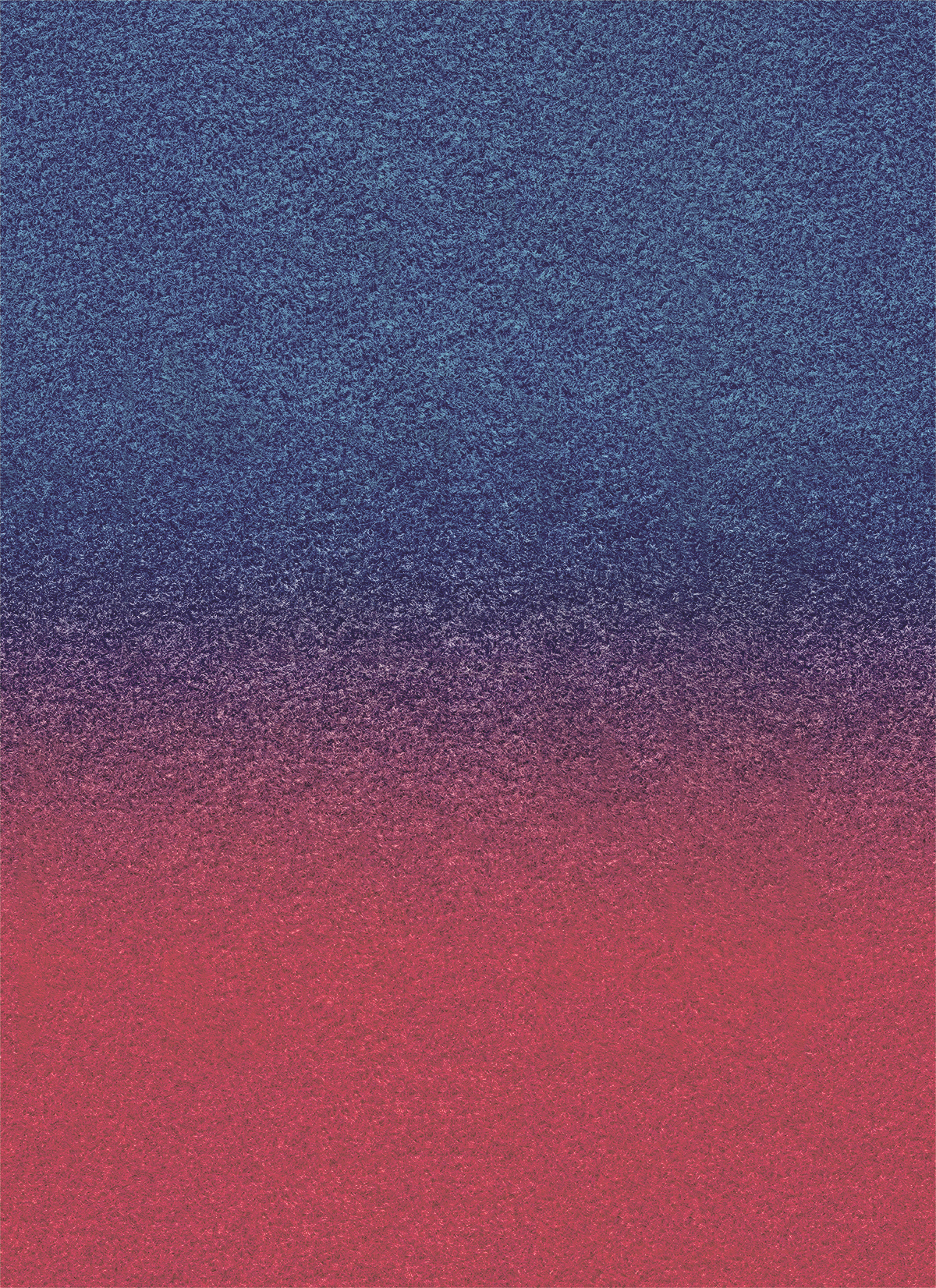
コメントを残す