街中のコンドミニアムというのは、交通の便はいいかもしれないが夜中でも騒音が絶えず、しかもその騒音というのが罵声や怒声、時には銃声なんて穏やかでないものばかりだったのでは気も休まらない。そういうわけで、ロックオンはどうも居心地の悪い余暇を過ごしていた。
余暇という言い方は語弊があり、次の任務に備えての待機中というのが実のところは正しい。また、そうでなければ、誰が好き好んでこんな過ごしづらい場所に滞在するだろうか。
ふと身じろいだ隙に安物のソファがぎしりと鳴って、ロックオンは顔を上げた。机上の携帯が示す時刻は午後10時。
「遅いな……」
無人の室内で誰にともなくつぶやいた言葉は、現在ペアを組んで任務を遂行している刹那を案じてのものだ。彼は夕方にふらりと出掛けたまま、未だに帰ってきていない。
任務中であることも考えればそんなに遠くに行くはずもないし、まさか厄介事に巻き込まれているわけでもないとは思うが。
読みかけのペーパーバックを閉じて、ロックオンは携帯に手を伸ばす。一応念のため、連絡をとっておくべきだと思ったのだ。
ナンバーを押そうとしたところでキッチンの奥から物音がした。入口の鍵を開ける音だ。丁度いいタイミングで、どうやら刹那が帰ってきたらしい。
ほっと一安心して携帯を机に戻し、再びペーパーバックを開きかける。先ほどまで読んでいた場所を見つけるためにぱらぱらとページをめくってみるが、玄関の気配がなかなか中に入ろうとしないのが気になった。
よく耳を澄ませば、さあさあと雨音がしていた。昼間も天気がいいとは言えなかったが、いつの間にか降りだしていたらしい。
となると、あいつは玄関で雨に降られながらもまだ入ってこようとしないのか。
「馬鹿……」
軽く舌打ちしてロックオンは立ち上がり、入口へと向かった。
扉を開ければ、予想に違わず濡れ鼠になった刹那の姿がある。大げさにため息をついてロックオンは彼を見下ろした。
「何してんだ……って、……なんだ?」
そうして、彼の両腕が不自然な位置に静止していることに気付く。まるで何かを大事に抱えているような。
「猫、か」
刹那の腕の中にあるのは、両手にすっぽりと収まってしまうような大きさの猫だった。夜闇と汚れのせいで本来の色はわからないが、見た目では灰色の短い毛をした、小さな猫だ。
「とりあえず中入れ。今タオル——」
無言のまま立ち尽くす刹那を促して一度部屋の中へ引っ込もうとしたのだが、ロックオンはふと動きを止めた。
室内から漏れた照明にきらめいて、金色の目が虚ろにロックオンを貫いた。
生きているはずである。生きていなければ動かないから生きているのだろう視線は、しかし死者と変わらぬほど虚無だった。
殺してくれ。まるでそう訴えかけるように見えたのは、果たして気のせいだろうか。
「……俺はいいから、これ」
「あ、……ああ」
先ほどとは反対に刹那に促される形で、ロックオンは室内に戻った。
タンスからタオルを何枚か取り出し、一枚を刹那の頭に放ると、残りは重ねてテーブルの陰に敷いた。蛍光灯の強い光はあまりよくなさそうだからだ。
それからキッチンで湯を沸かし、水で温度を調節しながらガーゼを浸し、絞る。
猫の看病なんてしたことがないから勝手がわからない。とりあえず、湯気を立てるガーゼを持って部屋に戻ると、刹那がテーブルの下にしゃがんでいた。自分は上着を脱いで、タオルを肩に掛けただけの姿だ。
テーブルで遮られていくらか柔らかくなった光の下。タオルに横たわる猫は酷く痩せていて、震える気力もないようにぐったりとしている。微かに上下する体だけが生を示しているようで、あの虚ろに輝いた瞳は今は閉じられていた。
ガーゼで身体をぬぐってやろうとすると、刹那が横からそれを奪う。
「……優しく、な」
手がぎこちなく猫に触れるのを微笑ましく思う。普段無愛想な少年も、動物には心を開くらしいから。
ひとこと添えてからキッチンに戻り、湯を盥に移し今度はミルクを温める。鍋に注がれたミルクの表面をじっと見つめながら、ロックオンはあの猫について考えた。
(老衰だな……)
子猫というには成熟した体をしていて、しかし髭はくたびれ、拭った毛並みも色艶が悪かった。ただ栄養状態が悪いだけという可能性もあるが、おそらくは。
もう死期が迫っているのならば看取ってやるのがいいとは思う。打てる手があるのならばしてやりたいとも。
なにより、あの刹那が猫を拾って来たということが、正直意外だったのだ。あの子はきっと、道端に転げているのが猫であれ人であれ、手をさしのばしたりはしないと思っていた。
エアコン以上の暖房器具が見当たらない部屋で、湯に浸した布で毛並みをぬぐい、冷めたらまた温め直しという作業を一時間続けた。それでも回復が見込めないならば、刹那には辛いかもしれないが作業をやめさせるつもりだった。
自分たちは猫の看病をしにここにいるわけではない。実行開始時間が不確定な任務に向けて、身体も心も十分に休めなければならないのだ。
あと五分だけだな、とロックオンは時計の長針が真上を指したのを見て思う。あと五分の甘さを捨てきれない自分には思わず苦笑がこぼれてしまうが。
「……あ」
刹那が小さく声を上げたので視線を戻すと、先ほどまで身じろぎもしなかった猫がうっすらと目を開けていた。それから二人が見ている中でゆっくりと体制を変え、箱のような形の、あの独特な座り方をした。
「ミルク、飲むかな……」
すっかり冷めてしまったが、それを人差指で掬って猫の鼻先につきだしてみると、細く目を開けてぺろりと舐める。
「お、飲むな。じゃあ温め直してきてやろう」
結局その猫は小皿に移したミルクを時間をかけてではあるがすべて平らげ、最後には満足そうな吐息すら零して丸くなった。
その鼻筋を撫でる刹那の指先を、猫はわざわざ顔を上げてぺろりと舐めた。お礼でも言っているつもりなのだろうか。
その様子をみてロックオンはあからさまに息をついてしまったが、ほっとしたのはきっと彼だけではなかっただろう。
明りを消すととたんに聴覚が冴える気がするのは、たぶん気のせいではない。外の雨音が一層激しくなったように思えるのは、どうだかわからないけれど。
刹那はベッドに、ロックオンはソファに横になる。
目を閉じる前に、ロックオンは訊ねた。
「なんで拾って来たんだ?」
「……死にたそうな眼をしていた。殺してくれと言っている気がした。殺してやろうと思って近づいたら、もう目を開けていなかったから」
「だから連れてきたのか?」
「……わからない」
十分な空白の後にぽつりと零して、刹那はそれ以上口を開く気配を見せなかった。
「そうかね」
わからない、ものかね。
テーブルの下から、微かににゃあと声が聞こえた、気がした。
任務の開始命令が来たら、この猫をどうするべきか。あと一日程度は時間的に余裕があるはずだが、まだ外に放すことができる状態じゃないし。
そんな心配は杞憂に終わった。
次の日の朝、ロックオンと刹那が見守る中で、猫はひっそりと最後の息を零し、そしてそれきり動かなくなった。
待機中の状況で遠出はできなかったが、幸い潜伏先のごく近くに小さな公園があった。薄汚れた街の中でも逞しく根を張る木と、枯れかけた芝生が対照的な、しかしそのみすぼらしい芝のせいか、人の少ない静かな場所だった。
一際枝ぶりの良い木の根元に穴を掘り、猫の死体を埋めた。土を盛って、最後に手近なところにあった石を置く。
その間、ロックオンと刹那は終始無言であった。
そこだけ色の違う土とその上にぽつんと乗った石を眺めながら、手についた土を払う。同じようにそれを眺める刹那の横顔を盗み見たが、何を考えているのかはわからなかった。
「お祈りは済んだか」
「祈る神を持たない」
ロックオンは苦笑する。
「そっか、そうだな。でもいいんだよ。天国……ってのもないのか? じゃあ、静かに眠れますように、安らかでありますように、そう願え。誰に向かってでもなくていいから」
「…………」
「……それならこれでもいい。『さようなら』って、心の中でそう言ってやれ」
「…………」
「言えたか? ……よし。じゃあ、帰るか」
先に背を向けたロックオンの後を、少し遅れてついてくる気配がした。
祈りなんて、死者のためにあるはずもない。
ロックオンはキリスト教徒ではあったが、神の存在を常に身近に感じていられるほど熱心ではないし、魂の存在も信じてはいない。
それでも祈る。一体、誰のために?
(自分のために、さ)
いなくなったものに別れを告げ、その空白に負けぬよう明日を生きるために、人は死者を悼むふりをして自分のために祈り続ける。
強がりでなく本当にそれを知らない様子の彼は、きっとロックオンなど及びもつかぬほどに強い意志を持った人間だ。
それを羨ましいと思うことはない。だって、それはたぶんとても……悲しいことだ。
「晩飯の材料でも買ってくか」
「肉が食べたい」
「大雑把な注文だなあ……」
振り向かずに投げた言葉に答える声は、濡れることも震えることもせず、いつもと同じ色をしていた。

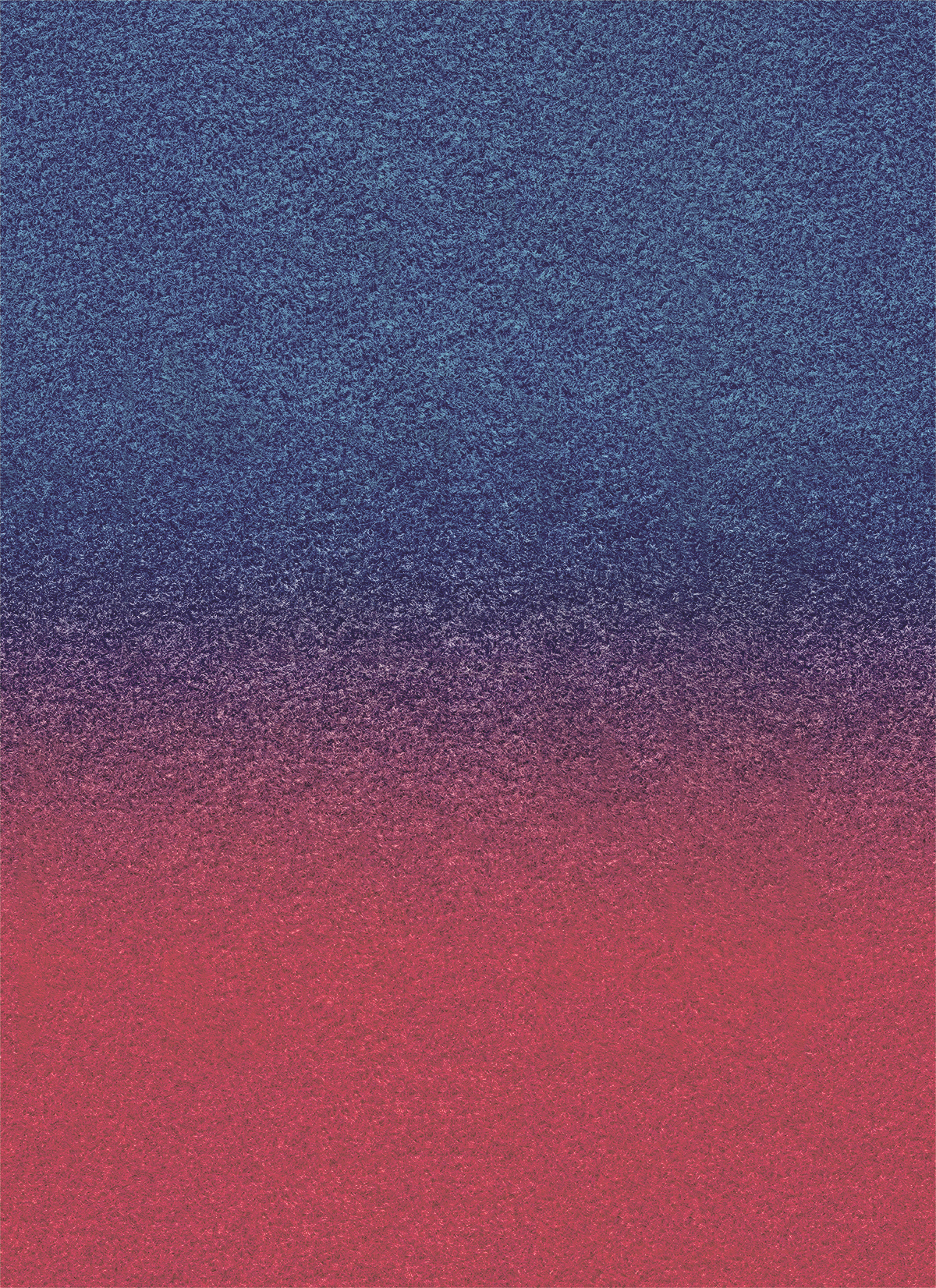
コメントを残す