ロックオン・ストラトス。
初めてその名を聞いた時は、なんてふざけた名前なんだと思った。
いくら偽名といえども、味方同士で呼び合うときに使い、背中を預ける者たちに託す名前なのだから、少しは親しみやすい名を使えばいいのに。
少なくとも自分たちに対しては、そんな作り物めいた名前ではなくて、人間らしい名前を使わせてくれたっていいじゃないか。
ふざけた名前に見合わず、ロックオン・ストラトスという男はガンダムマイスターたちの中でも常識人で、一番とっつきやすい性格をしていた。彼らの中では最年長だったので、ある程度は常識を持っていないとチームのバランスが保てないという抑制もあったのかもしれないが。
なにかと年下の面倒を焼き、時には貧乏籤としか思えないような役割を引き受けながらも、チームのムードメイカーであり続ける。
買い物袋片手に鼻歌を歌いながら街で擦れ違ったとしても違和感がないだろうな。というか、他のマイスターたちではそんな光景は想像できない。
そんな認識が崩れたのはどれくらいした頃だったろうか。
何が切っ掛けだったというわけでもない。ただ、ミッションを終えて帰還したばかりの、まるで硝煙と血の匂いに酔っているかのような近寄りがたい背中を見たとき、また、滅多に使うことはないだろうスナイパーライフルの整備を真剣な顔をして行っている横顔を見たとき、知っていたはずの事実がまるで初めて知ったことのように重くのしかかる。
彼が普段はそんな様子を欠片も見せないような性格をしているからこそ、その落差に打ちのめされたのかもしれない。
その名は、すべてに対して偽りであり、しかし何よりも彼の本質を表しているのかもしれなかった。人というものを覆っている余計な皮を全て剥いで、必要かもしれなかった肉すらも殺ぎ落とし、最後に残ったものがそれだ。
彼も「向こう側」の人間なのだ。もちろんこの組織に所属している以上、誰もがその宿命を負い、そして自分もその「向こう側」に足を踏み入れてかけている。しかし、彼は完全にその身を浸し、そして何があろうともこちらへ帰ってこようとは思っていない、きっと。
ロックオン、その名を呼ばれるたびに彼は何を思うのだろうか。
仮の名を自嘲するのか、戒めの名を噛み締めるのか、未だふさがり切らない傷口を自覚するのか。
出撃準備の放送がかかり、緑のパイロットスーツがドッグに駆け込んでくる。オレンジ色の相棒も一緒だ。
彼が横を通り過ぎようとした瞬間、思わず彼の名を呼んでしまったのは直前までそんな愚にもつかないことを考えていたから、だろうか。
「ロックオン」
「……あ? なんだよおやっさん」
「ああ、いや。——無事に戻ってこいよ」
突然妙なことを口走ってしまったチーフメカニックをどう思ったのか、彼は一瞬目を丸くしてからにやりと笑って背を向ける。去り際にヘルメットを軽く掲げて見せて。
「……気障なやつだなあ」
もう戻る気はないのだということを、その名が教えてくれる。
例え全てが終わりを迎えても、彼はきっと戻る気も、振り返る気すらないのだ。
彼はそんな道を、歩いている。

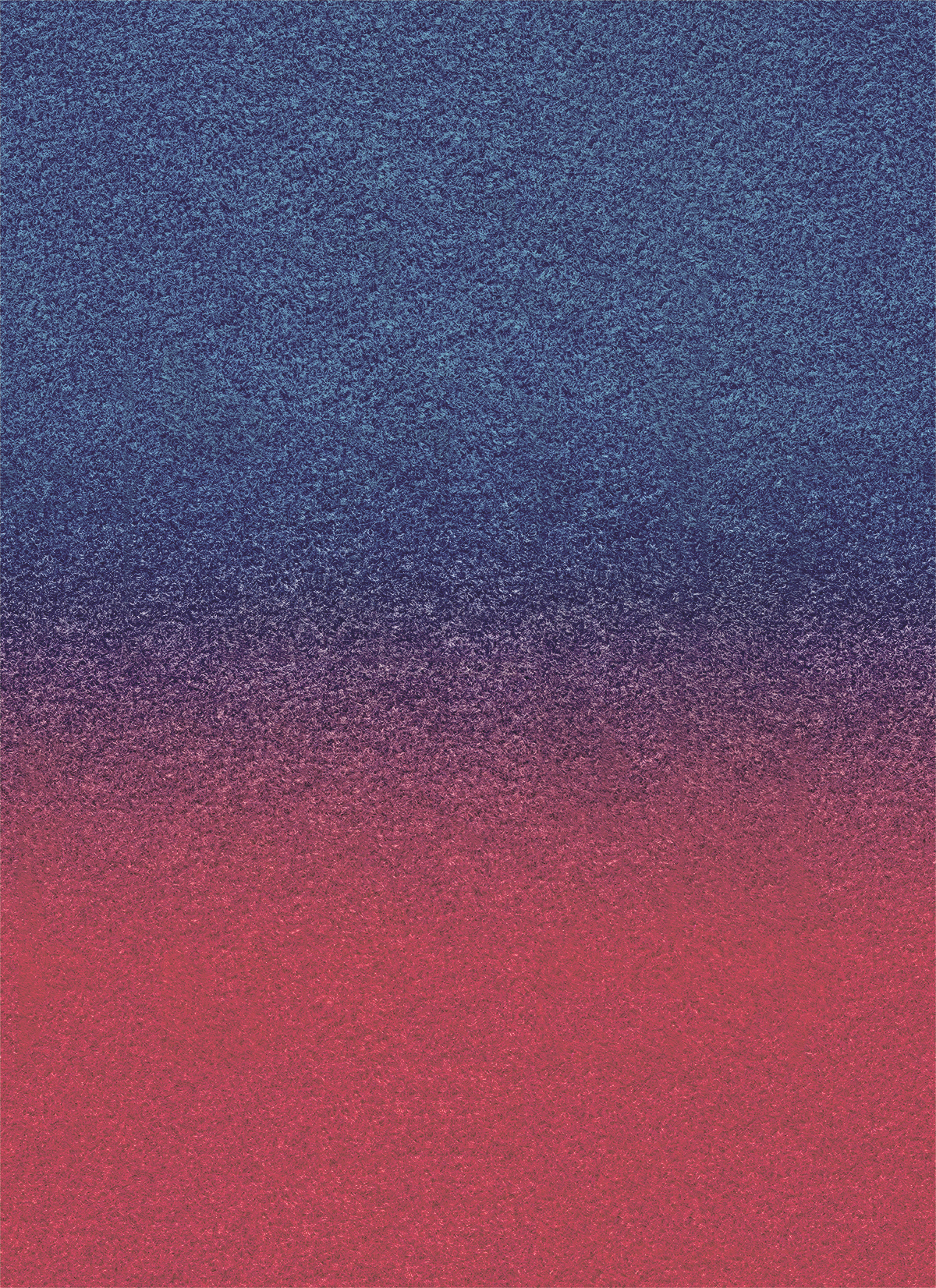
コメントを残す