「俺たちは、ソレスタル・ビーイングなんて気違いな集団が出てきちまうような世界に生まれなきゃ出会わなかったわけで」
あくびでも出しそうな声で、隣に座る男が言った。
地球に降りると、なんだかんだいつも一緒に行動しているような気がするのは、気のせいか。
砂漠の真ん中で、岩陰に機体を隠して自分たちも身を潜め、本来なら人に見つからないように行動すべきなのに、二人してこうして暢気に夜空を見上げているのはなぜだろう。
刹那の手にはミルクティが入ったカップがある。レーション付属のインスタントティにミルクポーションを落としただけの簡素なものだったが、砂漠の夜の冷え込みには沁みるような温かさだった。
「でまた、それぞれがそんな糞ったれな世界に殺されなきゃここに集まったりしなかったわけで」
男の手にも同じものがある。彼はそれを一口含んで、はっと息をついた。月灯りに息が白く曇る。
レザーの手袋に包まれた手にも、今自分が感じているのと同様の温度が伝わっているのだろうか。材質のせいか色のせいか、手袋をしていても冷たそうに見える指先に触れてみたいと思った。
刹那が終始無言であっても、彼はかまわず一人で喋る。本来が喧しい性格だったというわけではなく、刹那や他のマイスターたちの寡黙すぎる性質が彼をこうやって振舞わせるようにしただけ、かもしれない。出会った当初、彼はもっと静かだったし、そしてもう少し自己中心的だった。
「俺とお前がこうやって隣同士仲良くやってんのも、戦争がなきゃありえなかったんだよなあ」
よく喋る男はそこで一度口を閉じた。仲良く、のくだりには口を挟もうかとも思ったが、どう言葉を繕ったところで子供が大人に反抗しているみたいでしかないと想像してやめた。
その代わり、彼の大きな独り言を反芻する。聞き流していた言葉を記憶から拾っても彼の言わんとしていることがわからず、しかしわからないなりに模索した結果を乗せて、刹那は尋ねる。
「それで、戦争があってよかったと思うのか?」
「いいや。全く」
ロックオンはいとも簡単に否定する。
もちろんその通りだった。自分たちは慣れ合うために、傷口をなめ合うために集まったわけではない。
それでも、なんだか自分の存在を否定されたような気分になって、とたんに心臓がぎゅっと縮こまるような思いがした。一人っきりで塹壕に身を隠しているときの気分に似ている。
それが置いて行かれた子供の気持ちと同じものだとは、知るよしもないけれど。
刹那は冷めかけた紅茶を最後まで飲み干すふりをして、ロックオンを盗み見た。緑の虹彩がこちらを向いている。視線が正面からぶつかってしまったのに慌ててカップの中身を睨みつけるけれど、なんのごまかしにもなっていなかった。
ロックオンは軽く笑ったがそれには触れず、自分もカップに口をつける。そうして、たっぷり間を置いてからもう一度口を開いた。
「だが、縁とか運命って言葉を信じようってくらいには、俺はお前たちのことが好きだよ」
鈍く笑って、彼はまた星の数を数えるように宙を見上げた。
もう寝よう。そう言って立ち上がろうとしたロックオンに一言だけ問う。
「結局何が言いたかったんだ?」
「いや、星の廻り合わせ、って言葉を思い出しただけさ」
見上げた彼の全く普段通りの横顔からは、その言葉以上の意味を見出すことはできなかった。
不可解を抱えたまま彼の視線の先を辿れば、そこには満天に広がる星々が広がり、大気を通してきらきらと瞬いている。
宇宙とは違う星空に、こういう夜も悪くはないと感じた。
漠然と感じた不安は、もう見当たらない。

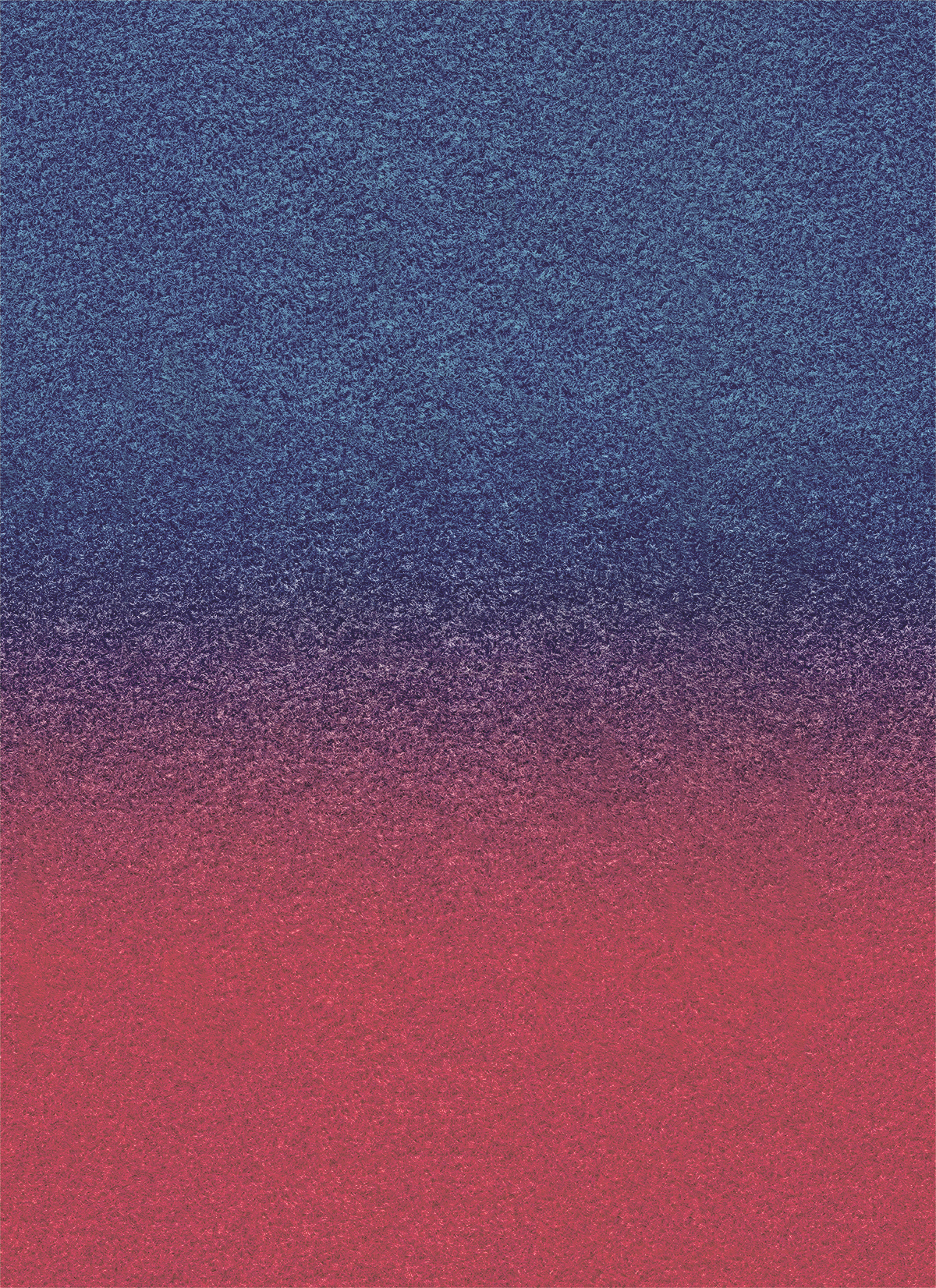
コメントを残す