柱に縛り付けられた伊八は自由の利かない四肢を捩りながら、うう、と喉の奥のほうで低く唸った。
そんなことをして解けるわけがないのに、その些細な抵抗がまるで状況の飲み込めていない猫の仕草のようで、ウーリッヒは思わず笑ってしまう。
緋色の着流しに食い込む荒い縄目の締付け増しただけで、なんの抵抗にもなっていない。乱れた着物のあわせから、白い首筋とそこに巻きつく黒革の首輪が覗いた。
自分で自分の首を絞めているのに全く気付いていない。ウーリッヒの笑みが深くなる。
それに気付いた伊八は唸るのをやめ、苦虫を噛み潰したような顔になってウーリッヒを睨む。
「解け」
「いやです」
「……あー、解いてクダサイ」
「ナイン、ナイン」
ウーリッヒは歌うように口ずさんだ。
「お前……」
はあ、と大げさなため息が伊八の口から漏れる。
そんな態度をとっても無駄ですよ、とウーリッヒは心の中で思う。それがあなたの「余裕」のポーズであることぐらい、私にはお見通しなのです。
「あのなあ」
さも呆れたといわんばかりに、伊八はウーリッヒを見上げた。
身長差があろうと、伊八は上目など使わない。顎を上げて、見上げているはずなのに見下ろしているかのような、独特の視線をウーリッヒにくれる。
それがどれほどウーリッヒを歓喜させるか、彼はきっと露ほども知らない。
簡単に屈服する者に興味はない。毅然としていて、何者にも屈服することを知らず、たとえ泥に塗れようとも精神までは地に落ちない。そういった者を従えることこそが至上の歓喜である。
その点彼は最高だ。
プライドなどないと装っているその一枚皮の下、彼が何を隠し持っているのか、まだ図りきれないそれを暴いてみたい――。
ぞくりと背筋が震えた。
もちろん、精神の恍惚と陶酔によって。
「U房サン? 聞いてマスカ?」
「なんでしょう?」
ニコリと顔の表面だけで笑うのはお手の物だ。伊八は日本人独特の理由のない笑みでそれに応えた。
「あのな、こんなことしても誰得だし、いい加減見苦しいだろ俺の緊縛とか常識的に考えて」
「そんなことありませんよ」
「空気嫁よホント」
「そんなことありませんって」
ウーリッヒは一歩伊八に近づいた。
ここへ来て、彼は初めてウーリッヒという存在に脅威を抱いたようだった。気付いていないわけでもあるまい、自分が何一つ反撃できない状態で、無防備に他人の瞳の前に差し出されている状況を。
それは、私はあなたの敵ではないですけれど、と内心でつぶやく。警戒されないのはうれしいが、あまりにも警戒がなさすぎるのは逆に眼中にないといわれているようで、面白くはない。
眼前に手を差し出すと、伊八の体がびくりと緊張したのがわかった。
顎に手を掛け、象牙の肌をするりと撫でやる。
「ちょ、おま、気色悪ィよ」
はハ、と笑いになり損ねた空笑いがいっそおかしい。
ゆっくりと首筋をたどり、ぴったりと肌に張り付いた首輪をなぞって、ウーリッヒはうっそりと呟いた。
「とてもよくお似合いです、伊八。なるほど、縄というのもいいものですね」
あれだけ主張していたことを認めてあげたというのに、伊八は口元をひくりとひきつらせたきりだった。
***
衣服の上から身体の線をたどる。
意外と細い、とウーリッヒは思った。何ヶ月も海底を漂う任務を帯びるため、海の男にしては屈強さがない。
かといって頼りないわけではなく、しっかりした筋肉の感触が布越しに伝わってくる。
肩から脇へ、脇から腰骨。太もも、膝、踝。
いつからかあの押し殺したような唸り声が再開していた。ぎりぎりと歯を鳴らしている気配さえする。
伊八がどんな目で自分を睨んでいるか、想像がついた。でも、まだ彼は本気で怒っていない。ここでウーリッヒがおとなしく拘束を解いてやれば、軽口に紛らわせてなかったことにしてしまう程度。
それでは駄目なのだ。
真っ白な踝を親指で撫で摩ると、伊八はくっと喉奥で擽ったそうに笑った。
「なにやってんの」
まだ彼は笑えてしまうのか。それが虚勢であっても、気に入らない。
下半身を拘束する縄のうち、ウーリッヒは右足を縛る縄だけを器用に解いた。左足は未だ柱にしっかりと括られている。
土踏まずのくっきり浮いた足を持ち上げ、ウーリッヒはたまらなく愛おしいその踝に口付けた。
ひゅっと息を飲む音。それはあるいは、目を瞠る気配だったのかもしれない。
唇だけでは物足りず、ねっとりと舌で舐めあげる――
瞬間、足が空を切る音。
「――ッのやろっ」
顔を狙った軌道からとっさに身を引いていたウーリッヒは、高く上げられた右足を音を立てて掴んだ。
掴んだ足をそのままに、ウーリッヒは伊八に肉薄する。
「あなたの愚かなところは」
着物の裾はあられもなく肌蹴ていた。日に当たらない肌は西洋人とはまた違った白をしていた。
どうにか右足を取り戻そうと、皮膚の下で筋が張り詰めている。しかし、こちらとてそう簡単に返してやるわけにはいかない。
体格に物を言わせて押さえ込んでしまえば、伊八に勝ち目はないのだ。
それを知っているから、ウーリッヒは勝者の笑みを浮かべた。獲物を前に舌なめずりする肉食獣の笑みだった。
「なりふり構わなくなるタイミングが遅すぎるところです」

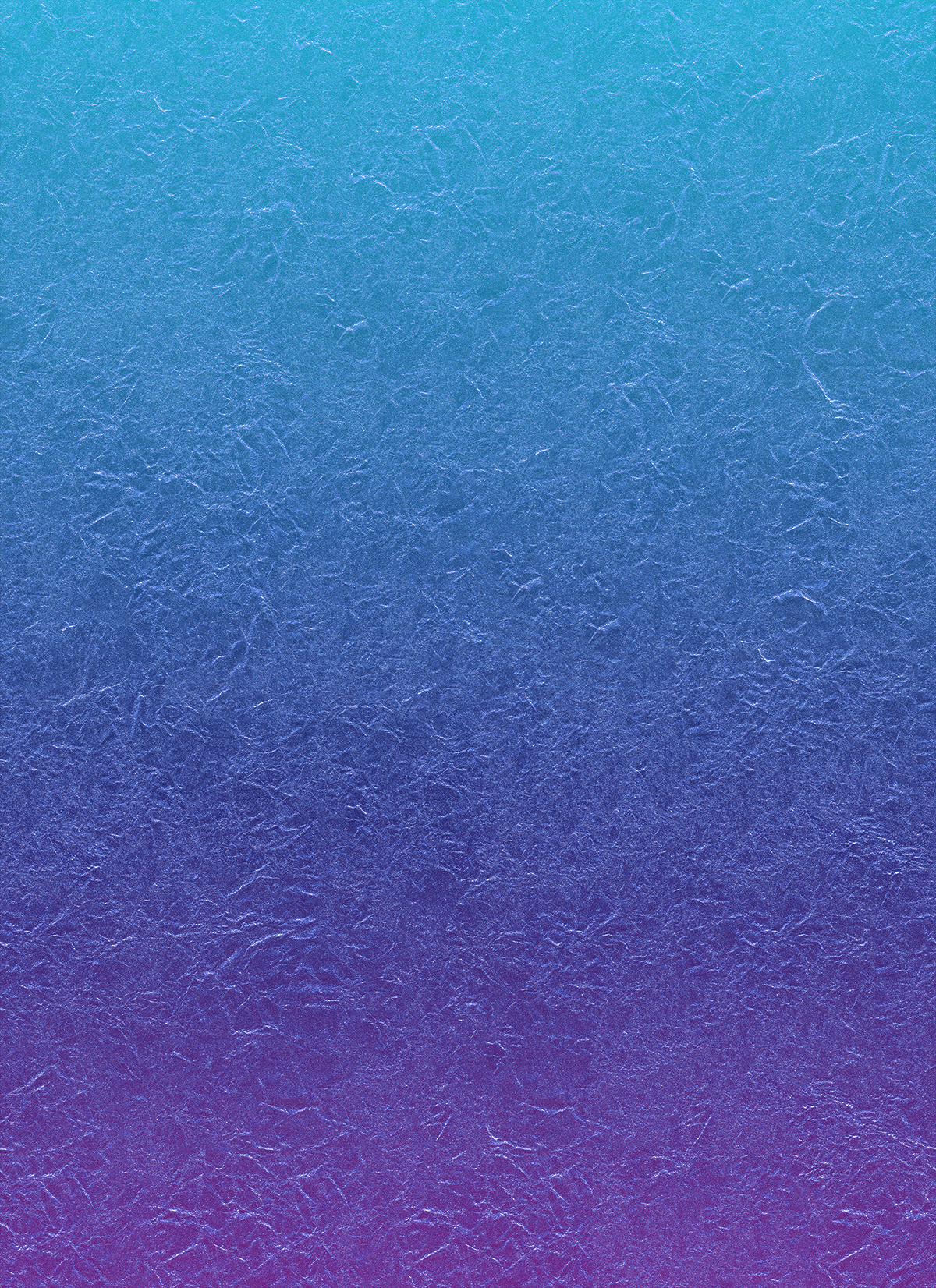
コメントを残す