赤の他人であるはずの自分を挟んでなぜか両側に陣取った独逸国籍の二人は、先ほどから売り言葉に買い言葉とばかりに口論を交わしている。それを聞きつつ、伊八はずるずると一人お茶をすすっていた(洋酒は体に合わないのだ)。
とてもつまらない。つまらないが、勝手に帰ることもできない。それにしても、二人ともよく飲む。本当に酒を飲んでいるんだろうな、というくらい、次から次へと杯を空ける。と同時に、口も動かす。
「大体だね、潜水艦に許される攻撃の手段などたかが知れている。武器の数も貧弱そのもの、魚雷を十本かそこら持ったところでそれを使い果たしたら貴様などまるで人畜無害、魚と変わりないではないか。そればかりか見つかってしまえば抵抗もできない、隠れている間しか力を発揮できない臆病者めが。そんなことでいっぱしの海の覇者の顔をされても非常に不愉快極まりない、その貧弱な武装をどうにかしてから来たまえ」
「そちらこそ馬鹿の一つ覚えのように武器の数にこだわって、それだから時代遅れだと言うんですよ。火力火力と言いますがこれからは機動力の時代です。一撃離脱こそが攻撃の要なのです。いかにこちらの損害を少なく、相手の被害を大きくするか。その点あなたは最悪です、鈍重な図体でのろのろ海の上を這いずり回って、下手な鉄砲でも数を打てば当たると思ってるんですか。そういうのを無用の長物というんです、ご存知で?」
……兵器としての構造上、もしくは取るべき戦術上の弱点というのはあるよな、とは思うが、そんな感想しか思いつかない。そもそも伊八はそんなこと考えたことすらなかった。自分がするべきことはお偉いさんに言われたとおりに敵を屠ること、それ以上でもそれ以下でもない。
ぶくぶくとストローで飲み物を弄んでいる伊八を尻目に、二人は近くを通りがかった給仕に次々と追加の注文を頼んだ。
――五分後。
「そもそもその根性が気に入らない! 数で囲んで海の下から不意打ちのように攻撃して仕留めることしかできないなど、海軍の風上にも置けない! それで勝ったつもりになっているとしたらとんだお笑い草だ、痴れ者だ、こんなのが味方だなんて信じたくもない。我々の名を騙って道端のチンピラみたいな真似をしないでくれるか、気分が悪いッ」
「それは私の科白です、いい加減にしてくれませんか、その自分以外のものを認めない古臭い考え方。これだから年寄りはいけない、老害とはまるであなたのためにある言葉ですね。言わせてもらいますが、あなたのその利己的なところ、昔から気に食わなかったんですよ。少しは周囲に感謝の気持ちを持ったらいかがです、あなた一人で戦争やってるんじゃないんですよ!」
あれ。なんだか個人の趣味嗜好の話になっていませんか。
そう思ったものの口に出す勇気はない。勇気と蛮勇は別のものであるからして、伊八はそうしなかったことを全く恥じも悔やみもしなかった。
二人が注文した新たな杯はすでに空になりつつある。最後の酒をくっと飲み干した二人は、ドンとほとんど同時に杯の底でカウンターを叩いた。
意外と気が合ってないか。
――三十分後。
「馬鹿者が! 少し敵弾掠めたくらいで簡単に沈むお前が知ったような口を利くな! 私は貴様らの打たれ弱さも憎たらしく思っているのだっ。潜航中に機関部をやられたら沈没を免れないなど、兵器としては三流以下、海に捨てるにしては少々大きすぎる廃棄物だとは思わないかね。断じて貴様の心配をしているわけではない、私は製造費とのコスト対効果のことを言っているのであって――」
「いい加減認めたらどうなんですか、あなたの敵は今や戦艦ではなく航空機、および敵潜水艦です。戦艦など巨大な的にしかならないのですよ。いくら対艦、対空兵器を備えていても数で負けるんです。動けないあなたは甘んじて攻撃を受けるしかない、それなのにあなたときたらいつまでたっても認めようとしない……! あなたに斃れられると士気に係るんです、士気に! おとなしく私たちに守られていてください!」
薄暗い照明も手伝ってか、いくら飲んでも顔色が変わらない彼らをさすが西洋人は酒に強いと感心していた伊八だが、どうやら思い違いだったようだ。完璧に酔っている。
というか、実はこの二人、とっても仲がよろしいんじゃないだろうか。
喧嘩するほどなんとやら、という諺を思い出す。
「もう帰ってもいいすかね……」
「私をこの青二才と二人きりにする気かね、アハト君!」
「こんな頑固親父と二人にしないでください、伊八!」
席を立とうとして両側から軍服の裾を掴まれた伊八は、なんかもうやだ、と泣き笑った。
今とても日本酒が飲みたい。

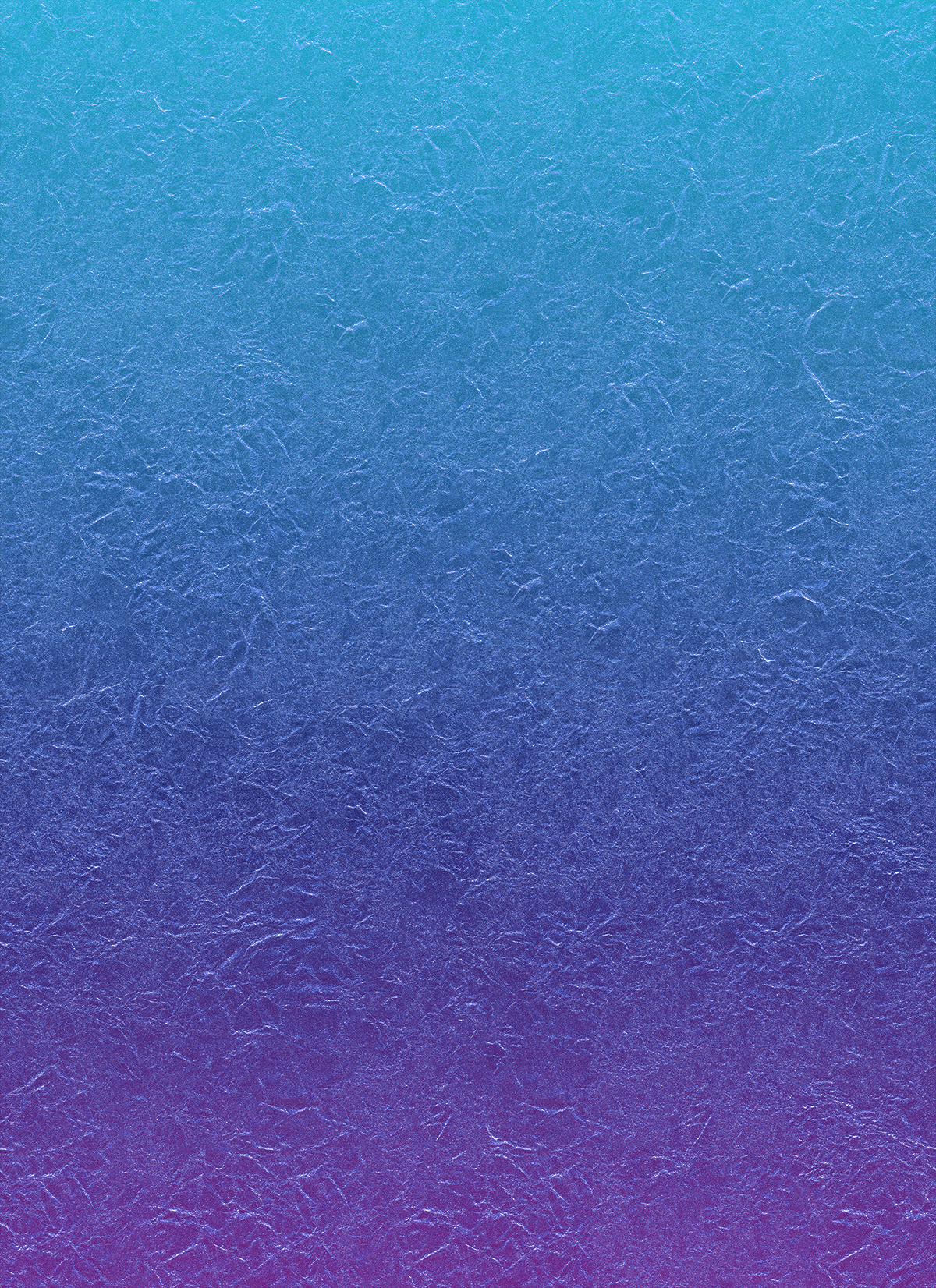
コメントを残す