ドナー
ニールにとって彼は、分身であり、弟であり、また息子であった。そして自分自身でもあった。我ながら馬鹿な事をしたと思ってはいる。今どきクローンなんて流行らないけれど、それでも生み出してしまったのはひとえに己の弱さゆえだ。戦いを選ぶ自分と、未来を生きる自分が必要だったのだ。
復讐は成し遂げられなければいけなかった。しかし、がむしゃらに前だけを——見方を変えれば後ろだけを——見続けるには、ニールは現実的な感性の持ち主であったし、また平和を渇望する心が邪魔をした。くじけそうになる心を支えるために平穏の偶像を作り上げねばならなかったその行為が正解だったかどうか、ニールは答えを持たなかった。
未だ目覚めぬ片割れの右頬を触る。石膏より温かな、人のぬくもりがしてニールは、これを守ろうと決意した。これの平穏を守るためならばどんなことでもしてみせると、ただ偶像を目の前にして誓った。
アクセプタ
彼を呼ぶのにふさわしい名を、持たなかったというのが正しい。
ニール、と親しみをこめて呼べるほど近しい存在ではなく、同じディランディであればミスタ・ディランディと呼ぶのも変だ。兄でもなく、弟でもない。完璧な合同図形であるがゆえに、ふさわしい呼び名は存在しないのかもしれなかった。
だからライルは、ただ彼のことを「あの人」と呼んだ。他人のようで、しかし誰よりも明確な指示詞を宛がって、ライルは彼を「あの人」と呼ぶ。
あの人のことを「兄」と呼ぶ日が来るとは思っていなかった。こんな自分をみて、あの人はどう思うだろうか。ただひたすらライルの平穏のために戦って死んだ、あの人が今の己を見たら。
まるで進んで争いごとに足を突っ込もうとしている自分を、そんなはずではなかったと悔いるだろうか。ライルは実は、そうは思っていなかった。
ほかでもない、あの人の分身なのだから。あの優しい人の分身が、自分の平穏だけを願ってのうのうと暮らすことなどできるわけないと、ライルは確信すら抱いている。
きっと苦笑して、許してくれるだろう。同じ形をしているはずの頬を手のひらでたどって、そっとその表情を想像した。

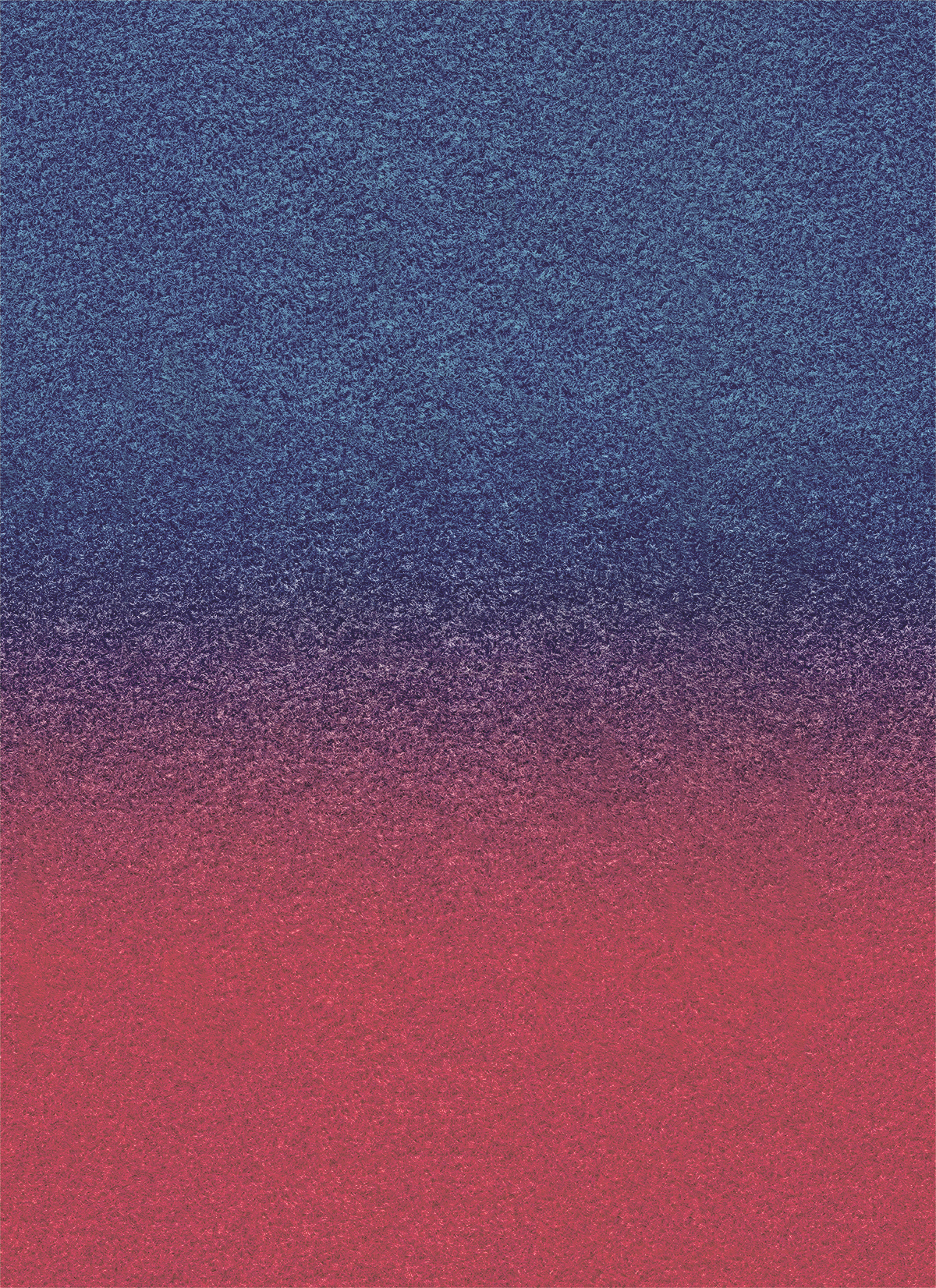
コメントを残す