なんだかとてもいい夢を見ていた気がする。
薄ら明るいだけだった視界の中央に黒い影が像を結ぶ。それがサーヴァント、レオナルド・ダ・ヴィンチのものだとわかっても、未だロマニは夢の中にいる気分だった。彼が、見たこともないような表情をしていたから。ずっと晴れない痛みを抱えた患者のような、親の余命を告知された子のような、難病の症例を前に悩む医者のような。
「起きたかい」
耳に残る高い声はどこに置いてきたというのか、それは囁く様な音だった。だから心配になった。唯我独尊、悠々自適を地でゆく彼をここまで憔悴させるのは一体なんなのか、できるならそれを取り除いてやりたいと思った。
「……なにか、辛いことでもあったの?」
ロマニの声もまた掠れるように小さかった。痰でも絡まっているのか声が出辛いが、咳き込むのも億劫だった。代わりに細く息を吐く。ゆっくりと吸う。ただの呼吸だというのに、とても長い間そのやり方を忘れていたような、気がした。
ロマニがそうして一呼吸をする間に、レオナルドは本当に、本当に微かに唇を歪めた。それから瞳を閉じて、一言だけ。
「いいや、なにも」
その答えに安堵してロマニは再び襲い来る睡魔に身を任せた。安らかな暗闇が意識を飲み込むまでの束の間、最後に見た唇の角度が瞼の裏に残って消えた。
歪んだ唇は笑みというより、嗚咽を耐える様にも見えた。

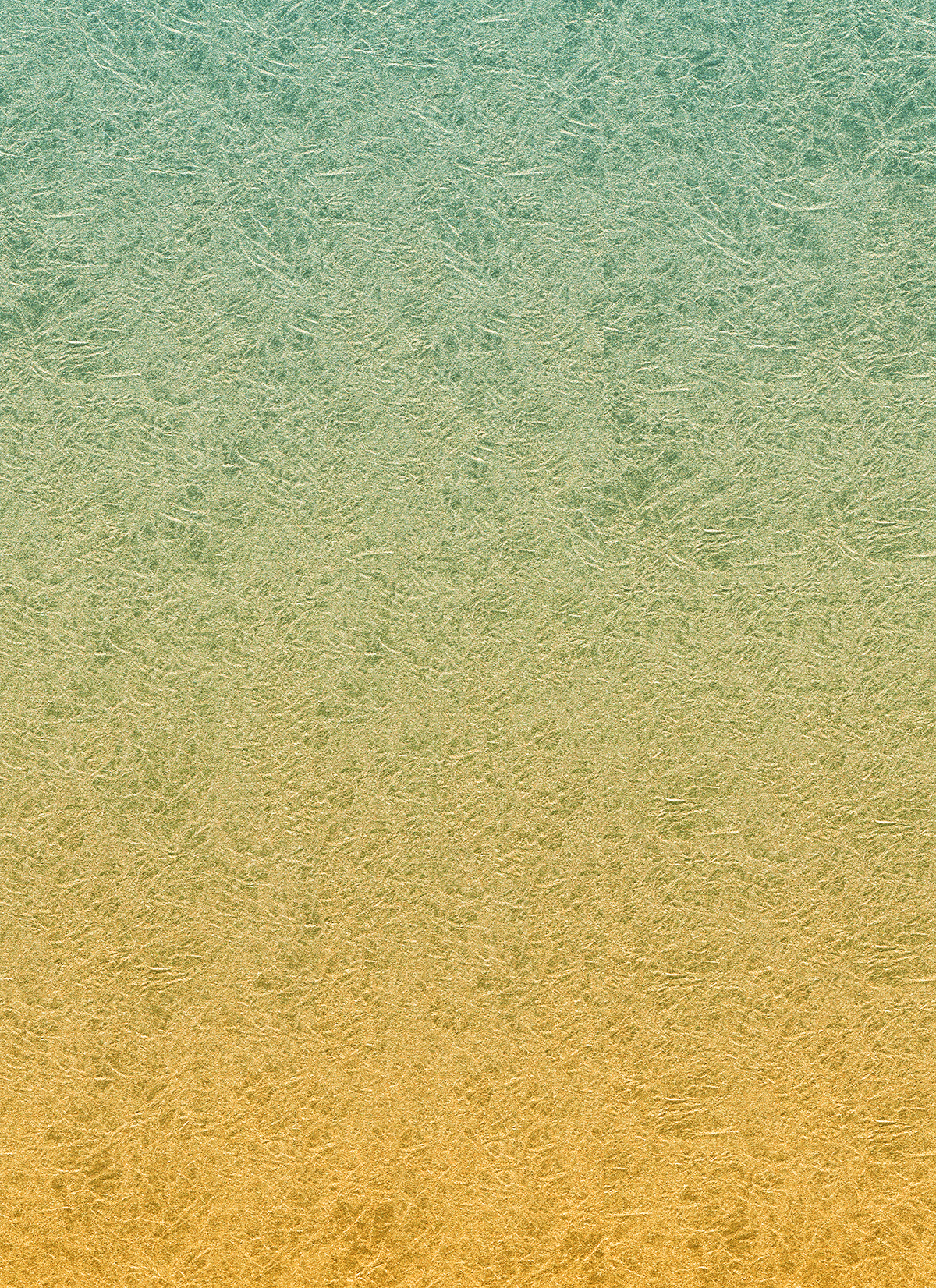
コメントを残す