ロード・エルメロイⅡ世は一種異様な熱気を感じ思わず立ち止まった。
カルデアの娯楽室の前である。普段ならそこは手持ち無沙汰のサーヴァントたちが三々五々集まってカードゲームに興じたり、映像記録の鑑賞に用いたりしているだけの部屋なのだが。
かくいうエルメロイⅡ世もまた本日今この時、まさに手持ち無沙汰であった。そうでなければこの部屋に立ち入ろうなんて、一瞬たりとも考えつかなかっただろう。そういうわけで彼はちょっとした好奇心もあって、その扉を開けてしまった。好奇心は猫をも殺すのである。
クー・フーリン(キャスター)の場合
「ふあっ、あ、あーっ、ん……ッ」
まず耳に入ったのが、うまく文字化すればそんな感じの音声だったので、エルメロイⅡ世は部屋に一歩踏み入ったところでしばらく硬直した。まずい、と、後から思い起こせばなぜそう思ったのかわからないがとにかくそう感じた彼は、直ちに扉を閉めた。この時既に彼は室内に足を踏み入れている。なぜ入る前に扉を閉めなかったのか、これもまた悔恨の残るところである。
室内にいたのは男どもばかり五、六人。何人かはダーツ機の前に屯しており、また何人かはバーカウンターで酒を煽っている。時刻が時刻であるせいか――ちなみに午後十時過ぎ――、室内は薄暗い感じに照明が落とされており、オトナのアソビバめいた雰囲気を醸し出していた。もう少し、もう数時間前だったら、いくら娯楽室とはいえもうちょっと健全な感じで女子供も楽しめる雰囲気であっただろうに。
しかし、なにより不穏な空気を醸し出しているのはダーツでもバーでもなかった。普段はスクリーンで映画が上映できるようになっている一角、大人三人がゆうに座れるだけソファーの、その上。
「あ、そこ、そこ、やべぇ、気持ちぃ」
「ここ?」
「そこ、あー、あーっ。ふあ」
「こっちはどう?」
「ンん……は、アッ、そっちも、いいッ、いいからっ」
さっきからあられもない声を上げているのは、カルデア最古参と名高いサーヴァント、ランサー……ではなかった。キャスター? 何種類か同一人物を元にしたサーヴァントが顕現しているので、紛らわしいのだ。とにかく、青い髪したケルトの光の御子が、普段の落ち着いた低音はどこへやったのか、大きな声を出しているものだからほら、ダーツ遊びに興じている連中もさっきからチラチラと集中できていない様子である。酒飲み連中はいい酒の肴くらいに思っているのかもしれないが。
とにかくその隠しもしない喘ぎ声――そう、使いたくないが、喘ぎ声との形容が一番この状況に適している、使いたくないが――はきっぱりと公序良俗に反していた。喩えそれが「マッサージ」によって引き起こされているものだとしても。
そう、マッサージなのである。ソファーの上に横たわったクー・フーリンが揉みしだかれている場所は、首から肩甲骨にかけての筋肉。そこに手をかけられる度に彼の口からは大きな声が漏れ出ている。体重がかかって肺から息が押し出されるのか、やたら空気を含んだ声が艶めかしい。
普段はローブに隠されている背中は、今はその行為のために露わにされていた。ランサーの彼ほどとは言わないが流石にたくましい。しっかりと張った、しかししなやかな獣のように優美な曲線を描く肩。ケルト人の白い肌は薄暗い照明の中でも輝いて見え、それがやたらと隠微である。ローブがすべて脱がされず、肌蹴たようになっているのも良くなかった。長い髪とローブが覆う背が、却って何も覆うものがないより……よろしくない。何がとは言わないが、よろしくないのである。
そして、そんな男の上に乗っかっているのが「彼」というのも、非常に問題だった。
エルメロイⅡ世は意を決して、その誰も近づかないソファーセットの一角まで足を伸ばし、彼ら二人を見下ろす位置で声をかけた。
「おい」
「ふあ、はーっ、はあっ、うー」
「あれ、ロード。どうしたの珍しい」
「んぁ、あっ、あう、ん。んー」
「私のことはどうでもいいが、……とにかく、それを一度やめてくれないか、マスター」
「ん? ああ……クー・フーリン、そろそろおしまいね」
「えっ、やだ! もっと、もっと、そこ、頼むッ、――アデッ!?」
最後のはエルメロイⅡ世がキャスターの頭を思いっきりひっぱたいたせいだ。聞き苦しい声には違いないが、先程までのアレより大分マシである。
マスターがおしまいと言って体を離す。それに大層未練がましい顔をした彼は、今までマスターの下に置いていた体をするりと起こすとこちらに噛み付いてきた。
「おい、なんで叩かれなきゃいけねーんだよ!」
「うるさい黙れ。胸に手を当ててよーく考えてみろ!」
調子が戻ってきたようで、なんとなくホッとする。そう、彼はどちらかと言えばそうしている方が似合うのである。
「はいはい、喧嘩はだめだよー」
「……あんたも相当問題だぞ、マスター……」
「なにが?」
まったく無自覚の少年に、エルメロイⅡ世は頭を抱えることしかできない。言っていいものか。あなたのその手遊びが大の男を喘がせていたんですよ、と。しかし、あまりに無垢な瞳で見上げてくるので、はっきり言及するのは却って愚かな事のように思えた。
「……あなたもわざとやってたわけじゃないだろうな、キャスター」
「はあ? なにがだよ?」
そして、逃げ道を探すように矛先を変えても、こちらもまた無自覚なのである。手に負えない。
「ダメですって。その人達自覚なしでやってんですもの」
果たして途方に暮れているエルメロイⅡ世を救ったのは、そんなお気楽な声だった。ダーツ遊びに参加していた一人――アーチャー、ロビンフッドである。
ロビンフッドの場合
「この人らのおかげでさっきから妙な雰囲気だったんですけど、さり気なく注意しても聞かないもんですから。止めてくれて助かりましたよ、ロード」
緑の外套を羽織った弓使いは、その手に持ったダーツをくるくる弄びながらいまだソファーの上であるマスターとクー・フーリンを顎でしゃくって苦笑いした。ようやく話が通じる人物が出てきて、エルメロイⅡ世は溜飲を下げる。
「そもそもどういった経緯でこんなことに?」
「いつもの主従の戯れだったはずなんですけどねぇ。『キャスターなんてのは肩が凝る』ってこのお人が言い出したのを、『俺マッサージ得意だよ』ってマスターが乗っちゃって」
「実家でばあちゃんの肩よく揉んでたからね。上手だって褒められたものだよ」
ロビンフッドの説明に乗っかってきたのは当のマスターである。その横では、未練がましいそうにクー・フーリンが袖をつついていた。
「なあ、ほんとにもうやってくれねーのか?」
「確かに凝ってたね、クー・フーリン。槍を使う筋肉と杖を振るう時の筋肉で使う場所が違うのを意識したほうがいいかもね。今のあなたはキャスターで、その体もそれに見合ったものなんだから、ちゃんと自覚しなくちゃ」
「しまったな。導く者であるはずの俺が諭されちまった。ま、それを抜きにしても気持ちよかったからな。また機会があったら頼むぜ」
ひらりと裾を翻してソファーから立ち上がったクー・フーリン。どうやら行く先はバーカウンターらしい。どうやら年代物のウィスキーがお披露目されていたらしく、目を輝かせんばかりにしているのを見ると先ほどの痴態――言いたくないが――はやはり何かの間違いだったのではと思わざるをえない。
「さて。それで。次は誰がマッサージされたい?」
背後からこちらもニコニコと目を輝かせているマスターに声をかけられ、ギクリとする。まだやらかす気なのか、この人は。
――基本的に人のいいロビンフッドは、エルメロイⅡ世が猛烈に首を振ったことで代わりに自分が生け贄になることを選んだようだった。
「ちょっと興味ないわけじゃないですし」
とは、心からの言葉か建前上のものか。
まだこの時までは、ロビンフッドもエルメロイⅡ世も、そうは言っても所詮マッサージ、と高を括っていたのだった。
「……ン、ッく」
緑の外套を脱いで肩を露出した彼は、さすがアーチャーとあり質のいい筋肉を持っている。若々しくつやのある肌に、少年然としたマスターの手が乗り、優しく撫でさすった。それに肩を震わせて、彼は首をすくめる。
ちなみに今回、ロビンフッドはソファーに寝そべることなく、腰掛けたままだ。背後に回ったマスターは立ったまま、肩から首にかけてを弄っている。
「ふ、くく」
耐え切れないような笑い声が上がった。
「なに笑ってるの?」
マスターの手はようやくそこと決めたらしい、頭の付け根、髪の生え際のあたりに親指をあて、徐々に下へと下ろしていく。
「くふっ、ひっ!」
一際高い声が上がった。
……なにかがおかしい、と気づいたのはエルメロイⅡ世だけのようだった。
マスターの手が動く度に、明るい茶の髪が小刻みに震える。俯いているので表情は分からないが、膝の上の手はなにかを耐えるように時折開かれてはまた握り締めるという動作を繰り返している。
「大丈夫?」
「……だめ、も、ダンナ、だめだこれ、」
マスターの問いかけに、ついに堰を切ったように拒絶の言葉が漏れた。
「何が?」
「く、くすぐったいっ、から、ひッ」
そのまま前に逃れようとするロビンフッドを、許さないとばかりに両手で肩を掴んで留めるマスター。
「そんなことないって。気持ちいでしょ? もうちょっとやってみよう」
そう言って、掴んだままの両手で今度は肩と首の筋を揉みほぐし始める。ロビンフッドの震え声は一層大きくなる。
「も、いいっ、いいって、ひぐ、く、くは、あはは」
肩を抑えられているせいでさっきまで隠れていた顔が顕になった。印象的な垂れ目が細められ、その目尻からは耐え切れない涙が滲んでいる。と思えば、よほどくすぐったい場所に触れられたらしい。突如見開かれた目から、ぽろりと大粒の涙が零れた。新緑の瞳が濡れている。正反対に、目尻は赤く染まっている。
「えー? 敏感だなあロビンは」
「ひ、ひぃ、くすぐ、った、やだ、ひっ、腹、はら痛いっ」
「……カット!!!!!!!」
呆然としていたエルメロイⅡ世は次の瞬間、思わず叫んでいた。
ドクター・ロマンの場合
もういやだ。
久しぶりに身も蓋もなく泣きたい気分だった。こんなのは、かの征服王と聖杯戦争に参加していたとき以来――いや、時計塔で手に負えないワルガキ共をしつけていた時も何度か――。思い返すとそう久しぶりの衝動でもないことに気づき、いや気付かなかったふりをする。それに、どんなに泣きたくても泣かないのがエルメロイⅡ世の強いところでもあった。
目の前では、ようやく責め具から開放されたロビンフッドが、息も絶え絶えな様子でソファーに身を預けている。上気した肌の具合とぐったりした脱力加減、その様もなんだか目に毒である。
「おっかしいな……。こんなにくすぐったがられること、今までなかったんだけど……」
それはおそらく、このロビンフッドという英霊がマスターが相手にしてきた今までのどの相手よりも敏感だったからだろう。生前も大群を相手取り孤独な戦いを続けてきたというし、まずここまで身を任せられるような関係を人と築いたことがなかった、そういうことなのでは。とは思うものの、やっぱり発言が不適切な気がしたのでエルメロイⅡ世はすべてを飲み込み必要最低限のことだけ口にした。しようとした。
「私は、そろそろお暇――」
「あれ、ロード・エルメロイ? こんなところに」
新たに参入してきた気の抜けるような声がなければ、きっぱりさっぱり、こんな異常な空間とはおさらばできたのだが。
「ドクター」
マスターが言うとおり、メルヘンチックな赤毛をポニーテールにしたカルデアの現司令塔、ドクター、ロマニ・アーキマンである。白衣に白手袋のいつものスタイルで、マスターでさえこの時間は楽な格好をしているというのに、まだ仕事をしていたらしい。この人はこんなだが、割に責任感が強い。決断力も兼ね揃えたよい司令官だとはエルメロイⅡ世も常日頃から感じているところだ。そう、こんな時でもなければ、よい司令官だと。
「ロードに何か用事?」
「いや、本来はキミに。明日のレイシフトの予定だけど、午前十時の予定、午後イチにずらせるかな? ちょっと機材調整に時間がかかりそうで……」
「問題ないですよ。スタッフたちの都合に合わせます。無理しないでって伝えてください。もちろんドクターも」
和やかに会話を続ける二人の後ろで、ようやく息を整えたロビンフッドが気取られないように離脱してゆく。非常に羨ましい。
「ありがとう。それでエルメロイ卿、キミは明後日健康診断の予定入れたからね。今日はいいけど、明日は飲酒と喫煙は控えること」
緑の英霊を恨めしそうに見ていたエルメロイⅡ世は、突如振られた話題についていけなかった。健康診断?
「また……なぜ」
「他の英霊と違って、あなたは擬似サーヴァントなんだ。肉体のメンテナンスが必要になる。人間と同じに」
忘れそうになるが、彼は本来医療セクションのトップである。スタッフだけならずサーヴァントの体調管理にまで気を配るのは彼の元来与えられた役目といえばそうだ。
「まったく、あなたも気苦労の多いことだな。本当は私からこの葉巻を取り上げたいだけなんじゃないか?」
「ま、喫煙が健康に利するところなんて一つもないから、やめられるならそうしてほしいけど。それとこれとは別だよ。キミの体を心配してるんだ」
喫煙を制限されるのが嫌で、子供じみた抵抗をしてみるが――それが余計だった。マスターに会話に入る隙を与えてしまったという意味で。
「肉体のメンテナンス……。よし、ロード! ここは一つオレがマッサージを――」
「――ところでドクター。あなたも随分お疲れみたいだ。マスターのマッサージなんて受けてみてはどうかね?」
「え? うん? マッサージ?」
なんとか、被害者になるのだけは、避けたが。
「…………ぅ」
あれよあれよと乗せられるがままソファーに横になったドクターは、今は白衣の上だけ脱いだ姿でマスターに馬乗りになられている。
デスクワークの人はやっぱりね、とマスターは早々に彼のための施術部位を腰に定めたようだった。
先行のクー・フーリン、ロビンフッドに比べると、流石に非戦闘員である彼の体は薄かった。普段はゆったりとした白衣に覆われている腰など、マスターが手を回すと意外なくらい細い。なんだか見てはいけないものを見た気がして、思わず目を逸らした。
「ン――ッ、……っ」
それにしても。
今までの二人と比べて驚くほど……静かである。マスターが力を込める度に耐え切れないような吐息は漏れるものの、それだけだ。
そうだ、本来マッサージとはこういうものだったのではなかろうか。今までがおかしかっただけで、これなら。
そう思い視線を戻す。ソファーの肘掛けに隠れるような場所で、ドクターは自分の両手で口を塞いで顔を真っ赤にしていた。
「っ、ふ、……んッ」
「気持ちいい?」
やにわ、マスターがその手を離してドクターの顔を覗き込むように伸び上がる。口から手を外し、ふう、と大きく息をついたドクターは、
「気持ちいいよ」
とおそらく本心からの言葉を返す。
「ふーん」
マスターはそれを聞くと、再び腰を押す作業に戻った。するとドクターは再び、すべてをこらえるように顔を腕に埋めてしまう。
「……ッ、……っふ、……っ」
「ドクター、ほんとに気持ちいい?」
今度は腰を揉みながら、マスターが問う。苦しそうにしていたドクターは、それでも何も返さないのは悪いと思ったのだろう。
「ん。気持ち、い、」
顔を抑えたまま、なんとか出した声はか細く震えていた。
「ねえ、声ださないの? そのほうが楽だよ」
追い打ちをかけるような更なる問いかけ。答えられない、と言わんばかりに頭を振るドクターを、マスターは許さなかった。
「なんで?」
「あ、だって……恥ずかしい、」
そのタイミングを待っていたように。というより実際待ってたのだろうな。これは。もう確信犯だ。天使のようなあどけない顔をした悪魔は、ドクターが口を開いたのを見計らって、力強く腰を押し込んだ。
「アッ、――くぅ、んんッ」
子犬が泣くような切ない声が漏れて、ドクターは耳まで真っ赤になっている。
エルメロイⅡ世はといえば、遠い目をして明日までに飲む葉巻の本数を想像するくらいしかできない。
「あ、次はロード、あなたの番だからね?」
今宵は長くなる。そんな予感がする。

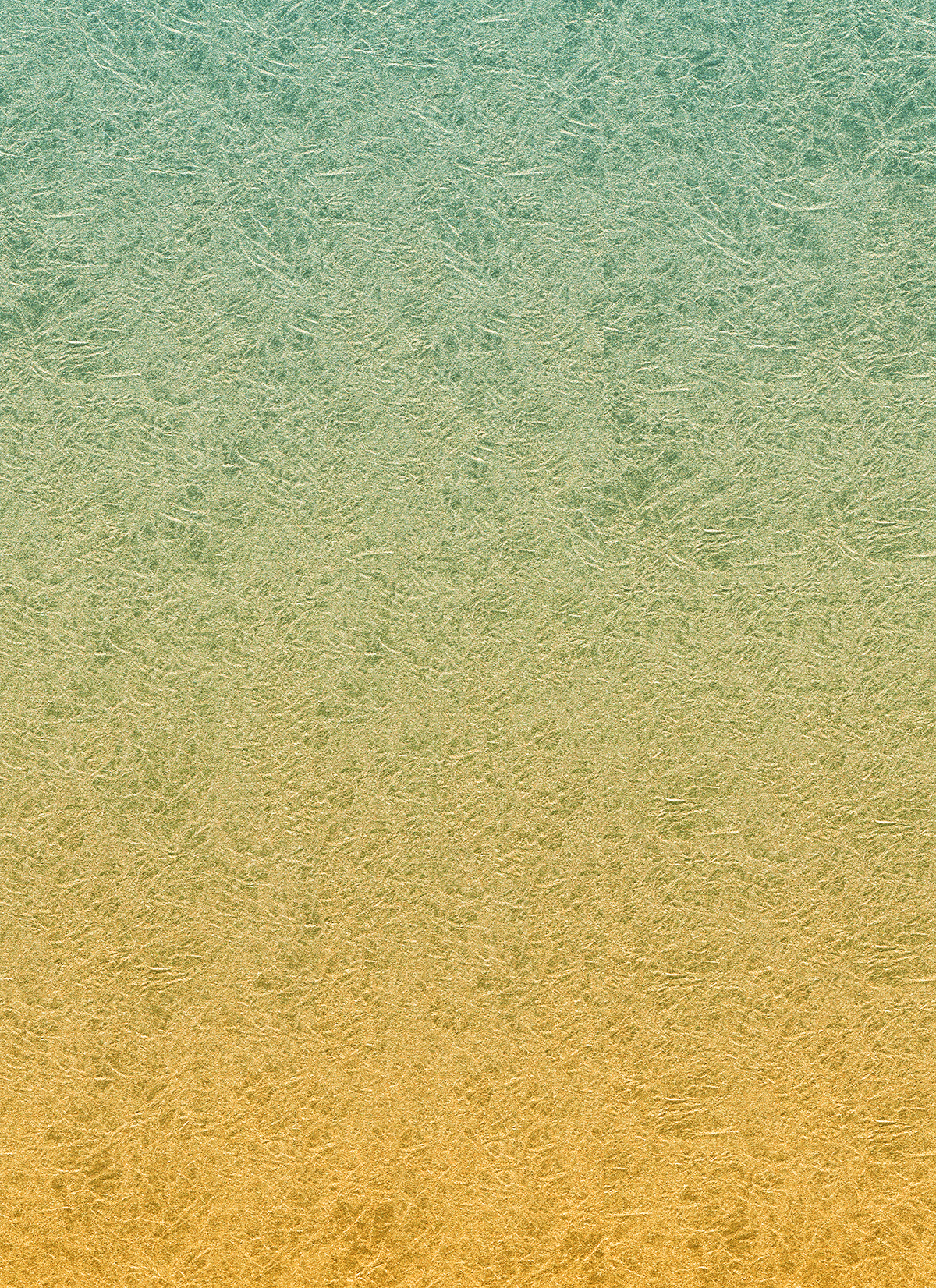
コメントを残す