目を覚ますと、モナ・リザは微笑んでいなかった。
名画が台無しだな、とまだ覚醒しきらない頭でロマニは考える。しかし、モデルとなったかの女性だって常日頃から微笑みばかり浮かべていたわけでもあるまい。憮然と、半眼で、虫けらを憐れむような顔で、寝起きの男を見下ろすこともあったかもしれない。例えばそう、こんな風に。
「起きた?」
「……レオナルド?」
みっともなく声がかすれて、何度か咳込んだ。仰向けに寝ているのが却って辛く、無理やり上体を起こすとコップ一杯の水が差し出される。ありがたく受け取って飲み干す。もう一杯、コップと突き返すと、彼――便宜上、ロマニは彼のことを「彼」と呼称することにしている――レオナルド・ダ・ヴィンチは、その美しい顔に苦笑めいたものを浮かべ、はいはい、と目隠しのカーテンの向こうに消えていった。
慌てて飲んだせいで口の端から零れた水が、喉をつたって白衣を濡らす感覚に、少し我に返った。周囲を見渡す余裕ができる。
嗅ぎ慣れた消毒用エタノールの匂い。無機質な白い壁に、申し訳程度の観葉植物。いつでも使えるようにと三日前にメイクしたベッドは、その時はまさか自分で使うことになるとは思っていなかった。医療セクションの長たるロマニの、本来の仕事場。いやというほど見慣れた部屋。しかし、どうしてこんなところに? たしかさっきまで――
だんだんと記憶が鮮明になってくる。そう、今日は朝から忙しかった。
カルデアにはたまにやたらトラブルばかり起きる日があって、今日はまさにそんな一日だった。昨日のレイシフト明けからシバの調子がご機嫌斜めで、一晩付きっきりで面倒を見たものの結局今日午前予定されていたレイシフトは延期。しかも技術部のコフィン定期メンテナンスが重なったせいでスタッフの手が空かず、昼過ぎまでかかってようやくシバの調整が終わる。午後は午後で地下の発電所の電圧が急に不安定になり、整流器が相次いで破壊。急いで取り替えているうちに、月一の全所員定例ミーティングの時間が迫っていた。立て続けのトラブルで一日中立ちっぱなしの働きっぱなし、ミーティングの間は座ってられるから気が楽だと、油断したのが悪かったのか――とにかく、そこから記憶がすっぽり抜けている。
――まずい。まずいぞ。
何がどうなって会議室にいたはずの自分が医務室に移動しているのか。まさか、倒れたのか? だとしたら最悪のタイミングだった。ミーティングには全所員が参加している。そのスタッフたちの前で倒れるようなことは、絶対にあってはならないことだった。これは、ロマニの面子やプライドとはまったく関係のない話だ。残された二十人に満たないスタッフの士気を保ち、人類最後の砦たるカルデアを適切に運営していくための、組織の長を任された人間が果たさねばならない義務だった。
人類の希望は、はたして恐ろしく脆い。それはすべてを小さい肩に背負って立つマスターの素質のことを言うのではなく、カルデアという組織そのものに言えることだった。少しのことで簡単に崩壊する危険性を帯びた、まるで砂上の楼閣。寄せ集めの人員で辛うじて動かしている、張りぼての城。まだ若いが確かな血統と能力を持ったオルガマリー、協調性に難はあっても優秀だった魔術師達。そういう支柱にあたる部分を真っ先に欠いてしまったこの組織を虚勢だけで支えている、それがロマニだった。彼が持っているものなどたかが知れている。医療に関する知識を除けば、あとは十年近くこの組織に属しているうちに身についた経験とも呼べない雑多な知識だけである。なんの因果か生き残ってしまった、人並みかあるいはそれより少しはマシ程度の頭脳を持った一介の医者であるロマニにできることといったら、虚勢を限りなく本物に近づける努力くらいだ。つまり、長時間の労働と、それを悟らせずに笑っていること、くらい。
皆が皆無理をしている。だが、その長たるロマニがここで少しでも揺らいで見せれば、辛うじて保たれていた緊張が一気に弾けることは――想像に難くない。
最悪の事態まで一気に辿り着くと、さして残っていなかった血の気がさらに下がった気がした。今は何時だ。今からでも間に合うだろうか。一体何に――とは考えが及ぶ前に、とにかく時計を探そうと頭を巡らすが、時間など気にせず休めるようにとこの部屋のベッドから見渡せる範囲に時計を置かなかったのはロマニ自身だった。今になってそんな過去の自分が恨めしい。
その手に冷えたペットボトル入りの水を持って再び顔を見せたダ・ヴィンチに、噛みつくようにしてロマニは尋ねた。
「何時?」
「午後六時三十二分。ミーティング終了後から一時間五十二分が経過。そろそろ食堂が開いて、スタッフと一部の食いしん坊な英霊たちが押し寄せてるころさ。ちなみに今日のメニューはカレーライス。キミ、食欲は?」
「そんなことより」
「そんなこと? キミ、自分が何をしでかしたか分かってるの? いや、正確には、『しでかそうとした』か、かな。少し落ち着きたまえよ。この天才ダ・ヴィンチちゃんがいるかぎり、フォローは万全さ」
「何が起きたか教えてくれ」
「ミーティングが始まって十分で爆睡。私は後ろで見てたけど、船を漕ぐでもなく死んだみたいに静かに寝てたよ。そのせいか誰もキミが寝入っているとは気づかず、終了前にキミの発言の番が回ってきてようやくバレたくらいさ。今日一日キミが駆けずり回ってたことは、だいたいの所員が知ってたからね。ドクターはお疲れなんでしょうって好意的に受け入れられたのはまあ、キミの日頃の行いが良かったからって言ってあげてもいいけどね。起こすのも忍びないからって皆して私に目配せしてそのままミーティングを終わらせて、残された私はキミを叩き起こした。起こそうとした。そしたらキミ、眠ってると思ったら気を失ってるじゃないか。椅子から転げ落ちても起きないから、とうとう死んだかと思った。それで、このダ・ヴィンチちゃんが人目につかないように配慮しつつ手ずからキミをここまで運んできてやったってわけだ」
そういえば左肩から上腕にかけて動かそうとするとものすごく痛い。折れてはいないだろうが、ひどい打ち身の気配がする。彼の言うことは間違いないらしい。
「つまり、ボクは会議で居眠りしていた情けない所長代理のままかい?」
「そうさドクター。キミのカルデアはまだ崩壊していない。青い顔して昏倒していた姿を見られていたら、どうなっていたかわからないけどね」
深い深い吐息が口から漏れた。
「…
…良かった……」
起こしていた体から力が抜けて、ふらついた頭をヘッドボードに盛大にぶつけた。痛い。
「ふん。それで? ちょっとは食欲が戻ってきたかい?」
「コンソメスープくらいなら頂きたいかな」
「結構。後で自分で取りに行くように」
「取ってきちゃくれないのかい」
とにかく最悪の事態だけは回避出来たことで、わずかに余裕が戻ってきた。ダ・ヴィンチのそれを軽口と受け止めて返すと、彼は大きくため息をついて、またあの、愚かな生き物を哀しむような目をした。彼がこんな風に物言いたげにすることはとても珍しい。言いたいことは軽口からモノの核心まで、なんであれためらいもせず言い放つタイプだから、言いよどむ姿など見たこともないと言ってもいい。
彼は、なにやら決心してそれを言うことにしたらしい。しかし、出てきた言葉はロマニにとっても予想外だった。
「私は私のことを、キミの友人であるという風に認識していたけれど、違ったかな」
「うん? ああ、もちろん……。いや、ありがとう。今回のことは助かった。キミがいなかったらどうなっていたか――」
彼の質問の意図を咄嗟に受け取り損ねる。そんなことを改めていわれるとは思わなかった。素直に返事をすると、彼はますます眉をしかめる。どうやら不正解らしい。
「そう、私はキミの友であって、間違ってもお母さんじゃあない。食事も睡眠も私が世話を焼いてやる義理はないよ。キミは誰かに言われないと食事も取らないのか? 睡眠も? 自分の限界も自分で見極められない? さっきまでの様子だと、キミにもちゃんと自覚があるようだったけれど、それなら最低限人前で無様を見せない程度に体裁を取り繕ったらどうだい? なんのために無茶をするって決めたんだ? 自分で自分の覚悟を水泡に帰すような真似をするな」
珍しく語気を強め、彼はロマニを視線でもって牽制した。いつもみたいな中途半端な答えで逃げるなと、ラピスラズリの青が見つめている。
「怒ってるのか?」
やや場違いな問いではあったが、ダ・ヴィンチは眉の上げ下げ一つでそれで往なした。
「怒っているとも。キミの覚悟を愚かにも認めてしまった過去の私にね。……やると決めたからには最後まで貫き通してくれ。それができないなら始めからやるな。私は自分が見誤ったとは思いたくないよ」
彼が言い淀んだ理由がわかった気がした。ダ・ヴィンチは、決してロマニの体を心配したわけではない。だが、ロマニが倒れることでロマニ自身が目指す場所に到達できなくなることを心配している。友という言葉を引き合いに出して、まだお前はそこへゆこうとしているのか、その覚悟を再度問うている。それは彼にとって苦しい作業であるのだろう。万能の人たる己が一度認めたことを再度問い直さなければならない、その苦痛。裏返せばそれはダ・ヴィンチがいかにロマニを認めているかということとほとんど等価なのだが――ロマニはそこまで気づいていない。
「キミを不安にさせたことは謝る。悪かったよ。ボクはキミに認められたボクの覚悟を放り出すようなことはしないから、安心してくれ」
「そう、なら、結構」
ダ・ヴィンチはふと表情を緩めると、ロマニの前髪をぐしゃぐしゃとかき混ぜてから部屋を出ていこうとした。
それに慌てて声をかけたのはロマニのほうだ。
「ねえレオナルド! 今ボクがフラフラ食堂に出て行ってごらんよ。却ってスタッフの心理面に悪影響を与えかねない。かと言ってキミがボクの分の食事を運んだりしても、やっぱりおかしなことになるね。それで提案なんだけど、ボクは久しぶりに腹が減っているんだ。そしてそこの棚にはインスタントのスープが入っている。電気ケトルは流しの横。マグカップでよければ、おあつらえ向きにちょうど二つある。どうだろうか?」
「ほんと、友達甲斐のあるやつだよ、キミは!」

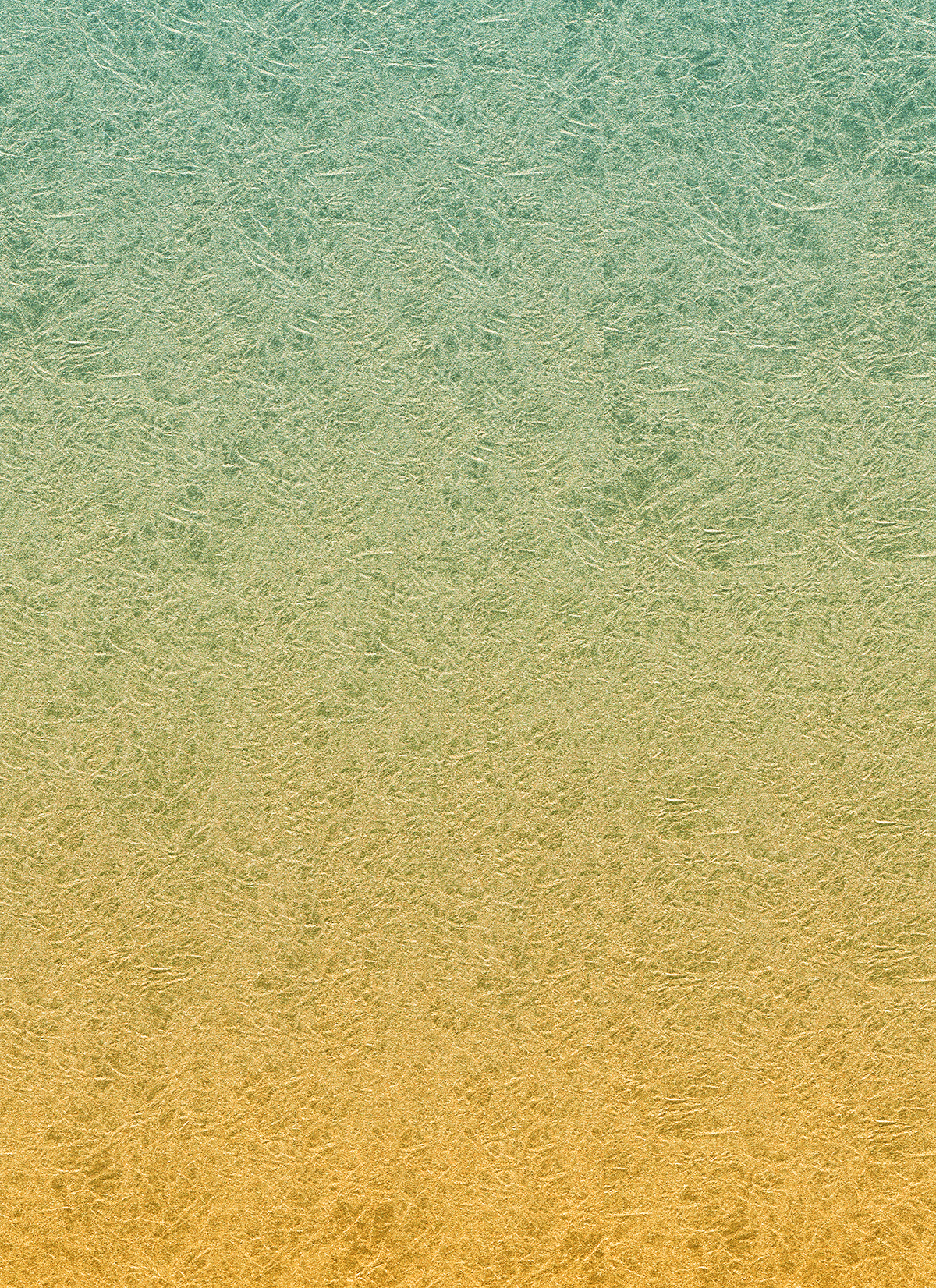
コメントを残す