朝飯が終わると、屋敷はにわかに騒がしくなる。
遠征、出陣、あるいは当番があたっている刀どもはそれぞれに支度にかかり、そうでないものも各々の予定に従って、庭や修練場に三々五々散ってゆく。
審神者もまたその例に漏れず、食後の茶を一服して母屋から執務室のある離れまで廊下を渡っているところである。
春もたけなわ、といった時期で、日に日に新緑の勢いの増す輝かしい季節である。庭の木々は我先にと太陽のほうに葉を伸ばし、鳥は自由に恋の歌を口ずさむ。一年の中でももっとも過ごしやすい、とくによい季節である。
最近よく耳にする鳥の声が、また今日も朝からせわしなく鳴いている。鳥の名前などとんと興味がない審神者でも知っている鳥の鳴き声は、どうにも、
「……うまくないなあ」
「何がだい、主」
ぼそりとつぶやいたのを聞きとがめられる。ひょいと視線をおろすと、縁側の柱の脇に煎茶色した頭が覗いている。鶯丸である。丸盆に急須と茶碗が一つ乗っているところを見ると、いつもの茶道楽とみえた。
「キミもどうだ?」
「いや、さっき飲んできたところだ」
鶯丸は、茶を喫する時必ず器を自分のともう一つ、用意する。通りすがりを引き止める口実にするためである。さりとて、誘いを断ったところで彼はそうかい、なんて予め知っていたようなふうに言うので、あんまり用をなしているようには思えない。
と、その折、またあの鳥、要するに、彼と同じ名前のウグイスという名の鳥が、鳴いた。二人してなんとなしに声のしたほうを――はっきりわかるわけでもないので、漠然と庭のほうを――見やる。鳴き声の余韻が空気に溶けて消えるまでまって、ほらなあ、と口を開く。
「どうも、今年のウグイスはうまくない」
「なるほど」
早春から鳴き始めるその鳥は、なぜか今年に限って、歌が下手なのである。巣立ったばかりの若いウグイスはまださえずりが上手くないとものの本で読んだ覚えがあったので、しばらくすれば良くなるものかと毎朝聞いていたのだが、一向に上達する気配がない。ウグイスにも音痴はあるのかしらん、と哀れに思うくらいである。
「ウグイスってのは、ホーホケキョ、と鳴くもんだろ。あれじゃあせいぜい、ヒーホキョホキョ、だ」
「ヒーホキョホキョ」
鶯丸は審神者の言うのを律儀に真似て、それから何がそんなに面白かったのか、一人でツボに入っている。
「ヒーホキョホキョ、かい。あはは。ヒーホキョホキョ」
確かにそう聞こえるのだから仕方がない。まず、入る音が高すぎる。ホー、というからには、もっと低くなければならない。ホーというのはフクロウの鳴き声と同じだ。それくらい低い方がいい。その後は、ホケキョ、と三つ音を並べればいいのに、なにを勘違いしているのか、ホキョを二回も繰り返しているから、間が抜けて聞こえる。一回で鳴き切るつもりで、気を入れてかかれば間違えない。
と、まあ、語れば語るほど腹をよじって笑う鶯丸が面白かったので、調子に乗った。ボン、ボン、と大広間の壁掛け時計が九つなって、始業の時間が来ていることに気がついて、慌てて執務室に急ぐことにする。先に来ている長谷部を待たすと、あまりいいことがない。
「ヒー、ホキョホキョ」
庭でまたウグイスが鳴いたのに、鶯丸が返事をして、笑っているのが聞こえている。
*
次の日の朝、同じ時間に同じ場所を通ると、やはり同じように鶯丸が縁側に腰掛けて茶を飲んでいる。
「キミもどうだ?」
「いや、さっき飲んできたから」
昨日と同じやり取りをしていると、庭でウグイスが、ホーホケキョと鳴いた。
「あれれ」
どうしたことか、うまくなっている。姿が見えるわけでもないが、ウグイス違いじゃなかろうかと目を凝らすが、間違いないと言わんばかりに、もう一度ウグイスが、それは上手に鳴くのである。
「上々だな」
茶を一口飲み込んだ鶯丸が、にこにこと頷いている。それを数瞬見下ろして、確信した。
「お前、何かやったか」
「なあに、キミが昨日喋ったのを、そっくり伝えてやったまでさ。なんの道でも、上達の一番の近道は、いい師匠を見つけるに限る」
「師匠って」
「よう師匠。お唄の師匠。あはは」
それからひとしきり、また何がツボに入ったのか鶯丸は笑い転げている。
しばらくした五月の朝、ウグイスの声で起こされた日があった。びっくりして目を開けると、番のウグイスが窓際から飛び立つところだったので、もしかしたらお礼の挨拶に来たのかもしれないと思う。

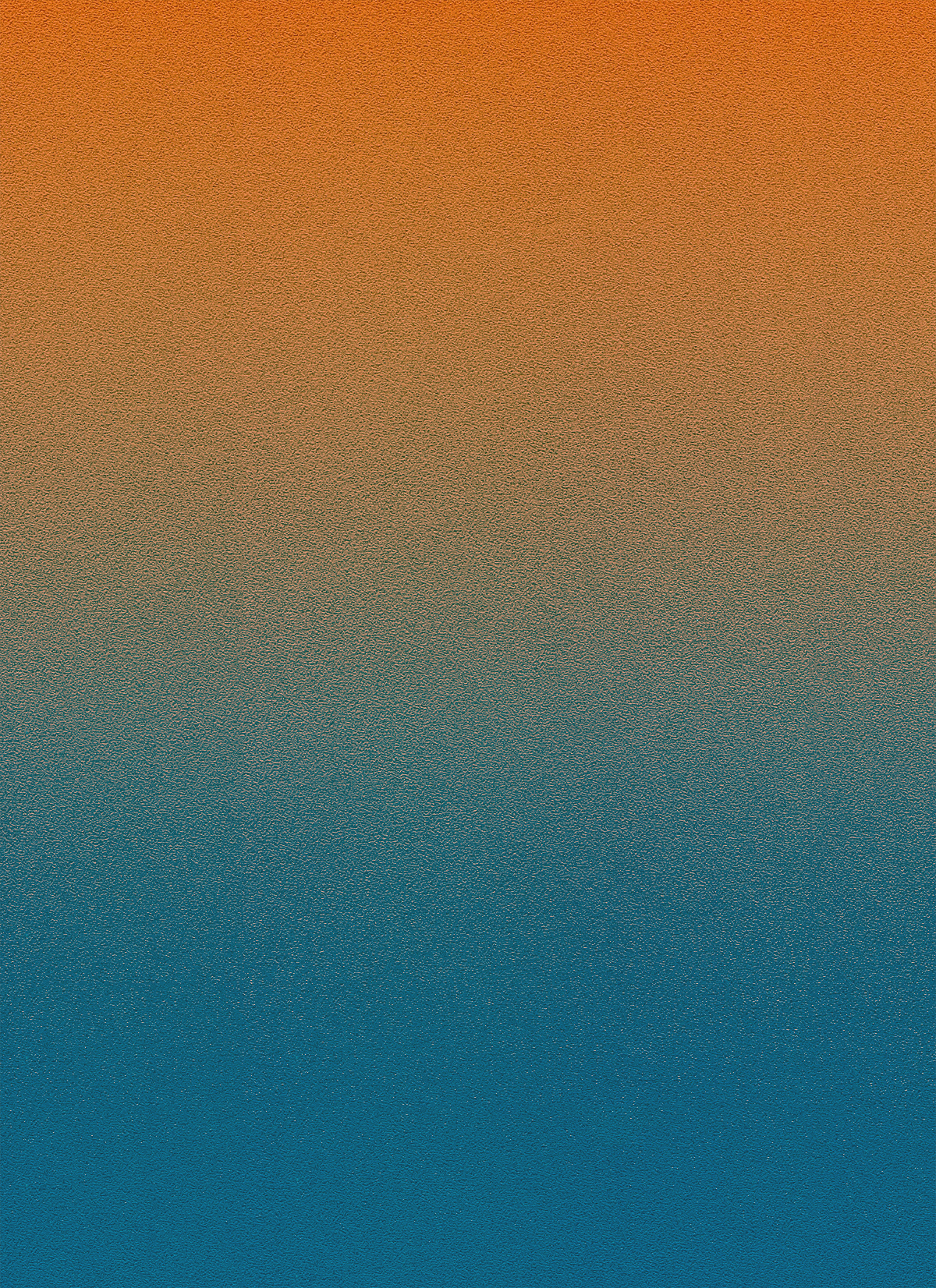
コメントを残す