冬の終わりの雨の日のこと。
審神者が新しい刀を呼ぶと言って鍛錬所に篭って数時間が経った。短刀やら脇差ばかり呼び寄せる審神者にしては随分長いこと戻ってこないから、何か都合の悪いことでもあっただろうかと、この本丸の初期刀にして近侍の加州清光は足早に廊下を歩いている。
もっとも、そう悪いことは起きていない気がしていた。むしろ良いことが起こるような、今日は朝起きた時からずっと、そういう予感があった。尻の座りが悪いような、首のうしろの後れ毛が収まらないような。
清光は自分の勘を信じるタイプだ。そしてその勘はついぞ外れたことがない。だから今だって、早足なのは何かが起こって審神者に害がおよぶのを心配しているというよりかは、ただ予感が成就するその瞬間を逃さないためだった。
ぐるりと巡る濡れ廊下の最後の角を曲がる。耳のすぐそばでしとしとと雨音がする。吐く息は白く、特に外側を向いている体の半分が寒い。それでも、先日まで降るのは雪ばっかしだったから、雨というのは暖かくなっている証拠である。審神者が大広間に掛けたカレンダーは、こないだ三月に変わったところだった。
廊下のどん詰まりから草履に履き替えて、その先にある小屋へ向かう。そこが鍛錬所と祈祷所が一緒になった別棟で、戦場で拾った、あるいは精霊が鍛え上げた刀に審神者が魂を呼びこむ場所である。
廊下から別棟まで、一応屋根が付いているから濡れはしないが、心なしか一層寒い。二三歩大股で辿り着いた建物の、一つしかない扉を開けると、そこは鍛錬所になっている。火の気はすでになくしんとしていた。精霊の姿もない。もう刀はとっくに仕上がっているということだった。そのまま部屋の奥のもう一部屋へ向かい、草履を脱ぐ。白木の上がり框を踏む。
「あるじ。入るよ」
声をかけながら、襖の引き戸に手をかける。
「ああ、うん、どうぞ」
気の抜けたサイダーみたいないつもの審神者の声がして、遠慮もなにもない仲だから、清光はするりと戸を開けた。
祈祷所にも火は入れられないことになっているから、そこは外と変わらないくらい寒かった。たった六畳ぽっちの狭い部屋に、人影は二つ。こればっかりは褒めてもいい、ぴんと背筋を伸ばして座る見慣れた主の姿。そしてもう一つ、視界に収めてああ、と嘆息が漏れそうになるのをぐっとこらえる。顔に出てはいないと思うが。
だって、ああ。なんだ、
「なんだ、お前か」
空色のだんだらを見たら、懐かしい記憶がとたん溢れだしたような気がした。おかしい、今までだって、どっかの脇差とは違って記憶の一つも失っていた覚えはないというのに。
猫っ毛の黒髪。細い眉と丸い瞳。真っ白な肌は正直何度羨ましいと思ったことか。羽織の胸元をほっそい指がぎゅっと握りしめている。ちょっと力を込めて握ったらぽっきり折れてしまいそうなその指が、どんなふうに刀を繰るのか、清光はよく知っていた。
「大和守安定」
名を呼べば、冬のよく晴れた空みたいな瞳が、ひたりと清光を捉え、お返しのように呼び返される。
「加州清光」
そのまま動こうとしない安定に、審神者が居心地悪そうに両手を宙に浮かせるから、さては自分が到着する前になにか一悶着あったなと、勝手に想像を巡らせる。これ以上この寒い部屋に審神者を置いておくのは忍びなく、清光は多少強引に二人の間に割って入った。
羽織から引き剥がすように掴んだ手は、驚くほど冷たい。まるで、さっきまで氷の下にいたみたいに。
「ばか。お前。手、冷たすぎ」
強引に引っ張ると、案外たやすく立ち上がった。後ろで安心したように笑っている審神者にも、早く広間に戻って暖かい茶でも飲ませなければいけない。

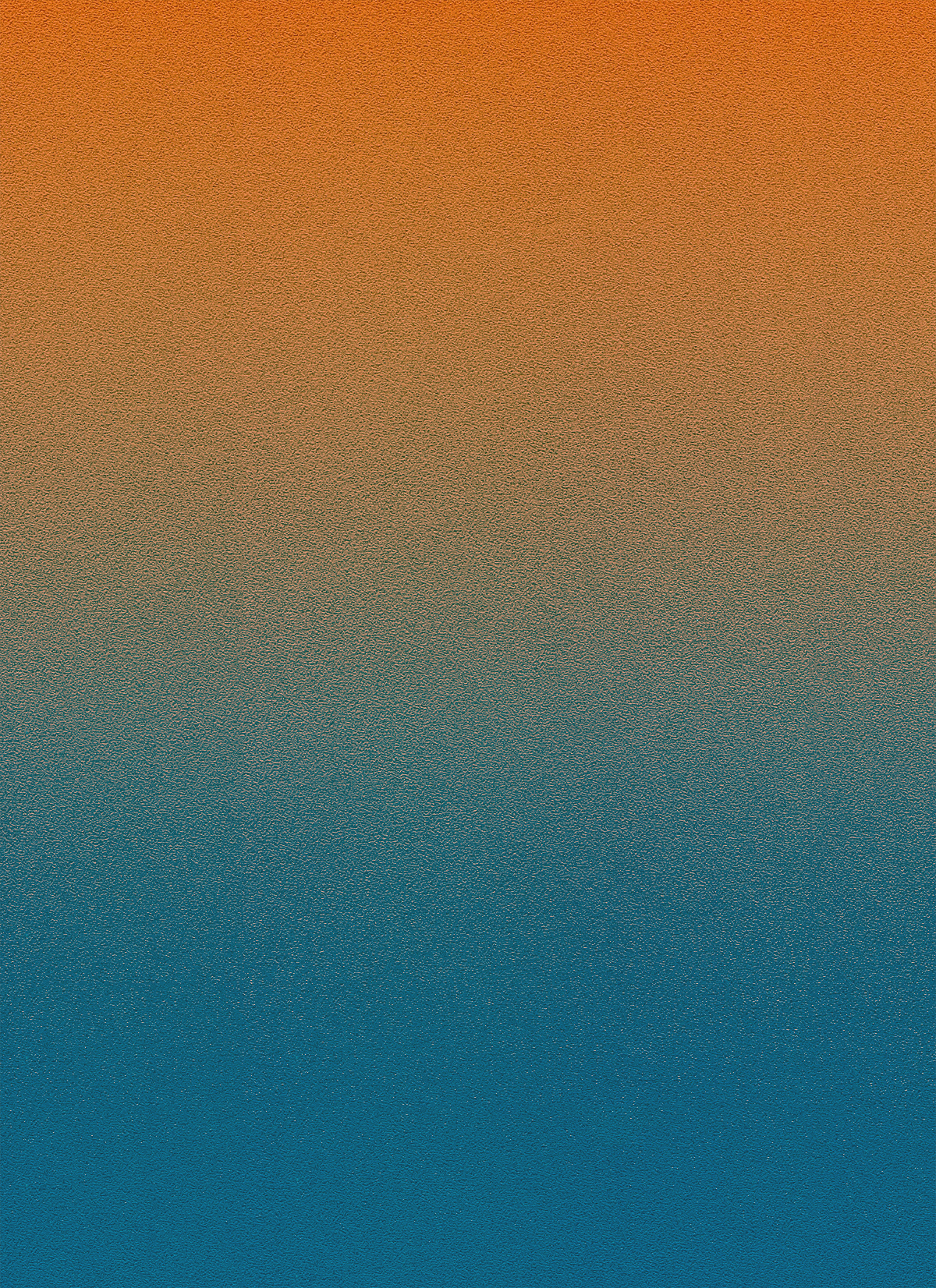
コメントを残す