ヴィクトル・ニキフォロフという人は、人懐こい。
今までメディアを通した彼しか知らなかったせいか、いやいや、雑誌やインターネットの記事でだって、彼という人のサービス精神の旺盛さやスキンシップの多さについては触れられてたはず。
それでもこうして直に接してみて勝生勇利は実感するのである。
ああ、この人、人懐こいんだ。
そもそも勇利は人間関係の構築を不得手とする方で、友達と言えばリンクメイトと長谷津の幼馴染くらい、SNSも押し切られる形でアカウントは持ったが更新頻度はお察し。彼女なんて夢のまた夢、まともに会話する相手といえば家族くらいなものである。
そんなところに突然、超の付くスキンシップ魔がやってきたものだから、勇利にしてみたら生ぬるい羊水から五十度の灼熱温泉に突き落とされたようなもの。その荒療治に最初こそ混乱しっぱなしだったが、最近はむしろ今までの社会性のなさが災いして、「これが世間の標準なら慣れねば」と勘違いまでする始末。結果的にその治療は成功した――と言えなくもない。
「ユーゥリ、今朝の調子はどうだい?」
今日も今日とてパーソナルスペースをゼロ距離に詰めて肩を組んでくるコーチに、はい、とどぎまぎしながら答える。慣れよう慣れようと努力はしているのだが、いつまでたっても心臓が跳ねる。すぐ近くに作り物みたいな小作りの顔があって、心なしかいい匂いさえする。
ぎぎ、と油切れのブリキのような不自然さで首を回すと、さらさらの銀の髪が目と鼻の先にある。あまりに近すぎてピントの合わないそれに、なんの魔が差したんだか、触れてみようという気になったのは。このままじゃいけない、と強迫観念?使命感?とにかく緊張の裏返しだったのは間違いない。
そ、と顔が乗っているほうの腕を動かし、反対側から手をのばす。視界の外側からだったから気が付かなかったのだろう。指先に絹のような触り心地の冷たい髪の温度を感じたのと同時、彼は振り返るより早く勇利の手を掴んで引き下ろした。
予想外の反応に掴まれた腕を振り払うこともできずに固まる。彼は彼で、自分の掴んだものを確認してぽかんとしている。そして一言。
「……びっくりした」
「な、なんですかだめですか、だってあなたが先に仕掛けてきたから――」
「や、もちろん、だめじゃないけど」
びっくりしただけ、と彼は再度繰り返した。
こんな過剰な反応を返されるとは思わなかったから、驚いたのはこちらのほうなのに。
彼は捕らえたままの勇利の腕を抱え直し、しげしげと眺めている。鑑賞に値するほどの手ではない。彼のような繊細さもない、のべっとしたただの手。それを愛おしそうに撫ぜるので、どんどん居た堪れなくなってくる。
「あのっ」
「ふぅん。これはこれで、なかなかいい。俺にとって、手は差し伸べるものであり、差し伸べられるものではなかったから」
その言葉の意味を深く理解したのは、もう少し時間がたってからだった。とにかくそのときは気が気ではなくて、差し伸べるとか、どうとか、そのあたりの語感への違和感だけで口を開けたり閉じたりしていた。
「そんなつもりじゃ」
「だーめ」
彼が勇利の手を持ち上げる。凍えた水色の瞳が、勇利を見つめて融ける。そのまま、手のひらに頬を寄せて、ゆっくりと瞼が伏せられた。
触れ合った場所から伝わる温度は、ひんやりとしている。ならば今、彼の頬は勇利の熱を感じているだろうか。

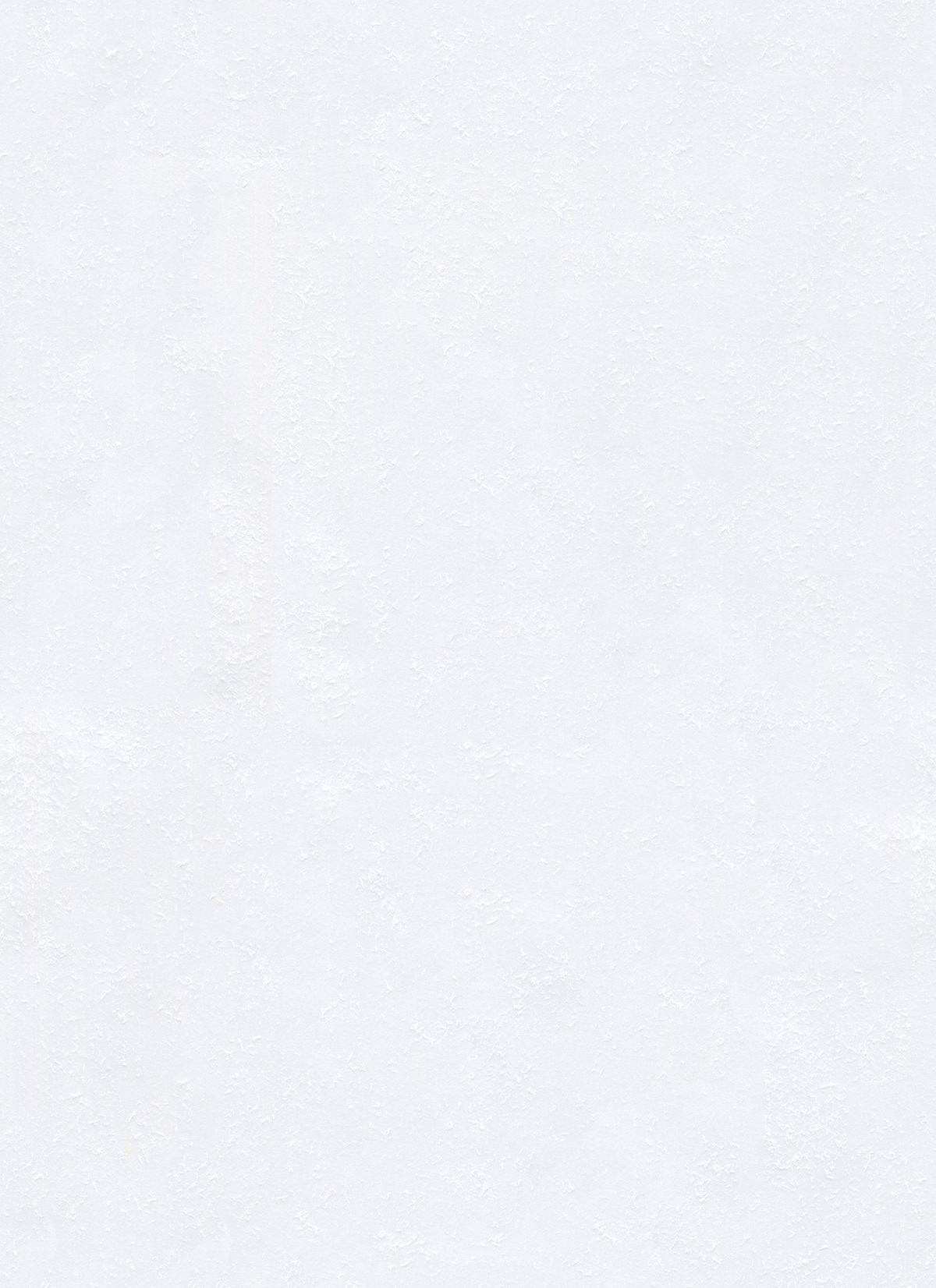
コメントを残す