「お前、驚かなかったな」
縁側で、蚊取り豚と寂しくビールを飲んでいる後ろ姿があまりに悲しかったので、隣に行って座ってやった。
枝豆を持って行ったせいか、追い払われることはなかったが、特別会話が弾むわけでもない。一人が二人になったところで何も変わらないかと、自分たちの後ろ姿を想像して笑った、その時だった。
「何が」
「俺が帰ってきても、驚かなかっただろ」
その時、初めて侘助を正面から見たように思う。
十年前と、あまり変わっていないようにも見えたし、まるで変わっているようにも見えた。なにせ十年だ。変わらない方がおかしいと思うのだが、どこが変わったかと聞かれたら明確に答える自信はない。
この歳になっての十年は、そんなものかもしれない。
「驚いたよ」
「嘘つけ」
「嘘じゃないさ」
気の早い秋の虫が鳴いている、その音源を庭のどこかに探しながら、とうに空になっていたグラスを呷る、ふりをした。
本当は、驚いたのかどうか自分でもよくわからなかった。
侘助の消息自体は、仕事柄耳に入っていたし、プライベートでもちょっとインターネットを検索すればヒットしたから知ることはできた。
それでもこうやって帰ってくるなんて思っていなかった。だって彼は、この家を出て行った人間だ。そんな男がひょっこり帰ってくるなんて、一度でも想像しただろうか。
「想像してたかなあ」
「なんだよ、いきなり」
「こんなふうに帰ってくるって、想像してたかなと思って」
こうして、栄の誕生日に、親戚一同が大勢いるところにふらりと現れることを、自分は想像しただろうか。それとも、それ以外の、たとえば冬の寒い日に、たとえば春のウグイスが鳴くころ、たとえば秋の紅葉のころ――ひょっこり彼が帰ってくることを想像したかといえば、やはりどれも想像していないと思った。
だから、こんなふうに帰ってきたりして、驚いた、のだと思っていた。
「驚いてなかったみたいだ、やっぱり」
「ほらみろ」
「うん。どういうふうに帰ってくるかは知らないけど、いつか帰ってくるって思ってたんだろうな。だから驚かなかったんだろうな」
恐らくは。
「別に出てったと思ってなかったんだな、俺は」
対外的に、彼は家を出て行った、そう認識してはいたが、自分の頭の中はそうでなかったらしい。
「俺は多分、お前がいつ帰ってきていても驚かなかった」
どの親戚とも同じ感覚だった。自立した子どもがいつ実家に帰ってきても、誰も驚かないのと同じだ。理一の中で侘助はいつまでたっても叔父であり、いつまでたっても陣内の家の一人だった。
「俺はお前が、この家を捨てて行っただなんて思っちゃいなかったから」
「……俺じゃなくて、この家が俺をいらないと言ったんだ」
「十代のガキじゃあるまいし。そんなこと本気で考えてるわけじゃないだろ」
侘助は煙草をつけた。
「もう飲むのはやめか」
「お前が酔っ払っちまってるみたいだから、やめだ」
「俺は別に酔ってなんかいない」
「嘘つけ」
「嘘じゃない」
リーリーと鳴く、虫の居所を探して、視線がさまよった。
「とりあえず、……おかえり」
「酔ってるだろ、そんなクサいこと言って」
「うん。やっぱり酔ってるなあ」
だから、隣から「タダイマ」なんて聞こえても、理一はひとつもおかしいとは思わなかったのだ。

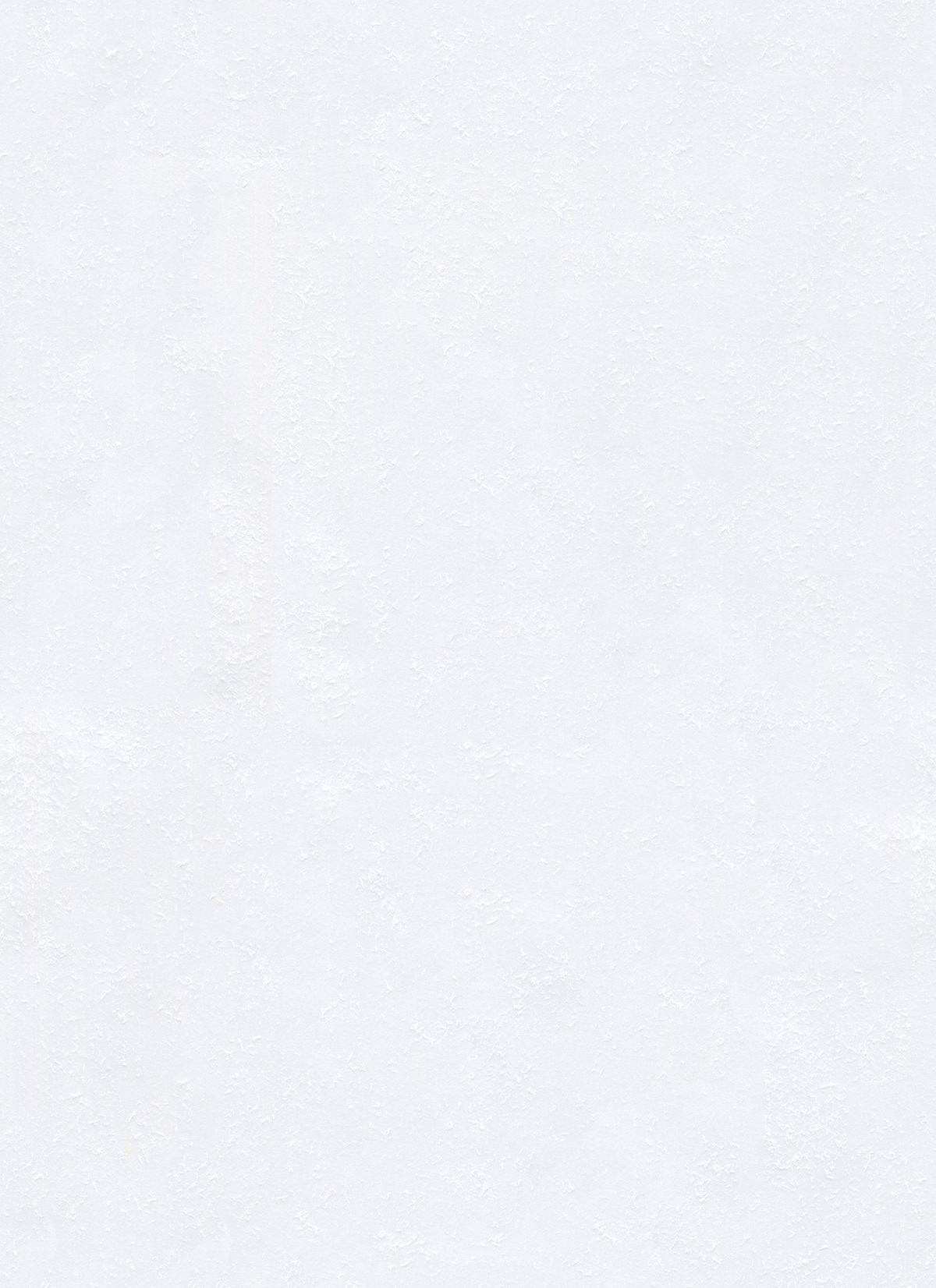
コメントを残す