後から聞いた話だけれど、ちょうど十二回目で僕は顔を上げたらしい。
「健二さんってば!」
「ん? ……あれ、佳主馬くん?」
遮光カーテンのペールグリーンが部屋全体を緑がかって見せていた。その中にあって彼の褐色の肌は異物だ。ただ単に、部屋と違って見慣れていないだけかもしれないけれど。
見慣れない、けれど異物というのはひどいなあと我ながら思う。
僕はぽかんと口を開けて彼を見上げていた。
「どうしているの……?」
「どうしてって……連絡してあったよね? 来週行くよって」
「でもそれって日曜――」
床に座っている僕をまたいで――この春買った二人掛けのソファは背凭れの役目しか果たせていない――、彼はずかずかと窓際に進み、両手でカーテンを開けた。シャッとレールが鳴り、昼の日差しがようやく部屋に差す。……昼?
「もう日曜だって、わかってないみたいだね」
「にちよう……今日が?」
何か言いたげに眉をひそめ、佳主馬くんは僕の横に座った。ひょいと手元を覗き込んで、なにこれ、と視線だけで問う。
「新しい暗号方式の論文……公開鍵暗号なんだけどRSA方式より強度があって、でもここなんだけど、」
と数式の載ったページを差そうとして、ぱっと紙束を取り上げられた。
あ、と思わず声が出る。
「そういうことを聞きたいんじゃないの。僕はこういうのは専門外だし言われてもよくわかんない」
「情報科なのに?」
「数学科の院生が一日以上熱心に読みふけってた論文の中身なんて分かるわけない」
ようやく僕は、自分のしでかした間違いに気がつき始めた。
彼は怒っている。
「ご、ごめん……なさい」
「なにが?」
「君が来たことに気がつかなくて」
「そういうことじゃないでしょ」
はあ、と重たい溜息だった。年下の彼にそんな溜息をつかせてしまうほど、僕はどうしようもなかっただろうか?
「あ、今片付けるから」
ローテーブルの上には飲みかけのカフェオレと、プリントアウトした論文の束、レポート用紙にシャープペンシルとその芯が乱雑に散らばっていた。
いつ入れ直したかもわからないカフェオレは、もう口に入れる気にならなかったから、これも片付けなければならない。
立ち上がろうとした僕を、佳主馬くんが横から引っ張ったせいで、僕はまたもとの位置に逆戻りだ。
「あの、佳主馬くん? えーと……コーヒー飲む?」
はあ。これ見よがしに再び溜息を突かれて、僕は少し怯んだ。その怯えをちゃんと理解して、彼は僕の頭に手を伸ばす。
くしゃくしゃとかき回されるのは、犬か何かになったみたいだけれど、手の感触が案外嫌いではなかった。
「健二さんは座ってて。じゃあテーブルの上だけ片付けておいて。僕がなにか作る。どうせなにも食べてないんでしょ」
「なにも……そういえばそうだ」
曜日を勘違いしているくらいだ。僕はまだ土曜日が終わっていないものだと思っていたし、現に最後に食事をとった記憶は土曜の朝まで遡る。丸一日以上、コーヒーしか飲んでいなかった。そういえば眠った記憶もない。
それを素直に申告すると、彼はもう溜息をつかなかった。
「僕が怒ってると思った?」
「うん」
「健二さんはたまに数学の国に行ってしまうよね」
「え?」
さっきから僕はえ、とかあ、とか、そういう短い言葉しか喋れていないような気がする。なんてことを考えたのは、彼の言っていることがうまく理解できなかったからだ。思考が上滑りしている。
「いつか帰ってこなくなりそうで怖い」
「え」
ええと、何を言えばいいんだろう。
「あの、」
「いいよ、別に」
立ち上がりかけた佳主馬くんは、去り際に僕の体をぎゅっと抱きしめた。
お風呂に入っていなかったから、もしかしたら臭うんじゃないかと腰が引ける。
それを許さずに、ぎゅうぎゅうと苦しいくらいにされて、ぐえ、と蛙のつぶれたような声まで出て、そうしたら、佳主馬くんはようやく僕を解放してくれた。
「ぐえっ、って」
色気ないね、と耐えきれないようにくすくす笑っている。
「あるわけないじゃない」
「たまにあるよ」
「からかわないでよ。佳主馬くんのほうが色気あるよ」
「そう?」
そんなふうにごまかして、彼はキッチンへ去ってゆく。しばらくしたらきっといい匂いが漂ってくるんだろうなあと思いながら、僕は幸せだと思った。

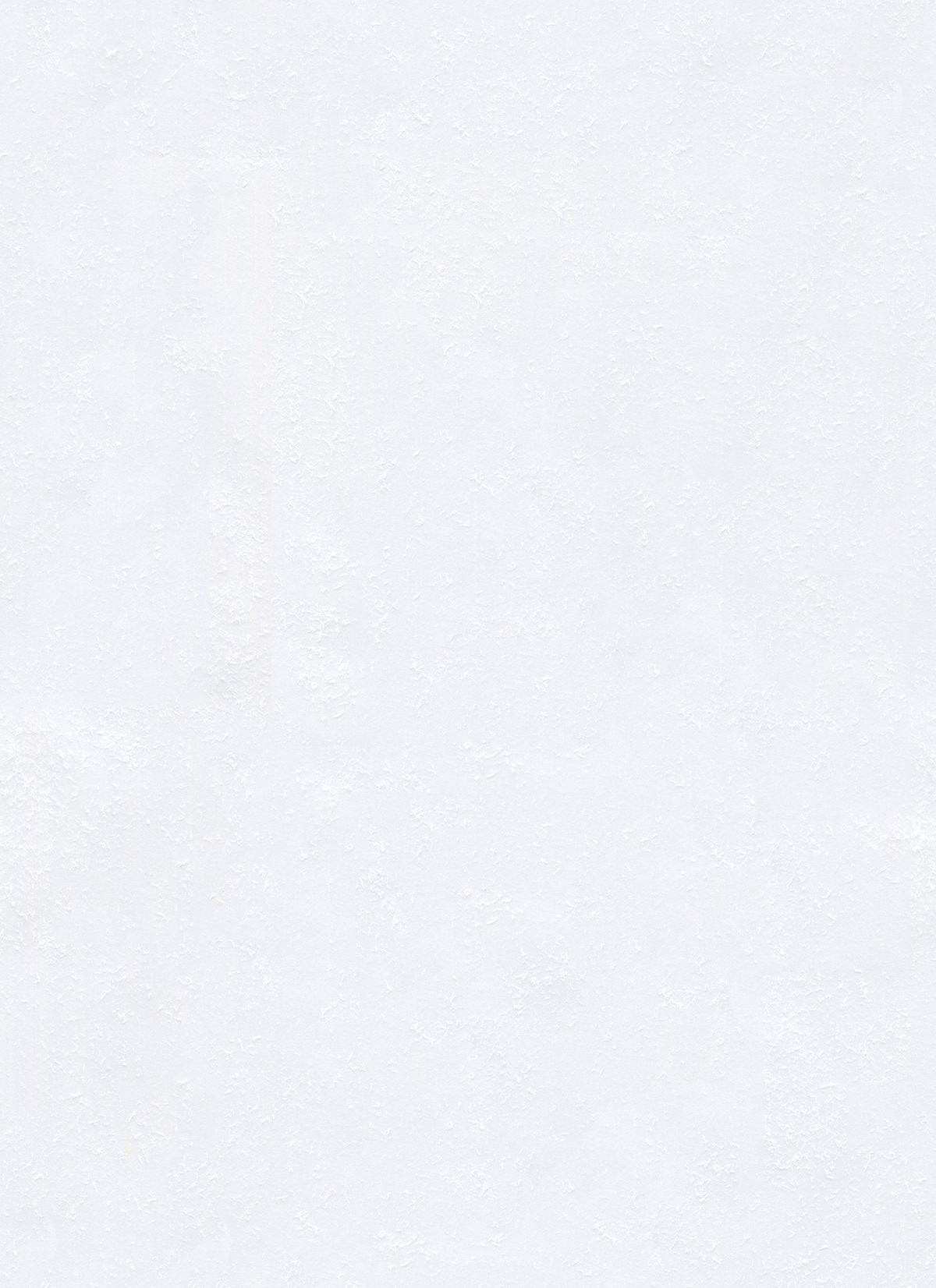
コメントを残す