「なあ、ハロ」
ロックオンがそれを思いついたのは、ただ単に暇だったからという、それ以上でもそれ以下でもない理由からだった。
暇だなんて、例えばティエリアを前にして言えば盛大に顔をしかめられ、それじゃあトレーニングでもしたらどうですかと苦言をくれるに違いない。刹那だったら、そうかと首肯されるだけで終わるだろう。アレルヤはどうか。内気な彼は困ったような微妙な表情で頷いてはくれるだろうが、かといって暇つぶしを提案してくれるところまでは期待できない。
マイスター相手ではどうやっても暇をつぶせそうになかったため、それでロックオンは、自室で一人オレンジの相棒と向き合うことにしたのだ。
赤色LEDがロックオンの声に反応して二度三度明滅する。呼びかけに応じて首をかしげる姿はまるでインコかオウムみたいだな、と思った。この高性能なAIを搭載したロボットは、本当ならばもっと充実した応答だって返せるはずなのに、まるで愛玩動物のような曖昧なしぐさと、子供のような片言しか返さない。これを作った人は何を考えていたのだろうと、詮ないことに思いを巡らせる。だからというわけではなかった。もう一度言うが、ただ単に暇人の思いつきである。
「お前、歌とか歌えるか?」
「ウタ」
「そう、歌」
ピコピコと、せわしなくLEDが点滅しているのは、ハロがデータベースにアクセスしている証拠だ。二秒も待たず、回答が返ってきた。
「データナシ。データナシ」
「そっか」
ふむ、と顎に手をやったロックオンは、不思議そうな顔をしてこちらを見上げている——ように見えるだけなのだが——ロボット相手に、にこりと笑って見せた。
*
「なあ、ハロ」
ロックオンがそれを思いついたのは、ただ単に暇だったからという、それ以上でもそれ以下でもない理由からだった。
年下の同僚たちは話相手にはなりそうもない。彼らがロックオンとのコミュニケーションを避けているようでもあるし、もともとロックオン自身が、彼らと慣れ合うことを避けていた。仕事の上で最低限の付き合いは必要不可欠だとは思っている。だがそれだけだ。オフに関しては、彼らに干渉することも、また干渉されることも望まない。
しかしあまりにも手持無沙汰であったため、ロックオンは仕方なく、「相棒」たるオレンジのAIを相手にすることにした。メカニック曰く、このAIとの対話履歴が彼の「仕事」にも影響を及ぼすということなので。
だから、それは暇つぶしの思いつきだった。
「お前、歌とか歌えるか」
「ウタ」
オウム返しに繰り返された合成音声は、二三秒のタイムラグの後に明快な答えを返した。
「ウタエル。ウタエル」
「へえ」
意外でもあり、しかしこの高性能なロボットならばありえないこともない回答だ。何のためにそんな機能が搭載されているのかを突き詰めると、疑問が残るが。
「歌ってみろよ」
「ハロ、ウタウタウ。チョットマテ」
尊大な物言いを残して言葉を切ったかと思えば、AIはやがて、歌いだした。
Daisy, Daisy
Give me your answer do
I’m half crazy all for the love of you
It won’t be a stylish marriage
I can’t afford a carriage
But you’ll look sweet upon the seat
Of a bicycle built for two
「……へたくそ」
「ハロ、ヘタジャナイ!」
反論されたが、どう聞いてもへたくそな歌だった。合成音で音程をなぞっただけの、発音も不完全な歌声。機械にプリセットするには些か程度の低い、つまらない歌声だった。
歌だってそうだ。幸い、歌詞はロックオンの母国語だったために聞き取れたが、なぜこの曲なのか。流行りの曲でもなければ有名な曲でもない。若者の不器用な恋を歌った、童話のような、真新しいところのない歌だった。
「なんでその歌なんだ?」
「シラナイ。シラナイ」
それもそうか。歌を歌わせるようにしたのはたぶんこのロボットの開発者であって、機械が望んでこの曲を歌えるようになったわけではないのだから。
それにしても、なぜこのロボットに歌を教えたのだろう。戦闘支援とメンテナンスを主な機能とするロボットが、歌を歌う必要はないだろうに。
「……もう一度、歌ってくれないか」
「マカセロ。マカセロ」
へたくそでつまらない歌を、それなのにロックオンはもう一度リクエストした。
やがて、合成音が歌い出す。

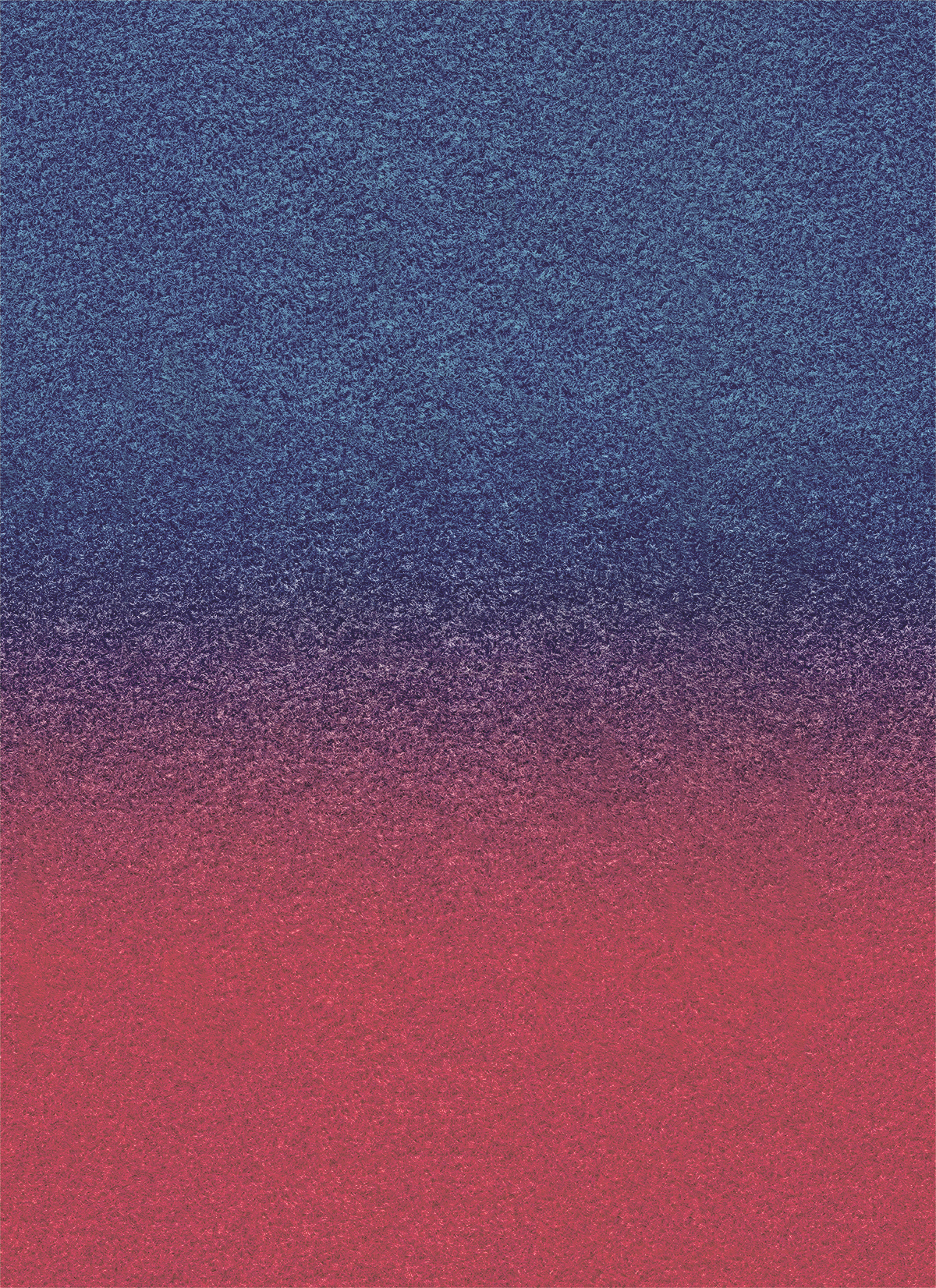
コメントを残す