(2期1話後)
僕を独房に押し込めた青年は、出口に手を掛けてふと立ち止まった。
彼はもう僕などなんとも思っていないのだろうという気がしていたから、そのことが僕には意外だった。彼が意識を向けるだけの何かが、僕にはまだ残っているのだろうか。完全に相容れないところに立っているのだと、思ったのだけれど。
彼は僕に背を向けたまま、呟くように言った。
「前にも、銃口を向けられたことがある」
当然だろう、という思いが僕の心を支配した。彼は世界を敵に回したテロリストだ。何度も銃を、ナイフを、敵意を向けられて、それをあんな風に冷たい目でいなしてきたに違いなかった。
彼はふと半身を翻し、僕の目を見た。蛍光灯に照らされて見えたのは、ひどく冷たい表情だった。
四年前、あのマンションで顔を合わせていた当時はただ人付き合いの悪い少年だと思っていた。しかしすべてを知ってしまった今ではその無表情すら不気味で意味深なものに見える。テロリストはきっと、みんなこんな顔をしているだろう。人間を殺すことをなんとも思わない、感情の欠けた顔。銃口を向けられることに、慣れた顔。
僕は彼の言わんとするところを理解できずに、ただ無言で彼の目を睨み返していた。
「その男も俺を詰問した。家族を返せと。返せないなら死ねと」
「……」
「あいつは撃った」
僕は撃たなかった。心の中で即座に反論する。いいや、撃てなかったのか。しかしどちらでもいい。僕は撃たなかった。それこそが絶対の真実である。たとえ怯懦の所以だとしても、僕は引き金を引く勇気が僕に存在しなかったことを感謝する。
「何が言いたい」
まるで獣のような唸り声が、僕の喉の奥から捻り出た。僕は彼が言う男なんて知らないし、その男自身でもない。
「僕も撃ったほうがよかったって?」
睨みつけた先で、彼のビーダマのように色のない瞳が、一瞬だけかすかに揺らいだ気がした。僕の声が彼の瞳を揺らしたのならと考え、僕は笑いだしたい気分になった。テロリストが何を迷うというのだろう。おそらくは気のせいだ。そうに違いない。
そして彼は、やっぱりどこにも動揺など見られない無表情で僕を見下ろした。
「彼の銃口は、そんなにぶれなかった」
「悪かったな、ヘタクソで」
嫌味だとしたらとてつもなく場違いだ。彼はまったくの真顔でもう一度だけ口を開いた。
「悪いとは言っていない」
彼はもう何も言わずに、強く床を蹴り去って行った。目の前で扉が閉まり、小さな電子音がロックを知らせる。
僕は確かに、引き金を引けない臆病さを、人を殺すことのできない弱さを喜んでいたはずだった。その一方で、これは自分の勇気のなさに対する詭弁なのかもしれないと考える僕もいる。
僕は選択を迫られているのかもしれなかった。今はまだ漠然としかわからないが、何か、とてつもなく大きな選択を。

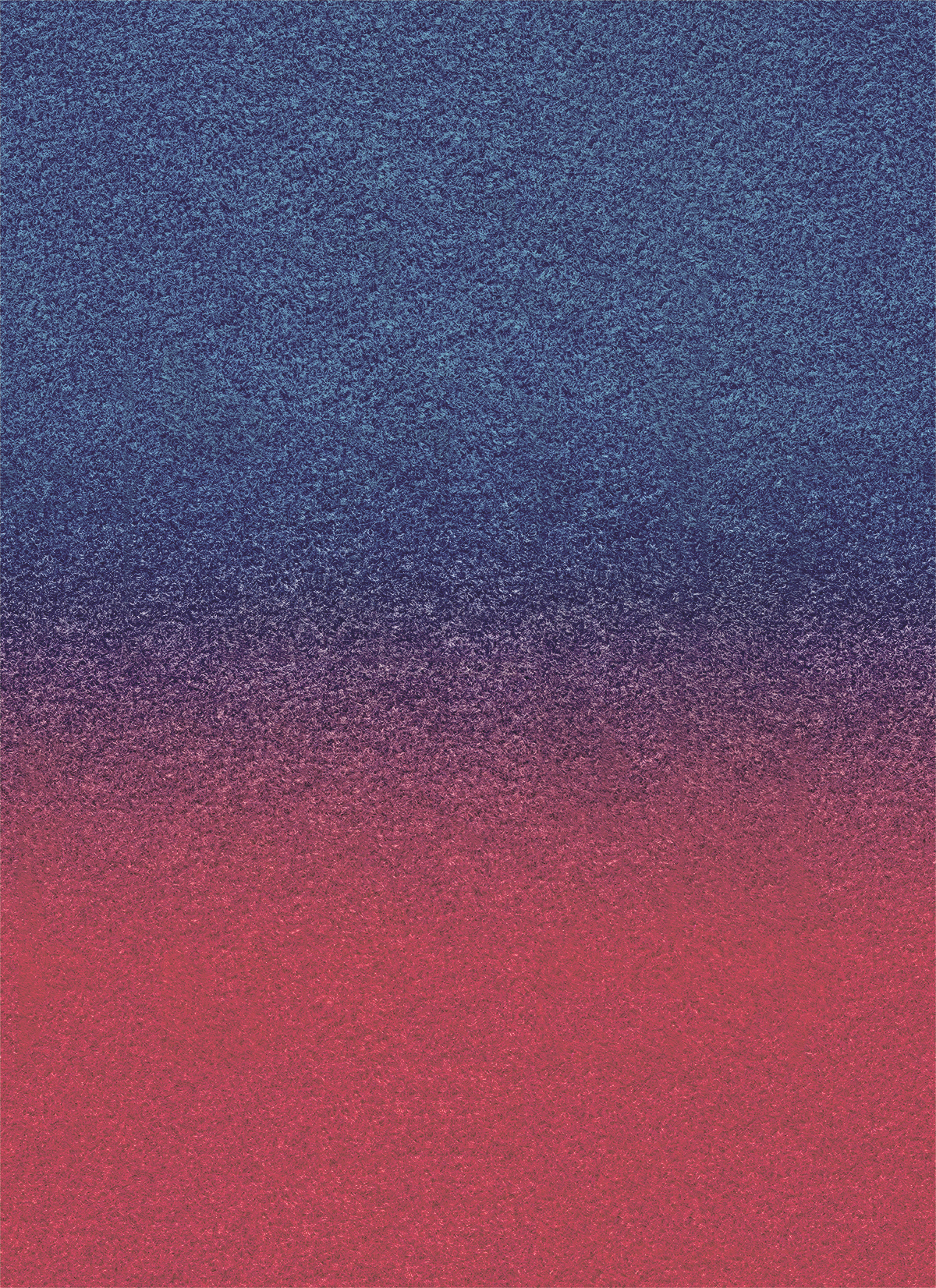
コメントを残す