ロマニがまた何かやっている。誰もいない深夜の管制室、その片隅。時間に関係なく一定の輝度に保たれた照明の下、パーティションで区切られたとある一角のその向こうから、何かモノを持ち上げて下ろすような、あるいは積んであったモノが崩れるような、そういう雑然とした音がしている。
「なにやってんのー?」
「あ、ダ・ヴィンチちゃん。爪切り知らない?」
「爪切りぃ?」
パーティションの影からひょいと頭だけだして、またすぐ引っ込む。珊瑚色のしっぽがひょんと追いかけて消えた。ガタガタ、ばさばさ、また音がする。私室に帰るのも面倒だとあれもこれも持ち込んだせいで非常に見苦しくなったその一角は、スタッフの間で「ドクターの巣」と呼ばれている。そのあまりの見苦しさに誰かが目隠しにパーティションを置いたのが却って良くなかったのか。見えなければいいだろうとその奥はますます収集がつかないことになっているらしい。ダ・ヴィンチはそのあたりをできるだけ目に入れないようにしている。理由は簡単、美しくないからだ。
「君、爪切りまでこっちに持ち込んでたの? 医務室じゃなくて?」
「あっちはあっちで備品があるけど……そうじゃなくて、ボクの私物。絶対持ってきたはずなんだけどなあ。ええと、最後に使ったのは――」
ぶつぶつとつぶやきながら徘徊する彼を尻目に、ダ・ヴィンチはシヴァ偏向角制御装置――有り体に言えば、監視カメラのモニター列――の管制官用チェアを適当に引き出して腰掛けた。ぐりんぐりんと手持ち無沙汰にチェアを回して遊んでいると、キャスターが不意に転がって慣性がかかる。その結果、バランスを崩して乗り出した肘が制御パネルの上に置いてあった何かを弾き飛ばした。
「ん?」
「あ! そういやベクターに貸したな、昨日。あいつならすぐ返してくれるはずだけど……ああ、そうだ。思い出してきたぞ。その後ハイネケンも使ってた。やれやれ、どうせその辺に置きっぱなしになってるはず……おお! ダ・ヴィンチちゃんそれそれ! それだよ!」
管制スタッフの名を挙げながら巣から出てきたロマニに、床から拾い上げたそれをよく見えるようにぷらぷら振ってみせると、彼は歓声と共に両手を上げてやってきた。この男本当に三十路過ぎかと疑いたくなる。
「いやー、爪って切りたいって思ったらすぐに切らないと気が済まなくない? 気になっちゃってさあ」
「私は英霊だからね。爪は伸びないよ」
「そっか、そうだね。それで……うん。…………ええと。あ、もしかしてお礼言わないから? ありがとう、見つけてくれて」
こちらに手のひらを差し出して、しかし一向にそこに載せられることのない目当ての品に、彼はしびれを切らして手を伸ばしてくる。それをひょいと避け、反対側の手に移してみる。銀色の、なんてことない爪切りだ。
「どういたしまして。別にそういう含みがあって君にこれを返さないわけではないけどね」
「じゃあどういう理由で?」
「そうだな……うん。じゃあこうしよう。私が君の爪を切ってあげる」
そういった時のロマニの表情と言ったら、間抜け面が五割増しでロバかカピバラか、ウーパールーパーみたいだった。
「いや。いやいや。いいって、自分で切れるから」
「君の能力を疑っているわけではない。私はただ自分の知的好奇心を満たしたいだけだよ。協力したまえ」
「またとんだ暇つぶしもあったものだね!? ボクの爪を切るという行為が君の頭脳を満足させるとは到底思えないので却下。はやくそれ返しなさい」
「かーえーしーまーせーんー。ダ・ヴィンチちゃんはこうと決めたことは最後までやり通すのです。はい、おとなしくここ座る。手ぇ出す。はい、痛くないですよー」
「あーあー、もう……君の気まぐれにも困ったものだね」
「この天才ダ・ヴィンチちゃん自らが爪の手入をしてやろうと言っているのに! こんなチャンス二度とないよー。出血大サービスだよー?」
これ以上この不毛なやり取りを続けても何の解決にも至らないと悟ったらしい。彼はひとつ大げさなため息を付いて椅子に腰掛けた。
「よろしい。さあ、手を」
「あー。痛くしないでね?」
「目を潤ませて角度はもう十五度上げて。声もだめだめっていうかやる気ある? 十五点」
「すみませんね」
下らない漫才を続けながら、しかし素直に差し出された彼の左手を取る。まずは白い手袋をそっと外してやった。隣でロマニが、おや、とでも言いたげに眉を上げる。
「意外に丁寧だってことだろう? そりゃ、私だって医療従事者の手を乱暴に扱うようなことはしないさ」
「何も言ってないけどね」
そうする間に布地の下から出てきた手は、まさか白魚のようなと形容するつもりは毛頭なかったが、それにしても予想以上に荒れていた。薬品を使うせいもあるだろうが、一番の理由はは不摂生だろう。甲の薄い皮膚の下には治りきらない内出血の痕が広がっている。点滴の名残だろう。栄養剤程度のことだろうが、治らないうちにまた入れるので見た目はあまりよろしくない。これが彼が手袋を外さない理由の一つだ。もう一つの理由は、このやたら冷たい温度だろうか。骨ばった男の手であるのに、まるで冷え性の女のように冷えている。カルデア館内はどこにいようと人が快と感じる温度に保たれているというのに、だ。睡眠不足、多忙を理由にした食生活の乱れ。精神的負担も大きいはずだ。
馬鹿だな、とは思うが、ダ・ヴィンチはなにも言わなかった。今までも、これからも。今この時も、別になにも言う気はない。
ダ・ヴィンチは、そうとは見えないかもしれないが、このロマニ・アーキマンという男のことを認めている。非凡でなく、英雄でなく、悪でない。ただの人であるところの彼を、人類史に名を残した天才たる自分は認めていた。それは信頼ではない。じっさい、彼のやりかたは危なっかしく、身の丈を考えない無茶ばかりだ。とてもじゃないが、安心して背中を預けられる相手ではない。だが、ダ・ヴィンチにとってそんなのは些細な問題だった。天才は天才であるがゆえに、他者の中途半端な手助けなど必要としない。カルデアにはロマニのサポートが必要不可欠かもしれないが、ダ・ヴィンチ個人にはどうでもいいことだ。
ダ・ヴィンチが認めるというのは、彼の生き方を否定しないということだ。彼が行うのがどんな無茶無謀であっても、彼がたくさんの可能性の中からそれを選択したという事実を尊重するということだ。彼が眠らず、食わず、休まずで働こうとも、その結果人類を救えた
として彼自身が息絶えるようなことがあっても、彼が選んだことならば、レオナルド・ダ・ヴィンチはそれを認める。全部が終わったあとで、やっぱり馬鹿だなあとは、思うかもしれないけれど。
ダ・ヴィンチがなにも言わないので、ロマニも僅かに張っていた肩の力をとうとうすべて抜いてしまったようだった。低反発素材の背もたれに全身を預けて脱力している。
よろしい。
――と今度は声には出さずに、ダ・ヴィンチは彼の爪の先を慎重に摘み始めた。

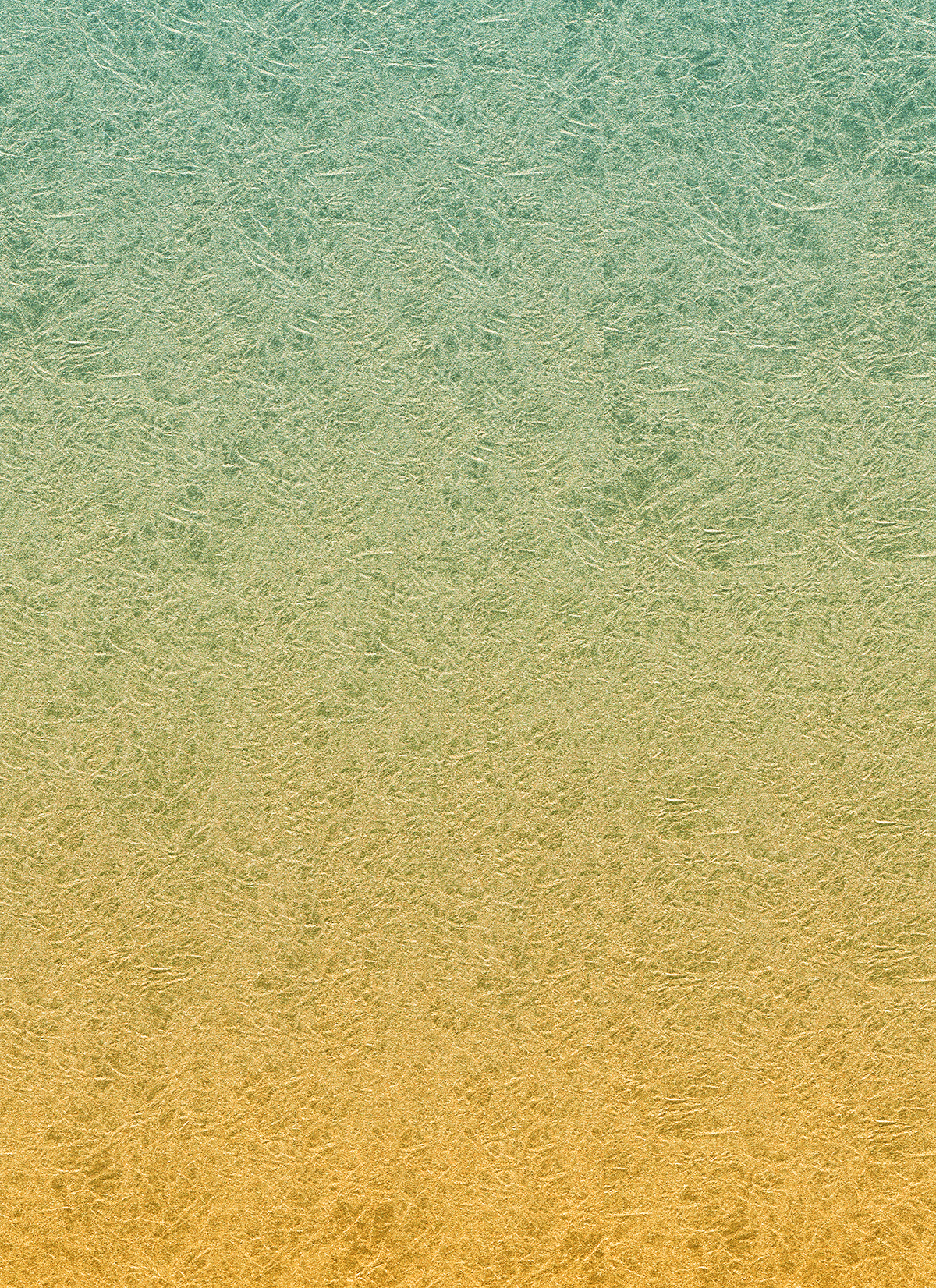
コメントを残す