――薄暗い管制室。壁面を埋めるように設置された大小様々な大きさのモニタとLEDを明滅させる計算機。コンソールはありきたりなキーボードタイプの入力装置にタッチパネル、ポインティングデバイスが並ぶ。空冷ファンの回る羽虫のような耳障りな音が断続的に繰り返す室内に、外部スピーカーから少女の声。
『正確な時刻は不明ですが、日も暮れましたので、ジャンヌはここで野営するようです。こちらも本日の作戦行動は終了しますが、よろしいでしょうか、ドクター』
「霊子転移(レイシフト)時点から8時間24分経過。だいたい午後7時過ぎといったところかな。もちろん、しっかり体を休めてくれたまえ。前回の冬木の時はたまたま短期間の探索で済んだが、今回からは長丁場になるだろうね。休息もまた重要な任務だ」
『了解です。今のところ周辺に敵はいないようですが――』
「引き続きこちらで索敵するから大丈夫。もし何かあったら通信を入れるから、それまではゆっくりお休み」
モニターの向こう側から通信終了の返答を待って切断する。メインモニタが落ちると、室内は途端薄暗くなった。脈拍三つぶん、息が詰まって、それから肺の中の空気をすべて吐き出すような細く長い溜息が漏れる。肩と首を軽く回し、足を組み替える。コンソールから生命反応探知の閾値を念のためやや低めに設定しなおし、結果を音声出力に切り替え。ソナーとも、バイタルとも似た電子音がスピーカーから聞こえてきたのを確認して、チェアを横に九十度回転。十段階に角度調節可能な背もたれを百四十度の位置まで思い切り倒すと、肩の位置がずるずると下がっていく。オットマンみたいな気の利いたものはないから、書類の乗るサイドデスクに行儀悪く足をのせる。そしてようやく、ロマニ・アーキマンは己に目を閉じることを許可した。
メインモニタに映るリアルタイム映像を始め、広域地図、拡大地図が表示されたサブモニタ、それぞれに乗算される生体反応および霊子反応のサーモグラフィ、マシュ・キリエライトとそのマスターたる少女のバイタルデータを示すタブレット端末まで。ありとあらゆるモニタと計器から情報を集めるために酷使していた目は、目を閉じても瞼の裏側にその幻覚を見ている。やがて眩暈すらしてきたので、目頭を強く抑えることで強制的にシャットダウンした。
目を閉じると、管制室に響く電子音が余計大きく聞こえるようだった。時折交じる人工音声による「異常なし」の報告が耳に刺さる。しかし、逆に言えばそれだけだ。室内には彼しかいないのだから当然だった。
本来チームで当たるはずの霊子転移(レイシフト)管制業務だが、レフ・ライノールの造反によりスタッフ数を二十名足らずまで数を落とした人理継続保障機関カルデアでは現在ロマニ以外に管制室への入室権限を持つ人員がいない。なにせカルデアの初任務を狙われたせいで、マスター候補生のみならず優秀なバックアップスタッフまで、死亡かそれに近い大怪我を負っている。凍結延命措置まで取らずに済んだ数名も、しばらくは業務復帰は不可能。それまでの間、どうにかロマニ一人で回すしかない。
目頭を抑え続けていた右手が、気だるげに移動する。そろそろと顔を這ったそれは、今度は頬のあたりをもみほぐすようにさすった。心なし、今も笑みの形に引きつっているような気がしたので。
ピラミッドの天辺を爆風に吹き飛ばされたカルデアという組織のなかで、何故か現状最上位階級として残ってしまったロマニだが、本来の彼は医師である。時には患者とのカウンセリングも受け持つ彼は、こういった非常時にこそ笑いと笑顔が人の心を支えるのだと知識上も経験上もよく知っていた。現にロマニが真顔で物思いに耽る顔をすると、マシュ・キリエライトのバイタルサインは不安定な傾向を示す。彼個人のキャラクターから言って、なにもすべて演技をしているわけではないが、ことさら「らしく」振る舞う必要性はあった。
気の済むまで顔面をマッサージし、やがて両手を組み合わせ、上に伸びる。くぅ、と喉の奥が鳴った。
――のを、まるで見計らったかのように。
「君、それじゃ取れる疲れも取れないだろうに」
「わひっ!?」
誰も居ないはずの室内に唐突に第三者の声が響き、驚いた彼はバランスを崩してチェアから転げ落ちた。それは見事に。漫画みたいな擬音付きで転がった彼は、したたかに打った腰をさすりさすり、涙目で声の主を見上げるしかできなかった。IDと生体認証の必要なこの室内に入ってこれる人物のことなど考えるまでもなくわかっているし、そしてその人物に対して文句を言うだとか説教をするだとかがどれだけ無意味なことかも同様。だからロマニはお願いという形で苦言を呈した。
「頼むから人の部屋に入るときはノックしようね、マナーとして」
ダ・ヴィンチちゃん。そう呼びかけた相手は、いつの間にかロマニが先ほどまで座っていたリクライニングチェアに君主のごとき優雅さで腰掛け、床にへたり込んだままの彼を見下ろしている。肘掛けに付いた肘で顎を支え、彼――彼女?――は皮肉に笑った。
「休息は重要なんじゃなかったのかい?」
「……一体いつからいたの、君」
「まさかハードワークは美徳だって信じてたりするのかい? 極東の島国の出身だったっけ?」
「全然会話する気ないよね」
「最初に質問に質問で返したのはきみのほうだよ、ドクター。空き部屋でサボるのが日課ってのはポーズかなにか? 授業中は寝てばっかりの癖にテスト前に家で猛勉強して上位に食い込んで、さも余裕を演出するタイプの人間っているよねえ。自己満足な上だいたいそういう人間って友達いないんだ、これが」
「ねえ謝るからそれ以上抉らないでダ・ヴィンチちゃん」
げんなりとしたロマニの態度に、彼は足を組み替え反対の腕で頬杖を付き直す。
「きみ、このミッションの間じゅう、横にもならないつもりか?」
「……今回だけさ。もう一週間もすれば何人か怪我から復帰するスタッフが出てくる。それまでの間だけだよ。ねえ、君もわかってるだろ。緊急事態なんだ」
「ふうん、一週間ねえ」
英霊は、かの名画のごとく微笑み、やがて気まぐれのようにロマニに向けて手を差し伸ばした。何らかの和解が成ったと思ったロマニは、遠慮なくその手を取り――そしてひどく強引に引き上げられる。
「ちょ!?」
その勢いのまま、手袋と白衣の間の隙間に指が突っ込まれ、乱暴に捲り上げられた。普段日に当たらない肌の、ことさら皮膚の薄いところが、英霊の目前に晒される。たくし上げられた袖の影、脱脂綿の張り付いたテープが一箇所、二箇所。三箇所。
「ふうん?」
すうっと、深海の色を宿した瞳が細まる。あえてその口元にはあえかな微笑みが残されているのが恐ろしい。
「た、ただの栄養剤だから! 間違っても怪しいオクスリなんかじゃ――」
「キミはバカだけど頭は悪くない。アンフェタミン系覚醒剤は常用できないことくらい、まだ判断できてるだろうね?」
その声はまさに海の底のように冷たかった。
「……栄養剤だよ、本当に!」
それを、ロマニはまるでなにも気が付かない愚か者のふりをして、染み付いた半笑いで受け流そうとする。
ふん、と鼻息一つ、ダ・ヴィンチは掴んだ腕を解放した。
「まあ、よろしい」
まったくよろしくなさそうな声音で言い切ると、彼はそのままリクライニングチェアをいたずらに回転させる。くるり、くるりと、まるで子どもが遊ぶようにして回っているのを、まあ見ているのは別にいいのだが、そのままではロマニはいつまでたっても立ち尽くすしかない。
「あの、よければですね、椅子を――」
ロマニが言い切る前に、彼は椅子をピタリと止めて尊大に足を組む。ついでに腕も組んだ。先ほどとは違い今はロマニが彼を見下ろす位置にいるというのに、相変わらず見下されているようだ。
「愚か者。頭をつかえー頭を! なんで私がここに来たかわかってないのか?」
「遊びに来たんじゃないの?」
「手伝いにきたの! ちみっ子達に現場で命張らせてるくせに後方の安全なところで指示と支援しかできない自分に勝手に無力感感じて自罰的になった上ろくに休憩も取らずに最終的に自滅してみんなに迷惑かけそうなどっかのドクターを休ませるために! はい、まわれーみぎ。駆け足!」
「はいっ!? ていうかひどい言われよう!」
命令通りに駆け足を始めてしまうくらいには、図星を突かれて動揺したらしい。入り口まで数歩のところで、後ろから再度声がかかる。
「給湯室でお湯沸いてるはずだから、一服してきなさい。お茶うけも出しといたから」
「え?」
「甘いもんでも食べて、少し休みなさい。それまでここは見ていてあげよう。『休息もまた重要な任務』さ、ドクター」
「ああもう! それはどうもありがとう!!」
からかうような声にいい加減に恥ずかしくなった彼は、管制室を出るまで振り向かなかった。流石に顔が火照っているのが、自分でもわかったので。
というわけで、ご丁寧に用意されていた「ごま饅頭」までおいしく戴いたロマニが、その後も過不足なく支援業務に就くことができたのはご存知の通りである。あの破天荒な英霊についてやや評価を改めたロマニが、そのすぐ後、デミサーヴァントの少女からそっくりその分評価を下げられることになるのも、また一つの予定調和であったが。

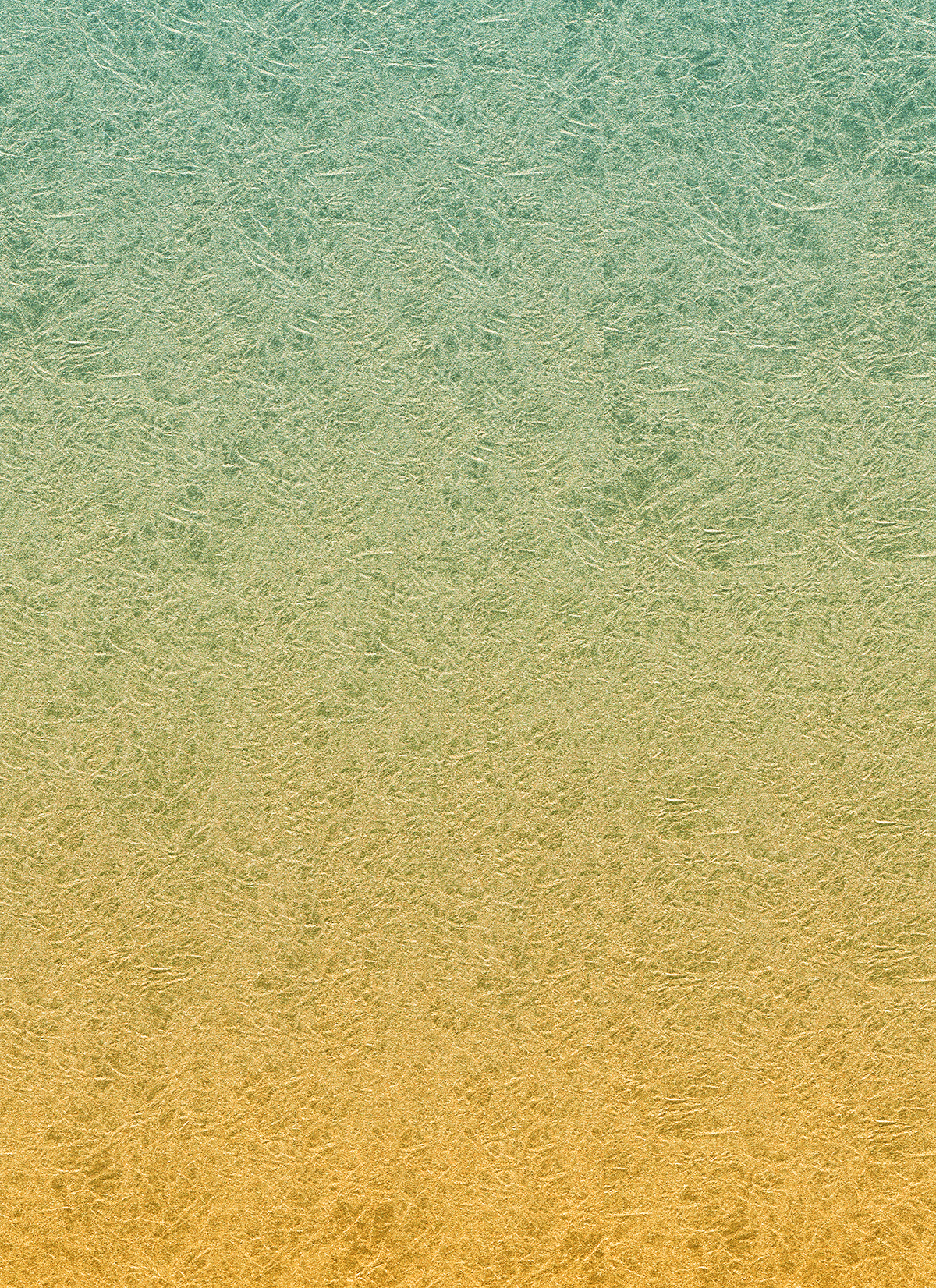
コメントを残す