頭が重い。
目は開いているはずなのに視界がまともに像を結ばない。
ここは――どこだ?
どこかのホテルの一室だということは雰囲気でわかった。大会のためにとったホテルからはいくつもランクが下がる、安ホテル。洗いざらしのシーツは清潔そうではあるが高級感は感じられない。起き上がろうと手をつくと軋むベッドは、サイズだけはやたら大きいが安物だ。ほら、今だってやたら片側が傾いている。晴れない頭を振る。ぶれた視界に、映る銀色。
銀色?
「ヴィクトル!?」
なんで今まで気が付かなかったのか。すぐ隣に人形のように横たわるもう一人の体。だからベッドが傾いていたのだ。もっと早く気づいたってよかった。
「、あっ」
だんだんと思い出す。
夕食をレストランで摂った帰りだった。
秋の終わりのロシア。とは言っても、もう冬みたいなものだ。シーズン初めの国際大会に参加するため、調整期間も含めて十日前のモスクワ入り。ヴィクトルにとってはホームみたいなもので、調整のための場所も融通が利くからと余裕を持った日程にした。夕食に入ったレストランはちょっと暖房が効きすぎていて、初日の今日くらいはと許されて軽く一杯だけ飲んだワインが変に回ったようで。少し外の風に当たりたいと言って歩き出した勇利のことを、ヴィクトルは「日本みたいな治安じゃないんだから」と窘めたが、ほんの一、二分、街灯もあるのだからと押し通した。
ちゃんと聞いておけばよかった。彼の言い分は正しかったのだ。
どこにでもありそうな乗用車がするすると道端に止まって、勇利の目の先でドアが開いた。男が一人で降りてきたところまでは覚えている。どんと体を突き飛ばされるような衝撃を感じて――気がついたらこうなっていた。
少し後を歩いていたヴィクトルが常に聞かないようなトーンで勇利を呼んだ、その声が脳裏にこびりついている。悲鳴のような、声。
彼だけでも、逃げてくれればよかったのに。
着ていた黒のコートは脱がされて、ワインレッドのセーターと黒のスラックス姿のヴィクトル。顔色は元々が色白のせいで白を通り越して真っ青に見える。
こんな顔色で、無理に起こさないほうがいいのではないか。頭を打っていたら、動かすのはかえってまずい。そう逡巡しているうちに、彼は自ずから瞳を開けた。
灰色のまつげが揺れて、その下から氷色の瞳が覗く。おそらく勇利と同様に茫洋とした視界が見えているはずだ。焦点がやがてひとつに結ばれてゆく様まで手に取るようにわかり、そんな場合ではないとわかっているのに見つめてしまう。
「ヴィクトル?」
その視線を引きたくて名を呼ぶと、彼ははっと息を飲んでその瞳に勇利の姿を映した。とたん、わずかながらにも安堵するように瞳が解ける。
「ユーリ」
片腕をついて体を起こす彼を手伝ってやり、二人はベッドの上で向き合う。畳の生活が長かったせいか、こうやって並んで座ることにも慣れてしまった。
「怪我はしていないね?」
彼は勇利の姿を頭の天辺からつま先まで視界に収めて確かめた。コーチとしてはなによりそれが気になるに決まっている。これからが世界の舞台だというのに、こんなところで躓いていては困るのだ。
「はい、どこも。そういえば、体を突き飛ばされたと思ったんですけど……」
「多分スタンガンだよ。衝撃は強かっただろうけど、実際には体を打ちつけるようなことにはなってなかった」
「一体……何が?」
その問いに答えるために、彼は一度ベッドから降り、扉を確認した。部屋の中に扉は二つ。片方はおそらくバスルームに続くもので、もう一つが廊下への出口だ。バスルームは開いたが、肝心のもう一つは開かなかった。ノブが回らないことを確かめると今度は窓際に向かう。しっかりと閉じられていた分厚いカーテンを払うと、街の灯が見えた。
「そんなに離れてないな」
呟くような声。でも英語ということは、勇利に聞かせる気があるということだ。それから彼はひとしきり部屋の中を歩き回ると再びベッドへと戻ってきて縁に腰掛けた。
「わかると思うけど、誘拐されたんだ。扉も外から鍵がかけられていて開かない。カバンもないし、スマホも取り上げられてる」
「えっ!? わっ、ホントだ……」
慌てて自分のポケットを確認する。着ていたダウンジャケットはヴィクトル同様脱がされていて見当たらない。スウェット地のパーカーと着古しのジーンズに乱れはないが、後ポケットに突っ込んでいたはずの携帯は抜き去られている。
薄々感じていた不安を詳らかにされて、動揺しないわけがなかった。どうして? なぜ? 何の理由で? 同じ問いが頭の中をぐるぐると回る。なにより十日先とは言え、試合前なのだ。それを意識しないわけにはいかなかった。
「ふつう誘拐というと、金目当てと考えるのが妥当だけれど、――ところで変なことを聞くけどユーリ、キミの家はお金持ちなの?」
「えっ、いえ、そんな。困窮してるってほどじゃないですけど、見ての通りで」
「だよね。だったら、ISUに直接? そんな馬鹿な、大げさにしてロシア政府まで敵にしたら割に合うはずがない……」
彼は人差し指を唇に置いて顎を触りながら、頭を整理しているようだった。
「どういうことです?」
「金目当てだったら、俺まで浚ったら意味ないと思わない? 世界チャンピオンの懐を目当てにしてるんじゃなきゃキミの実家かと思ったけど――」
「み、身代金? 無理無理無理、うちには無理です!」
身代金なんて英語、使ったことがない。あまりにも非現実的な単語の連続に、処理が追いつかない。
「つまり、お金じゃないってことさ。もう一つの可能性といったら、大会絡みだろうけど……」
あんまり想像したくないな。
I don’t wanna imagine.
その言葉の意味を問い返す前に、閉じられていたはずの扉が、開いた。
入ってきたのはガラの悪そうな男が三人ばかり。
黒服に目出し帽でもしていればそれっぽかったが、そんなことをしたら逆に目立つのだろう。ジャージ姿で斜に構えた態度が鼻につく。白人の年齢は日本人にはわかりづらいが、おそらくどれも二十代半ばくらいの男たち。背はヴィクトルと同じくらい高いが、横幅は彼の倍くらいありそうだった。何のために鍛えたのだか、腕は無駄に太く、その割に腹がたるんでいる。頬に傷があったり、眉がなかったりという違いは多少あったが、ガラが悪いという以外の印象が感じられない。これこそ無個性というのだろう。
「お目覚めか」
そのうちのどれかが、勇利には理解出来ない言語で何かを言った。ロシア人同士なのだから、ロシア語なのだろう。勇利の視線の先で、ヴィクトルは無表情でいる。
「何のつもりだ」
「わかってんだろうが、美人さん」
「残念だけど、心当たりが多くって」
彼はおどけるように肩をすくめてみせる。しかし変わらない表情からして、楽しい話題ではなさそうだった。
「こういや分かるか、祖国ロシアの裏切り者め。お前がこの地で異国人を勝たせるのが気に食わないって連中が、うじゃうじゃいるんだ。悔いるなら自分の軽率な選択を悔いな」
「ふうん。なるほど。それで? 君たちの雇い主は俺たちを誘拐して何をしてこいって?」
「……さっきからこっちが大人しいからって、自分の立場がわかってねえんじゃねえか? 舐めた口ばっかききやがって」
「そう聞こえたなら悪かったよ。元からこうだから変えられなくてね」
「……」
ヴィクトルがなんと言って相手を挑発したのか。後ろにいたもう一人が耐えかねたように腰からバタフライナイフを取り出し、バネを跳ね上げて刃を見せつける。
それに怖気づいたのは今まで蚊帳の外だった勇利のほうだ。ひっ、と声にならない悲鳴を上げて、思わずヴィクトルの服の袖を掴む。頼むから、あんまり挑発しないでくれ、という意図を込めて。
その掴まれた部分を見下ろして、彼はほら、とでも言いたげに男たちに笑いかけた。そう、笑ったのだ。
「怯えてるだろ。フィギュアスケート選手は繊細なんだ。メンタルだって、フィジカルだって、ちょっとのことですぐバランスを崩して跳べなくなる」
彼は勇利の手を軽く払って立ち上がった。直ぐ側に刃物があるというのに、そんなの見えていないような素振りで、ボス格の男に近づいてゆく。
今まで頑なに強張っていた表情はどこへ置いてきてしまったというのだろう。彼はまるでリンクの上にいるときみたいに妖艶に笑って、その繊手で男の顎に触れた。まるでいつかの勇利にしたみたいに。
「ねえ、君たちの主がなんて言ったか当ててやろうか。『犯して、辱めて、精神的に二度と立ち上がれないようにしてやれ』……。そんなとこだろ? 目に見えるところに傷なんて付けちゃあメディアにバレちゃうしね。秘密裏に処理したいなら性的暴行が一番具合がいい。それで君たちが選ばれたってわけだ――ゲイなんだろ。見ればわかるよ」
彼が流し目を送った先で、ナイフを構えていた男がそれを取り落とす。もう一方でひたすらこちらにガンをくれていた男は、怖気づいたように一歩下がった。その様子に笑みを深くすらして、彼はすぐに沈痛な表情を作った。そして次に視線が向けられるのは――勇利だ。
「残念だけど、あの子はもうだめだ。前シーズンだって、飼い犬が死んだくらいで精神的ダメージを負ってボロ負けしたんだよ。せっかく半年かけて仕上げてきたのに……それはすごく悲しいけど、でも、見てよ。あんなに震えて。あれじゃあもうだめだ。前シーズンの二の舞にしかならない」
なんでそんな目で見つめられるのかわからない。外国語でかわされる会話からは手がかり一つ得られない。それでも彼の表情がひとつ変わる度に、勇利は悪い予感に背を震わせる。
彼の冷たい目がとろりと溶けて、もう一度男を見た。
「せっかくなら楽しもうか。君たちだって、ノンケの子豚ちゃんとやるより、俺みたいなののほうが楽しいでしょ。どうせあの子は放って置いても勝手に傷ついていくんだから」
彼の言葉に、男たちがゴクリと唾を飲み込む。勇利のことなど、とうに忘れ去ったみたいに。誰が仕向けてそうなっているのか、外で見ている勇利には手に取るようにわかった。
「ロシアの英雄は誰にでも股を開くビッチって噂、本当だったのか」
「確かめてみたら? いいよ。きなよ」
心が、痛い。
それからのことを、勇利は曖昧にしか覚えていない。
男たちを誘ってベッドに横たわったヴィクトルと入れ違いにそこから追い出され、抜けた腰を引きずるように壁際まで後退った。そこでただ、目に映るもの見るとなしに見つめ、耳を通り抜ける音を聞くとなしに聞いた。
彼が婀娜めいた仕草で自ら服を脱ぎ、男たちの汚らしいものに奉仕するのを見た。ときに喉奥まで押し込まれてえずく音を聞いた。悩ましく寄せられた眉。四つん這いに這わされて前後から責められる姿。いやらしい水音。しなる背筋。高く響く嬌声。足を大きく開かされて、男の体を受け入れさせられる。両の手の指の先まで犯される。
その間、勇利は何もできなかった。
拘束すらされずに放置されていた彼には、本当はもっとできることがあったのかもしれない。
が、少しの勇気を振り絞って立ち上がろうとする度、氷のような視線が勇利をその場に縫い止める。
(動くな)
唇が、音もなくそれを伝える度、勇利の足は立ち上がる力を失った。
すべてが終わったのは、夜半を過ぎ、朝が近くなった頃だった。
散々あの白い体を貪って満足したのだろう、男たちは上機嫌なくらいで、やはり足下に転がっていた勇利のことなど見えていない様子で部屋から出ていった。
しばらく、ヴィクトルの掠れた息だけが部屋に響いていた。
立ち上がると、ベッドの上の彼がよく見えた。
白いシーツよりも更に白い肌を惜しげもなく晒して、体のあちこちには赤黒い噛み跡と強く吸われた痣が散らばっている。もうとうに麻痺してしまった嗅覚が、彼の上にばら撒かれた白濁の臭いを思い出した。
そんな散々な状態だったけれど、彼は目を開けていて、見下ろす勇利に気がつくとふと笑いかけようとして喉をつまらせて咳き込んだ。
自分を守るように体勢を変えて何度もつらそうに喉を鳴らす彼に、触れて良いものか手を上げ下げする。
「あの……大丈夫、ですか」
口をついたのは、一体なんてバカな質問だろう。大丈夫なはず、あるわけがない。
それなのに彼は笑ってみせた。
気丈に。
それくらいはわかった。
「どうってことないさ。キミが無事で良かった」
こんなことになっても、まだ彼は人の心配をしている。そのことにふつふつと湧き上がる感情があった。あの男ども、それを指示した知らない誰か、見ていることしかできなかった自分自身、それだけじゃない。
「――な、で……」
強く握りしめすぎて、爪の先が手のひらに突き刺さる。
「なんで……ッ」
彼に対して、大声で怒鳴りたかった。言いたいことがたくさんあって、ありすぎて喉で詰まったしまったみたいに何も出てこなくて。
代わりにぼろぼろと、涙が零れた。
違う。泣きたいわけじゃない。
泣いたら余計、彼を心配させるだけだから。
相変わらず言葉は出てこなかったから、首を振る。違うのだと言う風に。それが彼に伝わったかどうかは分からない。
彼は困った子を見るように笑みを苦いものに変えた。
「帰ろうか」
足を揃えて立ち上がった彼が、涙の向こうで僅かにふらついたように見えて、思わず手をのばす。それは彼の肩に触れる前に容赦なく叩き落された。
「いいよ。汚れる」
こちらの手を拒んだ彼は、やはり立っているのが辛いのだろう、数歩進んで壁に手をついてなんとか体重を支えている。
驚いたが、わからないわけではなかった。こんなことになって、これ以上他人に体を触られるのは嫌だろうと思ったから。しかし、しばらく動く気配がなかったので、流石に助けが必要だと判断する。もう一度伸ばした手、それが届くよりも前に彼の体は逃げてゆく。
「ごめん。ちょっと、」
語尾は声になっていなかった。口を抑えて、転げるようにしてバスルームに駆け込んでゆく。
「えっ――」
伸ばした手の先で乱暴に閉じられた扉。
その向こうで苦しそうな喘鳴が聞こえた。
愚かなことに、そうなるまで勇利は、彼が「大丈夫」なんだと、――あのバカな問いみたいに――心の何処かで思っていたのだ。

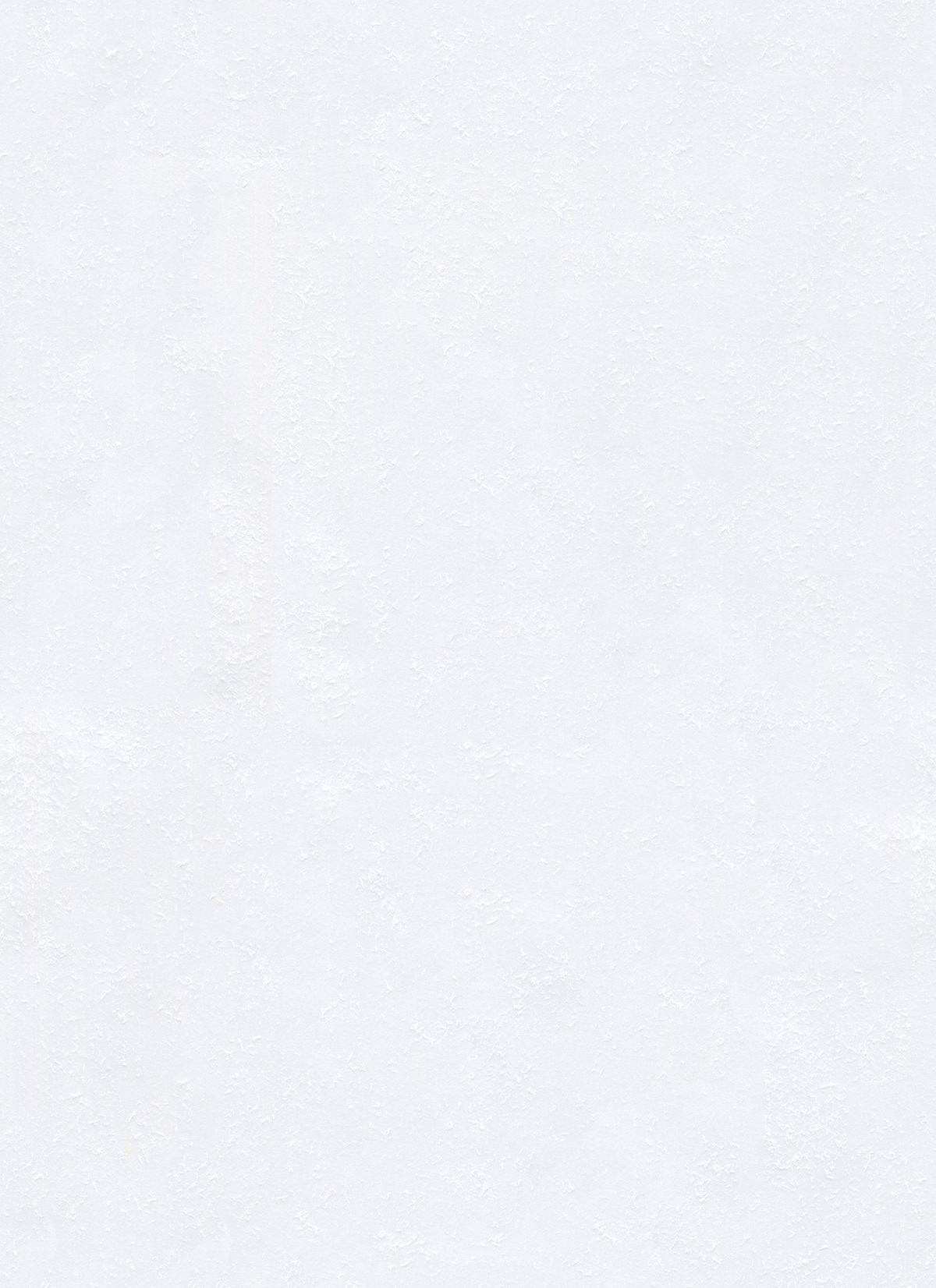
コメントを残す