日の光は、宇宙であっても等しくすべてを照らすらしい。命あるものも、動かぬものであっても。
闇色をした空の中で、強烈な光に照らされながら、ロックオンは奇妙に満ち足りた思いだった。それは、もしかしたら無力感なのかもしれなかったけれど。
アリー・アル・サーシェルは、おそらく仕留め損ねただろう。狙撃手の感覚でロックオンはそれを理解していた。自らが狙った獲物が生きているか死んでいるかを理解できないスナイパーなどいない。
命をかけてまでして、世界を変えるどころか、仇の一つもとることができなかった。それなのにロックオンは、意外なほど平静な気分で宇宙を漂っている。
平静とはいっても、罅の入ったヘルメットのせいで脳に酸素がいきわたらずに頭痛がひどいし、右目はもはや痛いのかどうかすらわからない。体はぼろぼろだった。それなのにどうしてか心は穏やかなのだ。
ロックオンは世界が変わることを疑わない。たとえ今は変わらずとも、自分の意思を継ぐ者が必ず変えるだろう。変革した世界を見られないのは少しさびしいが、「彼」がいることを思えば悲しむほどのことではなかった。
だからロックオンは、死という断絶を前にしてこんなにも静かでいられるのかもしれない。
ああ、世界はこんなにきれいなのにな。
真っ青な地球が、ロックオンの不自由な視界の中で確かに光っていた。宝石のように美しい星は、しかし悲しいかな、理不尽な暴力で満ちていると、ロックオンは知っていた。
ロックオンは今になって思うのだ。俺はそれでも、この世界が好きだったんだな、と。平穏を取り上げられ、この世の一番汚いところを見せられて、それでも世界を壊すのではなく、ただ変えたいと思うほどに。自分はこの世界が愛しくて仕方がなかったのだと。
そう思うと、その世界を内包するあの青い星がとてつもなく愛おしいもののように思えて、もう一度あの世界に触れたくなって、ロックオンはそっと指を伸ばした。美しいだけではないとわかっていながら、触れずにはいられない、その星。
当然のようにするりと宙を掴んだ右手を、悲しいとは思わない。血にまみれたこの手が触れること叶わなくとも、これ以上その血で世界が汚れなければ。どうか、世界が変わるのならば。
こうしてひとりで、それも、悪くない。

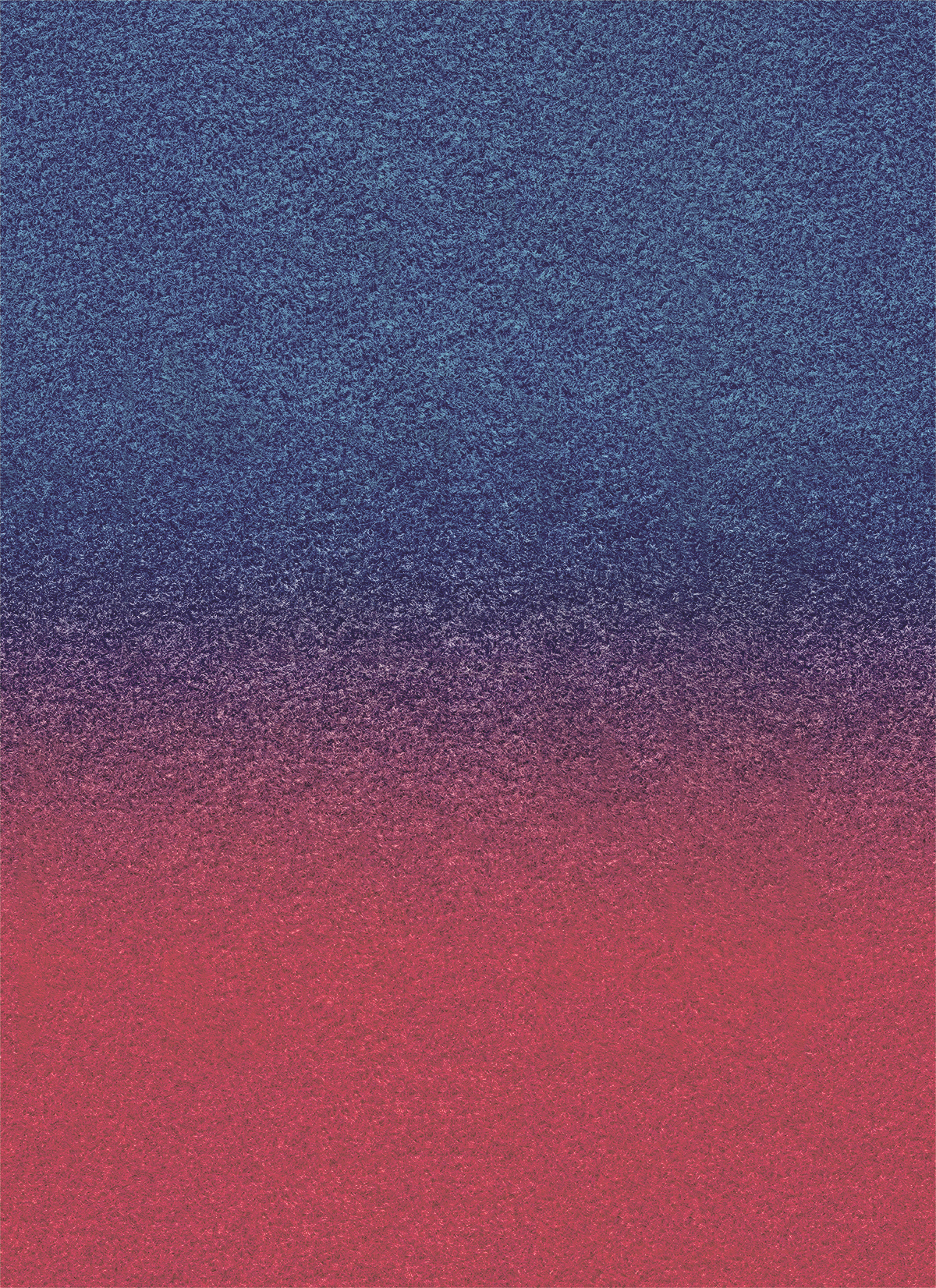
コメントを残す