カルデアの英霊召喚システム・フェイトがようやくまともに機能しはじめ、戦闘員としてマスターとともにレイシフトするサーヴァント以外に魔力的制約によりカルデアで待機せざるを得ないサーヴァントが一定数出てきた頃。時期で言うと、ちょうどオケアノスでの人理復元が完了した頃だったか。
「――管制室の警護? ええと、すみません。なんでまたいきなり?」
「いきなりじゃないんだ。前々から考えていたことで」
ドクター・ロマンがマスターである少女を呼び止めて曰く、『居残り組のサーヴァントに持ち回りで管制室の警護を担当してもらえないか』という提案である。
「カルデアの防衛という観点でいうと、管制室の重要性はマスターたるキミと同程度と言っていいほどに最重要だというのは理解してもらえるかい? シバにトリスメギストス、それにカルデアスといった機材は、優秀なメンテナンススタッフが居るとはいっても、破壊されるようなことがあったら取り返しがつかない。レフ・ライノールの離反のときにこれらの機材が修復可能な程度の損傷で済んだことは、奇跡みたいなものだったんだ」
「でもドクター。管制室に敵が侵入することなんてありえるんですか?」
「理論上、ないとは言い切れない。キミたちがレイシフト先から戻ってこれるということは、敵もその経路を使用するかもしれないということだから。もちろん、セキュリティについては十分配慮してる。だから、念のため、万が一、という措置ではあるけど」
「わかりました、ドクター。もちろんあなたの意見に賛成します。レイシフト前には誰かに管制室に待機してもらうよう、お願いしておけばいいんですね?」
「うん。協力ありがとう。早速今度のレイシフトから――」
二人が段取りを整えている様子を、英霊レオナルド・ダ・ヴィンチが少し離れた場所から見守っている。にまにまとした笑みを浮かべ、しかしこれと言って口を挟むこともない。ロマニ・アーキマンはそれを見て何か勘違いしたようだった。
(どうせボクは臆病者の悲観主義だよ、《最悪》を想像して手を打っておかないと気が済まないような――)
実はこの頃、彼は割とやさぐれていた。声しか聞いていないはずのレイシフト先のサーヴァントから、チキンだの、小物臭いだのと散々の評価をされていたので。しかしレオナルドは彼のその執拗なまでの慎重さを気に入っていたし、カルデアを預かる司令官として当然の差配だとも思っていた。気に入りの人間が文句ない手を打ったことに満足していた。
――と、ここまでは前置きである。
管制室に待機英霊を置く措置を考えついたロマニでさえ、まさかこのとき、こんな事態に陥るとは考えてもいなかった。
(……冗談だろッ)
マスターの少女と彼女のデミ・サーヴァント、マシュ・キリエライトが飛ばされた、端的に説明するなら「異世界」とでも言うべき平行世界から、五体の敵性体がレイラインを通ってカルデア管制室へと送り込まれた。《事態》とはつまり、こういうことだった。
魔神柱を操る人類の敵――魔術王ソロモンからの攻撃までは想定していたロマニも、まさか魔法少女が蔓延るファンシーな世界線から、冗談みたいな形の敵――二足歩行トナカイと巨大ジンジャークッキーみたいなモンスター――がやってくるなんて想定外にも程があった。今回の管制室警護当番であるバーサーカーのクー・フーリンが真顔で霊体を解いて現れなければ、ロマニはもう少しひょうきんなリアクションを取っていたかもしれない。
その時管制室にはロマニを含め四名の所員が勤務していた。オペレータの女性が一名、機材制御と管制補助の男性が二名。彼等は管制室中央に据えられたカルデアスの周囲で各々の業務分担を熟していた。敵はコフィンから伸びるレイラインを辿ったものであるから、やや離れた場所に安置してあるマスターとマシュ用のコフィンのすぐ傍に出現した。マスターのオーダー以外は言うことを聞かないバーサーカーというサーヴァントの性質上、クー・フーリンがコフィン脇で待機していたのは僥倖だった。どのカルデアスタッフより近くで敵性体を迎撃することができたので。
通信越しでなく目の前に現れたおかしな敵にロマニがあっけにとられたのは、長く見積もっても一秒に満たなかった。持ち前の危機管理能力――臆病故の、とも――で、持っていた書類を手放しコンソールに飛びつく。
「オペレータ! 緊急放送! 君たちはレイラインの一時凍結作業を!」
カルデアの生き残りたちはいずれも優秀なスタッフたちだ。自失していたとしても、上司の指示に直ちに我を取り戻し、各々が課せられた役割を果たそうとする。
『緊急館内放送、緊急館内放送。管制室に敵襲。戦闘員は直ちに管制室に集合せよ。繰り返す。管制室に敵襲――』
オペレータの音声と共に、放送スイッチと連動して照明が赤く明滅する。管制補助の二人はその間に早くも作業を開始していた。もちろん、これもロマニの指示で訓練済みである。
敵がレイラインを辿って管制室に侵入した以上、その侵入経路を放置することはできない。かと言って、それがブレーカーを落とすような単純作業であるはずもなかった。
「予備記憶装置、起動します。安定状態まで残り、五十パーセント、七十、八十五、九十五、……完了」
「現接続環境のキャプチャ取得、完了。記憶装置への転送開始します。……二十パーセント……三十パーセント――」
管制官が読み上げる声の裏で、クー・フーリンが槍で敵を屠る鈍い音がする。二体目。
一体目は出現と同時に切り捨てていた。クッキーの形をしたおかしな敵はゲイボルグで一突きすると脆くも崩れ去った。
「……」
軟い。しかし、やりづらい。二体目を倒すまでにやや時間がかかったのは、周囲の機器を壊さぬように敵を相手取るのに手こずっているからだった。本来なら槍の一振りで弾き飛ばすものを、穂先を手元に戻し、的確に繰り出すというまどろっこしい真似をしなければならない。五体同時出現といえども、歴戦の戦士たる彼にとっては物の数に入らないはずなのだが、ひ弱な人間の方へ行かないよう牽制しながらともなればこれもまた、やりづらい。
「……チッ」
今も一体が、フラフラとカルデアスの方へ向かおうとするのを、背後から締め上げる。トナカイの角が顔に刺さるのが地味に痛いが、どうにか絞め落とすところまで漕ぎ着けた。これで、三体目。
管制補助スタッフが作業完了を伝えたのはそれとほぼ同時だった。
「――百パーセント。キャプチャ転送完了」
ロマニは無意識にほっと息をついていた。やりなれない作業だったが、流石にスタッフたちは優秀だった。手順にミスもなく、すべての作業を最短で終わらせている。
「オーケイ、あとは切断処理のバッチ実行だけだね。君たちも避難して。オペ子ちゃんはもう行ったね?」
「ドクター、あなたは?」
「これが終わったらすぐ向かうから。上司だからね、これくらいは任せて」
二人が避難を開始するのを見送ることなく、コンソールに向き直る。通常の切断処理から抜き出しておいたバッチを実行。端末に白い文字の羅列が浮かび上がっては消える。Done、Done、Done。プログレスバーが伸びる。カウントダウン。3、2、1――――完了。
全作業工程が終了。これで、レイラインを辿ってこれ以上敵が侵入する恐れはなくなった。ずっと燻っていた焦りが、ようやく解ける――かと思った。背後で不穏な破壊音が響いたのは、その時だった。
「クー・フーリン!?」
ロマニは次の瞬間には白衣の裾を翻していた。戦闘域に非戦闘員が割り込むことがどれほどの無謀か、理解していなかったわけではない。しかし、音の出処を目視してしまった以上、放ってはおけなかった。あれは、マスターである少女の使うコフィンだ。
「あれほど慎重にって――ッ」
「うるさい! そいつが勝手に突っ込んだんだ!」
わかっていても、ロマニの口からは思わず文句が飛び出す。すかさず反論するクー・フーリンは、最後の一体を相手にどう仕留めるか逡巡している。ゲイボルグが敵の得物のステッキに絡め取られていて、無理にひきはがすと周辺の機材にぶつかりそうだ。
それを完璧に意識の外に追いやる程、ロマニはコフィンの状態を確認したくてしかたがなかった。コフィンはレイシフトにおける絶対の安全装置。カルデア側からの帰還信号もこの装置を通して送られる。これが壊れてしまえば、いくらレイラインを確保していたとしても帰還は非常に困難になる。不可能とは言わない、特異点Fでのことのように、コフィンを使用せずともレイシフトは可能であるから。しかし、今回は異世界とでも言うべき平行世界へのレイシフトで、イレギュラーが多数発生していることも鑑みれば、下手をするとマシュとマスターを回収することができなくなる――永遠に。
コフィンの上ではクッキーの怪物が伸びている。目も口もチョコでできているのでよくわからないが、ぴくりとも動かない。ステータス表示用の小型ディスプレイが埋め込まれているのはその化物のすぐ脇だった。近づいて覗き込む。旧時代的なTN液晶。少しの問題があればすぐエラーを吐くと、メンテンナンスの度にスタッフが愚痴をこぼしていたのをロマニは知っている。果たしてそこに表示されていたのは――Running(稼働中)の文字。
「よかっ……た」
はあ、と安堵の溜息が漏れた。緊張していた体が弛緩する。状況を思い出してしゃがみ込むような真似はしなかったが、既にそこに至るまでの行動が既にあまりに不用意だったとしか言いようがない。
「おいッ!」
焦ったようなクー・フーリンの声。
それに、顔を上げる暇はなかった。
衝撃。
「アぐッ!」
動かないものだと油断していた怪物の一撃によって、頭脳労働者の薄っぺらい体は軽々と吹き飛ばされる。冷たい床に叩きつけられ、慣性のままに磨かれた床を転がった彼の体はカルデアスの支柱に当たってようやく止まった。
「はッ――カハッ、ゲホッ」
ずんぐりとしたフォルムの怪物は見た目の間抜けさに見合わず俊敏な動作で今しがた自分が吹き飛ばした獲物に近づいた。腹を庇い蹲るようにして彼は胃液を吐いている。失神さえしていないが、とても動ける状態ではない。
クー・フーリンはやや強引に相手取っていたトナカイを伸した。敵は未使用のコフィンにぶつかって鈍い音を響かせていたが、この際気にしてはいられない。そうまでしたが、彼がロマニと敵との間に割り込むことは不可能だった。距離が開きすぎている。敵を前にして舌なめずりをするような知性も持たない怪物は、未だに蹲って動けないロマニに淡々と二撃目を打ち込もうとしている。
「チィッ」
クー・フーリンは荒く舌打ちをし、彼の魔槍を大きく振りかぶった。投擲によって逆転した因果律によって敵は必ず仕留められるだろう――同時に、その周囲にも被害が及ぶのは間違いない。管制室当番中の宝具の使用はマスターによって固く禁じられていたが、こうなっては優先順位というものがある。
狂化がかかっているとはいえクー・フーリンの判断は非常に冷静だったといえる。
しかし。
「だ、めだ……クー・フーリン」
それを止めたのは当のロマニだった。
意識ははっきりしているようだが、とにかく内蔵に負ったダメージが大きくまともに起き上がれないでいる。上げた声はささやかではあったが、クー・フーリンの手を一瞬止めるには十分だった。
その一瞬は果たして誰を救い、誰を殺したか。
敵が振り上げた腕は、一直線にロマニに向かって――振り下ろされ、なかった。
「待たせたね。ダ・ヴィンチちゃん参上だよ」
敵に気づかれぬよう、ギリギリまで霊体で接近していたもう一人の英霊――レオナルド・ダ・ヴィンチが、杖の先端でもって敵の腕を破壊する。そのまま、二撃、三撃。最後の敵はあっけなく無力化され、ぼろぼろと崩れて落ちた。
管制室内は一瞬の静寂を取り戻す。立っているものは二基の英霊のみ。
「これで全部?」
「……ああ」
レオナルドは軽く周囲を見渡した。倒れている五体の敵は、いずれも派手に辺りを汚したり、体の部品を欠損したりすることなく静かに横たわっている。元々ここではない世界の魔物だ、しばらくすればそれらも自然とエーテルに還り消滅するだろう。
「キミにしたら随分おしとやかにやったね」
「オーダーは果たした。あとは適当にやれ」
クー・フーリンは仕事は終わったとばかりに姿を消す。消す、といっても霊体に戻っただけで、まだしばらくはここに居るのだろう。それがマスターのオーダーである限りは。
彼が溶けるように消えた空間をしばらく眺めていたレオナルドは、振り返るとカルデアスの根本で未だに空咳を繰り返している男に向かった。
「おい、生きてるね?」
「なんとか……」
咳をする度に腹が痛むのか、目には涙が滲んでいた。口の端からは吐いた唾液が伝っている。それらを袖で強引に拭って、ドクター・ロマンはゆっくりと身を起こした。
「肋骨が二本はイってる……し、当分食事はできないだろうけど内臓破裂みたいな惨事にはなってない。よかった、本当。ボクもだけど、設備も大きな損傷はないみたいで。いや、後でちゃんと確認して、メンテもしないと」
聞いてもいないのにペラペラと自分の症状を喋っている。なにか話していないと落ち着かないのだろう。その表情は、もしかしたら本人は笑えているとでも思っているのかもしれないが、口角は強張るだけで持ち上がっていない。腹を押さえている手はかすかに震えていた。それに、腰が抜けているのか、いつまでたっても立ち上がる気配がない。
「担架いる?」
「いや、突然通信を切ってしまったから、向こうで彼女たちが不安がっているだろう。一旦は繋ぎ直さないと。手を貸してくれ、レオナルド。……あいててて」
「無理はしないほうがいいぞドクター。避難中のスタッフもすぐ戻ってくる」
「うん。接続だけ先にやっておく」
差し出した手に捕まってようやく立ち上がった彼を、抱きかかえて行ったほうがいいだろうかとレオナルドは大分本気で考えたが、扉の向こうから一時避難していたスタッフが戻ってきたのを見て思いとどまる。
レオナルドが駆けつけたとき、ロマニは体を丸めて苦痛に喘ぎながらもクー・フーリンの加勢を拒んでいた。レオナルドがあと少し遅ければ、彼はまず間違いなく重傷を負い、場合によっては死んでいたかもしれない。かといってクー・フーリンが宝具を使用すれば、彼が体を預けていたカルデアスはただでは済まず、長期間の間人理復元作業が滞ることになっただろう。
状況を考慮すれば、ロマニが取った選択は正しかった――それは、レオナルドも頷くところである。偽りの献身だとか、自己賛美的な自己犠牲はレオナルドの最も嫌うところだが、彼の選択は的確な状況判断に基づくもので極めて合理的だ。だが、《気に入りの人間》がそういう選択をせざるを得ないと言う状況はあまり気分の良いものではない。
凍結処理をしていたレイラインを回復させ、早速異世界のマスターやマシュと連絡を取り合っている彼は、先程まで歩くのも覚束なかったというのをちらとも見せずに振る舞っている。それを、レオナルドは不機嫌な顔で眺める。その機嫌の降下は本人にさえ自覚はなかったが、逆に神経の繊細なロマニのほうが敏感に感じ取っていた。
通信が再び切断され、彼はスタッフたちにいくつか指示を出した後、ちょいちょいとレオナルドを手で呼ぶ。スタッフ達がそれぞれ作業に集中しているのを確認してから、彼は通信の間ひた隠しにしていた疲労を表に出すことを己に許した。痛めつけられた内臓は段々と吐き気すら齎すようになり、もう姿勢を保つことすらきつい。
「ちょっと限界。医務室まで連れてってくれないか? 動けそうもない」
囁くように伝えると、レオナルドはきょとんと目を丸くして、それから、ふふん、まるで機嫌の良い猫のように笑った。
「そのオーダーに応えましょう」
瞬く間に機嫌を回復させたレオナルドは、歌うように応じるとロマニの体を椅子から掬い上げる。
何事かとスタッフたちが振り返る。横抱きにされたドクターは目を白黒させて幾ばくかの抵抗を試みているようだった。
「ふお!? いや、普通に! 普通に連れってくれ!!」
「暴れると肋が痛むよ。ほらほら、おとなしくしておいでよ」
――もちろん、そんなことで万能たる英霊を引き止めることなどできなかったが。

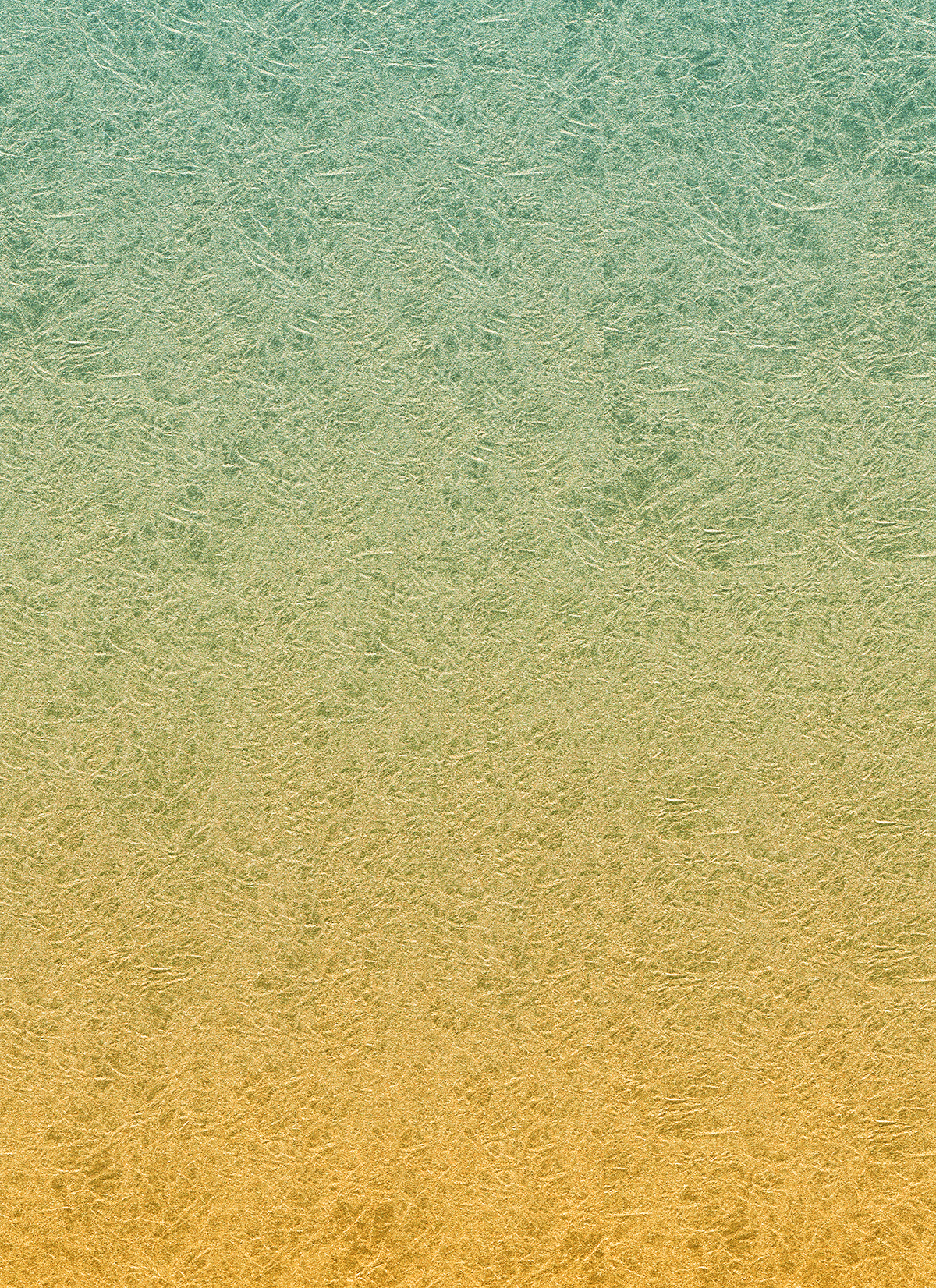
コメントを残す