その夜は大宴会となった。
クリーク海賊団のせいでとても営業できないほどの損害を受けたバラティエはしばらく休業せざるを得ず、となれば備蓄していた大量の食材を消化しなければ駄目になる。そうして作られた数々の料理を前に、酒を飲まないわけにはいかない。——というのは建前で、コックたち皆、サンジの旅立ちに祝杯を挙げずにはいられなかった。なんだかんだ、誰もがあの生意気な若造のことを好きだったので。
明るい内から始まった宴会は、コックが入れ替わり立ち替わり厨房に入り、作った皿が饗されればその度乾杯の音頭が上がり、一口食べて「俺が作った方が美味い」と誰かが叫び、その誰かがまた厨房に入って料理を作り……。それが延々繰り返されて、お月様が昇る頃にはもう、客席は死屍累々の様相である。
あちこちから鼾が聞こえる。もう食えねえ、と誰かの寝言。遠くでちゃぷちゃぷと波の音。うるさいはずなのに妙に静かだと思うのはどういうわけか。
カルネは厨房からもう一本持ち出したウィスキーの瓶を片手にぶら下げて、転がった料理の皿と屍たちを踏まないように、ゆっくりと窓辺の一等席へと向かう。
「これで最後ですよ」
月明かりで、そこだけが明るい。
足を組んで椅子に腰掛けるオーナーゼフは、向いの椅子を引くカルネのほうを見もせずに、グラスだけを突き出した。はあ、と呆れを微かににじませて、グラスに指二本分、琥珀の液体を注いでやる。
「けちくせぇ、瓶ごと寄越せ」
ちらとグラスに視線を落としたゼフは、唸るように言った。そのわりに口の中で舌が回っていない。こう見えてこの人は、とびきりに酔っている。
「いやですよ、あんた、誰が介抱すると思って」
カルネは自分の分も同じように注いで、乾杯、と無理矢理グラスを合わせた。ちっと舌打ちをして、ゼフもそれで諦める。
アルコールが喉を焼き胃に落ちていく感覚を、カルネは一周回って新鮮な気持ちで味わった。向いでは一息でグラスを呷ったゼフが、グラスをテーブルに置く仕草で、肘をついてうなだれる。
こういう夜が、たまにある。
このレストランで一番の大酒飲みであるゼフ。海賊団の元船長で、バラティエのオーナーでもあるからか、彼が酔い潰れることなど滅多とないが、たまにこうして酒を過ごすときがある。そういうとき、相手をするのはカルネだった。人並みに飲み、人並みに酔うのだが、酔いが覚めるのが異様に早いせいで、この時間になると逆に素面であることが多いのだ。まあ単純に、他に起きているやつが居ない、というだけかもしれないが。
パティなどはああ見えて意外と酒に弱い。飲むだけ飲んで、大騒ぎして、すぐに寝る。今も床に大の字になり、鼻提灯を膨らませて眠っているが、明日は二日酔いで苦しむだろう。
副料理長のサンジも、そこまで酒には強くなかった。酔って暴れたりはしないものの、いつの間にか机に突っ伏している。金色の、ひよこみたいに丸っこい頭が、くうくうと幸せそうに眠っている。
それを見ながら飲むのが、オーナーゼフは好きだった。もちろんゼフが口に出して言ったわけではないが、カルネはそう思っている。
「——ありゃあ、酷い嵐だったのさ」
寝言か、譫言か。鼾の大合唱のなか、ともすれば聞き逃してしまうような唸り声で、ゼフの昔語りが始まった。
「俺たちゃ、船に山ほどお宝を積み込んでたし、その客船からも巻き上げてやった。純金のネックレスに、ブルーサファイアの指輪もあったぜ。あんなでっかくて上等なのは、見たことがなかった。金持ちばっかり乗ってた、いいカモだと、思ったんだがなぁ」
「そうなんですねえ」
この話をカルネが聞くのはもう何度目か。この話の続きを、カルネを知っている。つまりカルネは、今回のことがあるより以前から、ゼフとサンジの過去を知っていた。知っていたというのもおこがましいか。なにやら複雑な関係なのだということを、薄らと察していたくらい。だから、誰にも、それこそ相棒であるパティにすら話したことはなかった。
オーナーゼフの昔語りは続く。
「ああ、あの嵐がなければ、あの純金も、ブルーサファイアも、俺のもんだったろうに。根こそぎ奪って行きやがって、今頃海の底だろうさ」
「そりゃ、残念でしたねえ」
「そうさ。おかげで手元に残ったのはちんちくりんのガキ一匹だ」
ゼフはいつもこのくだりになると、そこらで寝こけている金髪頭に目をやったものだった。そうして、ふと目を眇めるのが、オーナーゼフの癖だった。
だが今日は、コックどものなかに目当ての金色は見当たらない。そのせいか、ゼフは彷徨わせた視線をふと、窓の外へと向けた。そのまま、まるでいつものように目を眇めるので、なにを見つけたのだろうかと、カルネも釣られて窓の外を覗き込んだ。
そして納得する。
夜空の真ん中で、まあるいお月様が暢気に浮かんでいる。
カルネは、ゼフのグラスにもう一杯だけ、注いでやることにした。今日くらいはいいだろう。ついでに、わかりきったことだからと、いつもは言わないでおいたことを言ってやる。そう、今日くらいはいいだろう。
「そいつあ、金の髪に、青い目をした、ガキですかい」
ゼフはちらりとカルネを見たが、何も言わずにグラスをとった。味わうように、惜しむように、ゆっくりとグラスを傾けると、再び口を開く。
「ああ、海の向こうにしょうもない夢ばかり見てる、クソガキだよ」

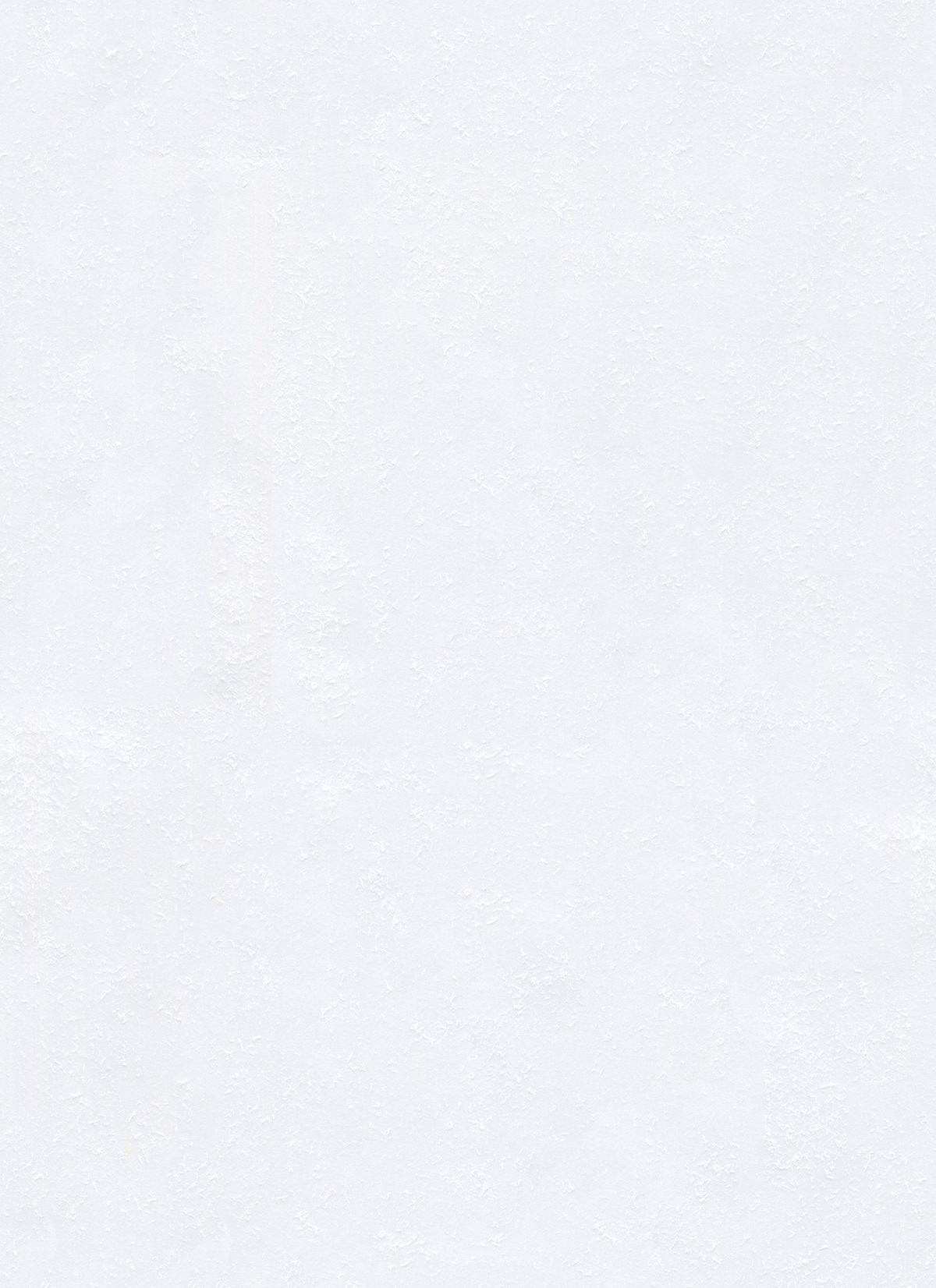
コメントを残す